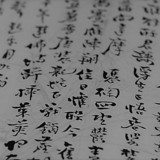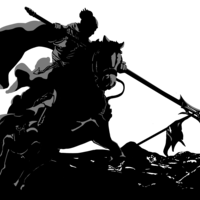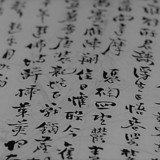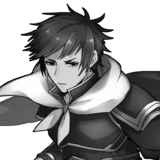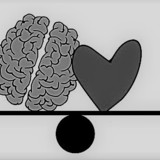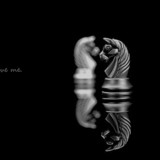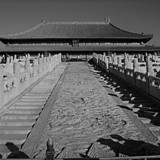記事一覧
三国志が日本に伝えられたのはいつ?どのようにして入ったのだろうか?
三国志の舞台である中国と日本は古くから交流がありましたが、三国志がいつ、どのようにして日本に伝えられたのかは日本史、世界史の授業では誰も教えてくれません。それでは三国志がいつ、どのようにして日本に伝らたのかを解説していきます。
三国志・魏の名将である張郃が一騎打ちでほとんど勝てていないのはなぜか?
魏の名将である張郃、その功績は三国志正史にしっかりと記されています。しかし一方で、三国志演義ではその強さを発揮できずにいます。張郃の一騎打ちの戦歴を紐解いてみましょう。
諸葛亮率いる蜀漢の侵攻を防いだ司馬懿。演義ですと、諸葛亮死後のことは大分端折られてしまうので司馬懿がどのようなことをしたかはあまり書かれていません。ですが、正史ではもちろん記載されていますし、歴史学的には非常に重要な部分です。司馬懿の後半の人生はどのようなものだったのでしょうか?
三国志を題材にしたゲームや小説・漫画で多いのは劉備(玄徳)あるいは諸葛亮を主人公とした作品です。やはり蜀漢を正当な王朝として考えるのが架空の話の中では流行りなのでしょう。その場合、ラスボスに当たるのは誰でしょうか?董卓や曹操が悪役でそれになることもありますが、圧倒的に多いのは司馬懿です。何故、彼はそのようなポジションになるのでしょうか?
三国志は様々なエピソードがあり、教訓になるものが多々あります。なかでも、ピンチでの対応は三国志から学ぶことができるのです。そこで今回は、三国志からピンチを切り抜ける方法や考え方について紹介していきたいと思います。
三国志演義の序章 黄巾の乱を徹底解説(黄巾 の 乱 わかり やすく)
黄巾 の 乱 わかり やすく! 三国志にはさまざまな合戦や反乱などで群雄たちが領土拡大や政権掌握を理由に争いあいます。本記事では三国志演義の始まりとなる黄巾の乱について解説します。
三国志最強の武将「呂布」。しかし、三国志演義に登場する呂布の一騎打ちの結果はイマイチです。その対戦内容を見ていきましょう。
三国志から人生の教訓を得よう!考え方が変わるエピソード・名言!
三国志には数々のエピソード・名言が存在しています。そのエピソードの中には、人生の教訓を得ることができるようなエピソード・名言があるのです。そこで今回は、人生の教訓を得て考え方が変わるエピソード・名言を紹介していきます。
諸葛亮(孔明)亡き後の蜀の主役は、諸葛亮(孔明)の後継者という扱いの「姜維」になります。姜維の武勇について振り返ってみましょう。
三国志は私たちに楽しさを与えてくれます。三国志の楽しみ方は人それぞれ、それこそ千差万別の楽しみ方がありますので、三国志ファンの方々がどのようにして三国志を楽しんでいるのかその実例を本記事のテーマとします。
211年、諸葛亮(孔明)が企てた天下三分の計をいよいよ実行するための行動が開始されます。益州(蜀)は天下を三分して力の均衡を図るための強力な地盤となります。当初、劉璋(季玉)を除いて蜀を支配することは、それ程難しくないと考えられていましたが、甘くはありませんでした。劉備(玄徳)は入蜀に際し大苦戦を強いられるのです。
三国志には実に多くの一騎打ちがあり、それにより戦局が大きく変わるという事が多々ありました。また一騎打ちを行うことで相手に脅威を与えることができ、さらには下の者「士気を上げる」ことにも役立っていました。ここではそんな一騎打ちにまつわる話を紹介したいと思います。
三国志演義、序盤から数々の見せ場があります。その中で印象深いものの一つが曹操による徐州での大虐殺でしょう。父親を殺された曹操が復讐のために徐州に攻め入り、劉備がわずかの援軍を率いてやってくる。二人の対称的な姿が映し出されます。その後、呂布や袁術が絡んできて、複雑な人間模様が描かれます。では、正史の徐州での攻防はどのようなものだったのでしょうか?
諸葛亮(孔明)亡きあと後事を託された蒋琬(公琰)と費韋(文偉)
あなたは蒋琬(公琰)と費韋(文偉)をご存知でしょうか?この2名はあまり有名ではないものの、諸葛亮(孔明)が亡くなるほんの数日前に「あなたの後は誰に任せたらよいか?」という質問に諸葛亮(孔明)が挙げた2名です。 本記事では諸葛亮(孔明)という天才に後を託された2名について説明します。
三国志に登場する人物はカッコイイですが、実は失敗も多いです。ダメ上司が多くおり、反面教師にすることができます。そこで今回は、魏・呉・蜀のダメ上司を紹介していきたいと思います。ぜひ、反面教師にしてみてください。
三国志・一騎打ちの勝率で父親である張飛と関羽を凌駕した張苞と関興の活躍ぶり
蜀の猛将「関羽」と「張飛」にはそれぞれ息子たちがいました。三国志演義ではその息子たちが、父親以上の活躍を見せているのです。 「張苞」と「関興」の一騎打ちの成績に注目してみましょう。
三国志が中国を舞台にしている物語なのは理解している人も多いですが、実際の舞台となった土地を見に行った人は少ないでしょう。 そこで今回は三国志の舞台になった土地が現在どうなっているのか、現在の状況を紹介します。
歴史は延々と続くものですから、正史三国志の時代のスタートはいつなの?と明確に示すことはできません。ですが、物語である三国志演義では明確なスタート地点があります。黄巾の乱です。黄巾の乱は歴史の授業にも出てくる、学問的にも大きな事件でです。壮大なる三国志の幕開け、黄巾の乱。一体どのような事件だったのでしょうか?
赤壁の戦い後、天下三分の計実現のために益州(蜀)攻略を模索していた劉備(玄徳)、諸葛亮(孔明)でしたが、逆に蜀からも漢中の張魯(公祺)に狙われていることを察知した人物たちが、外部から強い指導者を招き入れ、蜀防衛を図ろうと画策していました。その筆頭となって行動したのが張松(永年)でした。
結婚指輪が習慣づいていなかった三国志の時代は既婚者をどう見分けたのか?
左手の薬指に指輪をはめている男女を見ると「この人は既婚者だ」と容易に判断することができます。しかし、結婚指輪が習慣づいていなかった三国志の時代はどのようにして未既婚を見分けていたのでしょうか?