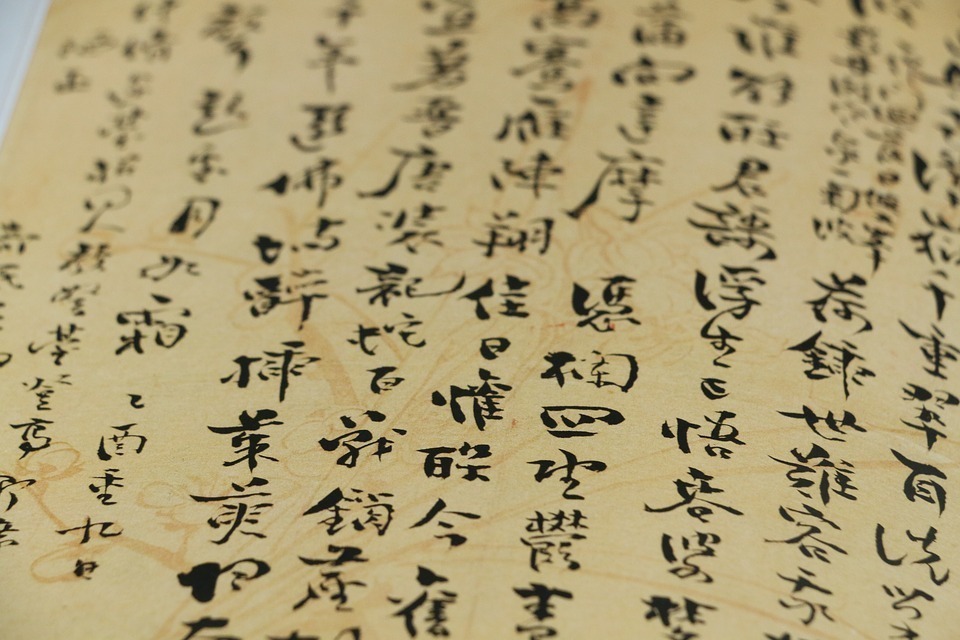諸葛亮(孔明)がこの世を去る直前後事を託した2人
■ 諸葛亮(孔明)がこの世を去る直前後事を託した2人
諸葛亮(孔明)がこの世を去る直前後事を託した2人
諸葛亮(孔明)は五丈原の戦いの最中に陣没しました。その際、戦況を確認するためにやってきた劉禅(公嗣)の使者は、病状が悪化していく諸葛亮(孔明)に対して政治の相談をしました。諸葛亮(孔明)は病の身体を起こし、その相談に親身に乗りました。
使者はその要件が済むとすぐに帰国しようとしました。しかし、その道中諸葛亮(孔明)の命がすでに長くないことを悟った彼は、急いで道を引きかえし「聞き忘れたことがあった」と再び諸葛亮(孔明)の陣営を尋ねました。
すると諸葛亮(孔明)は「君が来ることはわかっていたよ。私の後は誰がふさわしいのかを聞きたいのだろう?」とズバリ使者が聞きたかったことを言い当てました。
そして諸葛亮(孔明)は「蒋琬(公琰)こそふさわしい」と言いました。すると、使者は間髪入れずに「それではその次は?」と聞きます。諸葛亮(孔明)は「費韋(文偉)がよかろう」と答えました。
また使者は「それでは費韋(文偉)の次は?」と尋ねると、諸葛亮(孔明)は押し黙ったまま答えることがありませんでした。
費韋(文偉)の後は自分たちで考えよと言いたかったのか、またはその当時は費韋(文偉)の次にふさわしい者が諸葛亮(孔明)の候補の中にはいなかったのかも知れません。
社稷の才 蒋琬(公琰)
■ 社稷の才 蒋琬(公琰)
社稷の才 蒋琬(公琰)
蒋琬(公琰)は零陵郡湘郷県の出身です。劉備(玄徳)に従って入蜀すると、広都県の長に任命されました。劉備(玄徳)が物見遊山のついでに広都県に立ち寄ると、蒋琬(公琰)は仕事をせずにあろうことか泥酔していました。これに激怒した劉備(玄徳)は蒋琬(公琰)を処罰しようとしましたが、ただひとりそれを阻止しようとした者がいました。その者とは諸葛亮(孔明)です。彼は「蒋琬(公琰)は国家を背負う器であり、百里四方の県を治める程度の才能ではありません」と擁護しました。そのため劉備(玄徳)は罷免するだけに留まりました。しばらくして県令となり、劉備(玄徳)が漢中王に就くと、蒋琬(公琰)は尚書郎に任命されました。劉備(玄徳)が崩御し、劉禅(公嗣)が第2代皇帝になると、諸葛亮(孔明)は丞相府を開き、蒋琬(公琰)に人事を担当させました。蒋琬(公琰)が彼自身の才能を発揮するのは劉備(玄徳)の死後です。
西暦227年、諸葛亮(孔明)は打倒魏のために北伐を開始します。そのとき蒋琬(公琰)は成都(蜀の首都)で留守を守り、丞相の代理を務めます。諸葛亮(孔明)は蒋琬(公琰)のことを深く信頼し、また劉禅(公嗣)に内密の上奏文を送って「私にもしものことがあれば蒋琬(公琰)を私の後任としてください」とまで述べるほどでした。
西暦234年に諸葛亮(孔明)が五丈原の戦いで陣没すると、後任に蒋琬(公琰)の名が挙げられました。諸葛亮(孔明)の死後、蜀は社稷の才・蒋琬(公琰)の手に委ねられました。
政治的後継者
■ 政治的後継者
政治的後継者
諸葛亮(孔明)の政治的後継者に指名された蒋琬(公琰)は尚書令となり、加えて刺史に任命されました。その後、大将軍、録尚書事を歴任しついには王侯のひとりとして封ぜられました。
北伐によって疲弊した国力を回復させんがため、消極策を選択します。諸葛亮(孔明)は北伐開始直前に蜀の生産力を向上させるような政策を実施していましたが、それでもなお国力の衰えを補うことができていませんでした。
蒋琬(公琰)は北伐に備えて内政に努め、ひたすら守りに徹しました。ただし、蒋琬(公琰)が北伐に無関心だったのではなく、漢水を下って魏を討つ計画を立てていました。諸葛亮(孔明)亡きあと、軍事を託された姜維(伯約)は蒋琬(公琰)が提示する消極策に反対し、北伐を強く主張しました。
しかし、蜀における荊州人士の発言力は強く、魏から臣従した姜維(伯約)の言うことに耳を傾ける名士は少なく、蒋琬(公琰)の意見を覆すことができませんでした。
「華陽国志」によると「劉備(玄徳)が入蜀したとき、荊州の出身者が高い地位を占めていた」と指摘しているように、蜀の重要な官職は荊州人士によってほぼ独占されていました。これは諸葛亮(孔明)が自身の基盤である荊州を重視していたためです。
しかし、蜀は荊州を失い、益州しか所有することができなくなると、益州出身者の待遇改善を迫られるようになりました。つまり、荊州出身者と益州出身者の融和を実現させられる広い度量をもったリーダーが求められたのです。
度量の広いリーダー
■ 度量の広いリーダー
度量の広いリーダー
益州の出身者で蜀の人事を担当した楊儀(威公)は大まかな性格で蒋琬(公琰)と議論を交わしている最中でも返事をしないことが多々ありました。ある人が楊儀(威公)を陥れようとして、「楊儀が目上の人をバカにする態度は気に入りません」と蒋琬(公琰)に抗議しました。すると蒋琬(公琰)は「人の顔がみな違うように、人の意見もそれぞれ違う。楊儀が私に賛成すれば、彼の本心ではなく。かといって反対すれば私を批判することになる。楊儀はそこまで考えてあえて返事をしないのだ。これが楊儀の賢さだよ」と言って楊儀(威公)の態度を受け入れました。ちなみにこれが人それぞれ個性があることを意味する「十人十色」の語源です。また、別の者が「あなたはまったくもって諸葛亮(孔明)に及ばない人だ」と批判されたことがありました。そのとき蒋琬(公琰)は「まったくもってその通りだ。事実わたしは諸葛亮(孔明)に及ばない。天才があれだけ努力していたんだ。わたしのような凡人がいくら努力しようとも彼の足元に及ぶことはできない」と辛い批判を認めています。その後、蒋琬(公琰)に辛い批判をした者が別件の容疑をかけられて逮捕されたことがありましたが、蒋琬(公琰)は個人的な感情で彼を処罰することはしませんでした。このように、蒋琬(公琰)は広い度量を持ち、気分に流されず道理に基づいて物事を処理していきました。彼を後任として指名した諸葛亮(孔明)の眼に狂いはなかったのです。
西暦246年、かねてより計画を立てていた川を利用しての北伐を決行しようというときに蒋琬(公琰)は病が篤くなってそのまま死去してしまいました。その後を継いだのがこれまた諸葛亮(孔明)が五丈原で名を挙げた費韋(文偉)でした。
稀代の実務家 費韋(文偉)
■ 稀代の実務家 費韋(文偉)
稀代の実務家 費韋(文偉)
費韋(文偉)は荊州江夏郡の出身でした。幼少のころに父を亡くし、叔父のもとで育てられました。大叔母(父の叔母)が劉璋(李玉)の母にあたるため、荊州から迎えられて入蜀しました。つまり益州在住の荊州名士です。劉備(玄徳)が蜀を建国すると、劉禅(公嗣)の訓導をする役目を担いました。費韋(文偉)は諸葛亮(孔明)から高く評価され、南蛮征伐から帰還した諸葛亮(孔明)は出迎えに応じた文武百官の中から費韋(文偉)を指名して凱旋の馬車に同乗させたと伝えられています。南蛮征伐後、呉への報告のために費韋(文偉)が使者に選抜されました。孫権は生意気な上に人をからかう癖があり、また呉には諸葛瑾(子喩)とその息子の諸葛恪(元遜)と言ったように弁舌に優れた人物がいました。彼らは舌鋒鋭く議論を仕掛け、費韋(文偉)を論破しようとしましたが、費韋(文偉)は正しい言葉遣いと節度をもって道理に基づきつつ返事をしたため、屈服することができませんでした。孫権(仲謀)は費韋(文偉)を高く評価し、「君は天下の良士であり、必ずや蜀の股肱の臣になるであろうから、おそらくここへ何度もくることばできまい」と言いました。五から帰還した費韋(文偉)は昇格し、諸葛亮(孔明)は北伐の折に劉禅(公嗣)に願い出てまで費韋(文偉)を同行させました。
蒋琬(公琰)と同様費韋(文偉)も荊州出身者と益州出身者の橋渡しをする役目を担っていました。特に魏延と楊儀は折り合いが悪く、時に魏延が刀を振り上げて楊儀を泣かせるほどでした。費韋(文偉)は最悪の事態を避けるため、楊儀と魏延との間に割って入り諫め諭して分れさせたと言います。費韋(文偉)の取り計らいがあってこそ、性格に問題のある魏延と楊儀は戦場で能力を発揮できたに違いありません。
四相に名を連ねる費韋(文偉)
■ 四相に名を連ねる費韋(文偉)
四相に名を連ねる費韋(文偉)
当時の人々は諸葛亮(孔明)、蒋琬(公琰)、費韋(文偉)、董允(休昭)の4名を四相と呼びました。董允(休昭)も費韋(文偉)と同格に高く評価された名士でした。董允(休昭)の父は息子の董允(休昭)と費韋(文偉)のどちらがより優れているのかを判断できていませんでした。ある時、同僚の葬儀に参加することになった費韋(文偉)と董允(休昭)は董允(休昭)の父が用意した馬車に同乗することになりました。董允(休昭)の父はわざと粗末な車を用意して二人を乗せようとすると、董允(休昭)は乗ることを渋り費韋(文偉)はそれに平然と乗り込みました。また、葬儀場にて諸葛亮(孔明)やその他高官がすでに集まっている中、彼らの立派な車を見て董允(休昭)は不安げな表情を浮かべていましたが、費韋(文偉)は泰然自若としていました。御者からこのことを告げられた董允(休昭)の父は、費韋(文偉)の方が我が子よりも優れていると大いに評価しました。
また、次のような逸話があります。費韋(文偉)は人並み以上の記憶力を持っており、記録を読む際には、しばらく文書を見つめていただけで内容に精通し、決して忘れることがなかったと言います。いつも朝と夕方に政務を執り、その間には賓客を接待し飲食しながらすごろくをするという生活を送っていました。
費韋(文偉)の後任として董允(休昭)が尚書令に就くと、費韋(文偉)の真似事をしたが仕事が10日も遅れてしまい、董允(休昭)は己と費韋(文偉)の能力差に落胆したと言います。
大宴会での暗殺
■ 大宴会での暗殺
大宴会での暗殺
蒋琬(公琰)と董允(休昭)がこの世を去った後の蜀は費韋(文偉)に頼らざるを得なくなりました。費韋(文偉)も前任の丞相たる蒋琬(公琰)と同様に消極策をとりました。しかし、姜維(伯約)は守りに徹して安寧を貪るよりも北伐を行って勝負に出るべきと主張します。そのように焦っていた姜維(伯約)を費韋(文偉)は諭します。
「我らは諸葛亮(孔明)に遠く及ばない。諸葛亮(孔明)ですら中原を平定することはできなかったのだから、自分たちには到底無理な話だ。まずは国家に平和をもたらし、民の生活を安定させ、謹んで社稷を守ることにこしたことはない。天下統一の樹立は才能のある者の登場を待ってからでも遅くはないではないか。焦って一戦でケリをつけようとしてはいけない。もし、失敗したら後悔しても遅いぞ」と。
蒋琬(公琰)がそうであったように費韋(文偉)も自身の能力の限界を認識していました。諸葛亮(孔明)でさえ成し得なかったのなら、諸葛亮(孔明)を超える逸材の登場を待つしかないのだ。とはいえ、魏を打倒することは蜀の国是。北伐をしなければ蜀そのものの存在理由を失ってしまう。蒋琬(公琰)は晩年に国力が回復しきったと判断して水路からの北伐を実行しようとしました。費韋(文偉)は姜維(伯約)に一万人以上の兵を持たせることを許さなかったが、国力をなるべくすり減らさない程度に北伐を行いました。こうした絶妙なバランスを保ちつつ、諸葛亮(孔明)の後継者たちは蜀の運営を行ったのです。
ところが蜀に不幸が訪れます。西暦253年、大宴会が開催され、費韋(文偉)は酔いつぶれていたところを魏から投降した者の手によって暗殺されてしまいました。蒋琬(公琰)、費韋(文偉)といった荊州出身者と益州出身者の橋渡しをできる者はもう蜀にはいませんでした。費韋(文偉)の死後、蜀は内部崩壊を招くことになります。もしかしたら、諸葛亮(孔明)が今わの際にあえて費韋(文偉)以降の名を出さなかったのは、このことを想定していたのではないかとさえ思えてきます。
まとめ
■ まとめ
まとめ
蜀の天才軍師として名高い諸葛亮(孔明)の後任となった蒋琬(公琰)と費韋(文偉)について説明してきました。
蒋琬(公琰)と費韋(文偉)はどちらも蜀にとって欠かすことのできない逸材であり、諸葛亮(孔明)の眼がいかに正しかったのかがわかります。
残念ながら費韋(文偉)の死後、蜀は滅亡の一途をたどります。後世の目から見ても、もはや彼ら2名を亡くして、蜀が国力を盛り返せるとは到底思えません。
このように蜀は皇帝よりも丞相というNo2の位置にいた名士たちによって存続できていた国でした。