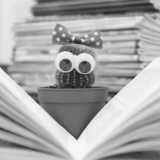徐庶の登場シーン
■ 徐庶の登場シーン
徐庶の登場シーン
徐庶、字は元直、豫州潁川郡の出身です。
曹操に追われ、荊州に逃れた劉備(玄徳)は、劉表の下に身を寄せることになり、新野に駐屯します。ここで劉備(玄徳)に仕えるようになったのが徐庶です。
三国志演義の第35回では、劉備(玄徳)は劉表配下の重臣である蔡瑁に命を狙われます。的盧にまたがった劉備(玄徳)は、壇渓を越え、何とか蔡瑁の暗殺計画から逃れることができ、名士・司馬徽の邸宅に身を隠しました。
そこで徐庶と劉備(玄徳)は出会うのです。
徐庶は、「的盧は馬主に祟る凶馬だが、それを避ける方法がある」と劉備(玄徳)に提案します。劉備(玄徳)が興味を持ってその話を聞くと、徐庶は「まず他人に乗せて、災いがあった後に乗るようにすれば祟られることはない」と伝えました。
劉備(玄徳)がそのやり方に怒りを示したことで、徐庶は劉備(玄徳)の仁徳を知り、仕官することになるのです。
徐庶の驚くべき活躍
■ 徐庶の驚くべき活躍
徐庶の驚くべき活躍
荊州に侵攻してくる曹操軍に対し、兵力の足りない劉備(玄徳)軍は圧倒的に不利な状況でした。これまでも劉備(玄徳)は曹操に敗れ、苦い思いをしています。三国志演義の読者は、またもや劉備(玄徳)は曹操によって荊州を追われるのかとがっかりするのですが、ここで驚くべき活躍をするのが新参者の徐庶でした。
曹操軍の総大将である曹仁は、まず呂廣と呂翔を先鋒として出撃させます。徐庶は軍師としてこの撃退に貢献しました。呂廣は趙雲に、呂翔は張飛にそれぞれ討ち取られています。
これに怒った曹仁は李典と共に、本隊を率いて新野に襲い掛かりました。その数2万5千。
しかも曹仁は、ここで八門金鎖の陣を布くことになりますが、劉備(玄徳)をはじめ、歴戦の勇を誇る関羽や張飛、趙雲はその陣形の恐ろしさを知りません。
しかし徐庶はその陣形を見破っていました。さらにその弱点まで知っていたのです。
劉備(玄徳)は徐庶のアドバイスに従って、見事に曹仁の八門金鎖の陣を打ち破ります。もし徐庶がいなかったら、劉備(玄徳)軍は全滅していたかもしれません。
まさに徐庶は救世主のように登場し、活躍したわけです。
軍師の重要性を強烈にアピールする
■ 軍師の重要性を強烈にアピールする
軍師の重要性を強烈にアピールする
これによって三国志演義の読者は、軍師の重要性をはっきりと知ることになります。いくら関羽や張飛のような猛者がいても、戦術に精通した軍師がいなければここから先の曹操との戦いに勝つことはできないと痛感します。
これまでも、曹操の陣営には荀彧や郭嘉、程昱、荀攸といった軍師がおり、袁紹には田豊や沮授、董卓には李儒、呂布には陳宮、張繍には賈詡といったような軍師が輝きを放っていました。
しかし劉備(玄徳)の陣営には誰もいなかったのです。それが劉備(玄徳)の弱点だったことに読者は気づきます。そして徐庶の加わった劉備(玄徳)軍の巻き返しに期待するのです。
これが「軍師の役割と価値を伝えるプレゼンテーション」であったのならば、まさに大成功です。これまで注目されてきた呂布や関羽などの個の「武勇」から、読者の興味は「智謀」に移っていきます。
徐庶の登場は、まさにその転換期となったのです。
あっと言う間に消える徐庶
■ あっと言う間に消える徐庶
あっと言う間に消える徐庶
徐庶の登場に驚いたのも束の間の話で、あっという間に徐庶は退場していきます。
曹操の軍師である程昱の引き抜き工作によるものですが、読者をさんざん期待させておいて、あっさりといなくなるので驚きです。
読者としては、これまで登場してきた軍師の中で、最も優秀なのが徐庶だろうと思っていただけに失望はかなり大きなものがあったことでしょう。
しかし徐庶はもっと大きな期待感を残して去っていきます。自分よりもはるかに有能な人材が荊州にはいると言うのです。それが「臥龍」の異名を持つ諸葛亮(孔明)です。
これは読者に相当な衝撃を与えました。徐庶がいるだけで劉備(玄徳)軍は無敵になったのではないかと思わせるほどだったのです。その徐庶より凄い人物が加わったら劉備(玄徳)軍はどうなってしまうのか、期待値は高まり、どんどんハードルが高くなっていきます。
そして諸葛亮(孔明)は見事にそのハードルをクリアしていくことになるわけです。
徐庶にこれほどのインパクトがなぜ必要だったのか
■ 徐庶にこれほどのインパクトがなぜ必要だったのか
徐庶にこれほどのインパクトがなぜ必要だったのか
徐庶の登場は、完全に諸葛亮(孔明)登場の布石です。
徐庶の登場によって軍師に注目が集まり、さらに徐庶を上回る智謀を誇る諸葛亮(孔明)の存在に期待が高まるのです。劉備(玄徳)が「三顧の礼」を尽くしたことも一段と読者をワクワクさせることになります。
諸葛亮(孔明)の登場は、まさに「真打ち登場」です。待ってました!の大喝采に包まれます。
三国志演義後半の主役である諸葛亮(孔明)は、こうして華々しくデビューすることになります。
諸葛亮(孔明)をひときわ輝かせるためには、徐庶の存在が必要だったわけです。徐庶が凄ければ凄いほど、その後に登場する諸葛亮(孔明)は引き立ちます。この演出は見事に決まり、ここから読者は諸葛亮(孔明)の虜になっていくことになります。
徐庶の智謀や活躍は、三国志演義の脚色がとても強いのです。ほぼ想像上の人物となっています。これは「三国志正史」と比較すると一目瞭然で、三国志正史では、徐庶は諸葛亮(孔明)を推薦しただけで、劉備(玄徳)の下を離れて曹操の陣営に鞍替えしています。名軍師ぶりは発揮されていません。
まとめ・ちょっとやり過ぎて違和感が出たかも
■ まとめ・ちょっとやり過ぎて違和感が出たかも
まとめ・ちょっとやり過ぎて違和感が出たかも
諸葛亮(孔明)にスポットライトを当てるためとはいえ、徐庶の登場と活躍は強烈過ぎました。鮮烈過ぎて、諸葛亮(孔明)に匹敵するほどの軍師ぶりになってしまったのです。
両者を比較すると、徐庶は「戦術面」だけで優れていて、「戦略面」でも天才的な諸葛亮(孔明)には、総合力で劣るだろうという意見が多いですが、あくまでも推測の域です。
実際に三国志演義に登場するような徐庶であれば、司馬懿を押しのけ、本当に諸葛亮(孔明)のライバルになっていたかもしれません。
結果として、ちょっとやり過ぎてしまったために、違和感が生じ、徐庶の軍師ぶりは諸葛亮(孔明)に匹敵するという憶測を呼ぶことになったのでしょう。でも、このあたりの演出こそが三国志演義の面白さでもありますね。