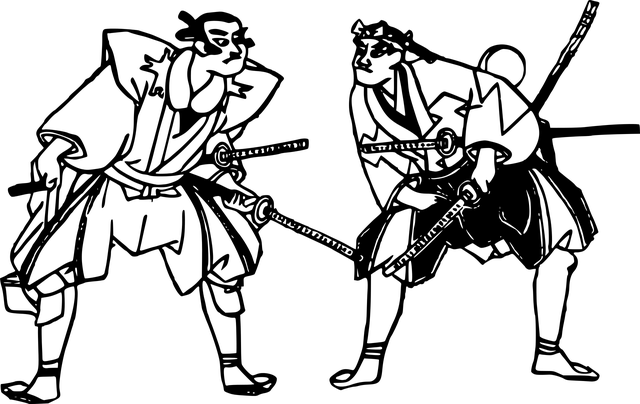空洞化した官僚機構
■ 空洞化した官僚機構
空洞化した官僚機構
中国は古くから官僚制度が発達し、秦漢統一王朝の成立によって高度に完成された官僚体制が出現しました。後漢時代この官僚体制は、中央政府は大尉、司徒、司空といわれる三公を頂点に9つの主要官庁の尾さである九卿以下、最下級官吏の斗食、佐史にいたる諸官で構成されており、地方行政組織は州・郡・県という三段階の行政区画にそれぞれの長官である刺史、太守、県令以下、それらの属官によって構成されていました。
これら諸官はみな一般政務に携わるのですが、その中に宮中で皇帝や後宮に奉仕する特殊な官職が含まれています。その中でもっとも著名なものが中常侍です。中常侍はもともと宦官でなくともなれたのですが、職務の性格上前漢中期から大半は宦官が任用されるようになり、後漢以降は宦官が独占した官職でした。定員は後漢初期には4名、それに次ぐ小黄門が10名であったのが、中期には中常侍10名、小黄門20名に増員されました。
後漢の官僚体制はこのように中央政府と地方行政組織に大別され、中央政府は宮中で執務する内侍官と朝廷で一般政務につく外朝官とに分けられます。この官僚体制の中で後漢時代政治運営の中心となったのは最高官職の三公でもそれに次ぐ九卿でもなく、九卿配下に属する尚書という官職でした。尚書は本来皇帝の秘書官のような役割をしていましたが、やがてあらゆる政務を事実上統轄する重要な官職となります。これに対して三公などはただ事後承諾を与えるのみの名誉職となっていたのです。
この官僚体制の全定員は7567名。それが穀物の量の単位である石で示される給料(実際には穀物と金銭で支払われた)の多少を基準に最高は一万石、次に二千石と続いていき、最低は佐史という役職の八石という全部で10数等級の階層に分けられていました。このほか職掌と称される雑務に従事する下級官吏が14万5千人以上、合計15万2千人ほどが約5000万人に及ぶ漢国民を統治していました。
豪族の子弟が官僚を世襲
■ 豪族の子弟が官僚を世襲
豪族の子弟が官僚を世襲
この官僚体制における官僚はいかにして選抜されていたのかというと、それは主に郷挙里選と呼ばれる官吏登用制度によるものでした。この制度は前漢期から始まったものですが、要するに地方に点在する有能な人材を州や郡の長官が中央政府へ推薦する制度でした。そして州から推薦された者を秀才(後漢以降は茂才)、郡で推薦されたものを孝廉と呼びます。一方、中央政府では三公などの主だった官職には府と呼ばれる官長が附設されており、そこに属僚が配置されているのですが、府の属僚を任命する権限はすべて府の長官が握っています。こうして府の長官はその属僚に地方から推薦されてきた秀才や孝廉を次々と選抜する形で登用していくのです。
ところでこの郷挙里選の候補者はどのようにして選ばれていたのかと言うと、その基準は儒教道徳にありました。漢王朝は孝の精神を重要視していたので三国志に孝行に関する記事が多いのはその影響です。それでは孝行者なら誰でも中央政府へ推薦されていたのかというとそういうことは決してありません。大半は有力者の子弟が選ばれていたのです。また、州や郡の長官の推薦であるため、州や郡の官長に勤務する下級役人が推挙の対象となったこともしばしば見られますが、そもそも州や郡に仕える下級役人はおおむね地方の有力者、つまり豪族の子弟が独占していたので結局は郷挙里選は豪族の中央官界進出の途上に過ぎなかったのです。言い換えてしまえば、後漢王朝の官僚階層は豪族の出身者が中心となっていて、そのために後漢王朝を豪族連合政権と呼ぶことすらあります。
外戚と宦官の権力争い
■ 外戚と宦官の権力争い
外戚と宦官の権力争い
後漢王朝は後漢は14代の皇帝が生まれましたが初代~3代目を除けばほかはみな幼少の皇帝でした。生後100日ばかりで即位し2歳で崩御した者、2歳で即位し翌年崩御した者、8歳で即位し9歳で毒殺された者、それ以外の歴代皇帝をみても大抵は10代で皇帝に即位しています。
このように皇帝が幼い場合、当然幼少の皇帝を補佐する役職が必要になります。しかし、その任はおのずとその皇帝の母親かその一族が当たるようになります。彼らを外戚と呼称しますが、後漢王朝は外戚がしばしば政治の中心となったことで知られています。そして、この外戚の動向が一方で宦官に活躍の場を与えることになります。その実例を次に示しましょう。
外戚と宦官による政治の実績
■ 外戚と宦官による政治の実績
外戚と宦官による政治の実績
4代の和帝が即位したのはわずか10歳の頃でした。そのため先帝の皇后である竇皇后が太后となって和帝を補佐し、政務は竇皇后の兄弟が執りました。和帝は成長すると政治に興味を示し、竇一族による専権を憎んでこれを排除しようとします。しかし武官はみな竇一族の息のかかる者ばかりで、和帝が信用できる武将はひとりもおりませんでした。結局和帝は幼少からいちばん身近で自分に仕えて信用することができる宦官らの力を借りてクーデターを起こし、見事外戚から実権を取り戻します。しかし、次は味方になってくれた宦官らを重用せずにはいられませんでした。この事件が引き金となって後漢ではしばしば宦官が朝廷で威勢をはるようになります。
和帝の皇后は鄧皇后といい、和帝が崩御すると生後100日ばかりの殤帝が即位します。しかし殤帝も他の皇子のように2歳でこの世を去り、その後を13歳の安帝が継ぎました。そしてこの難局にあたったのが鄧皇后です。鄧皇后は安帝が即位してから10数年に渡って朝廷に君臨し政治を執りました。鄧皇后が摂政に在位していた期間、当時の倫理観から一般官僚は宦官を通さなければ太后と接することができず、太后もまた宦官を通さなければ一般官僚と接することができなかったので太后も宦官を相手に政治の相談をせざるを得ませんでした。このほか、和帝の即位以後から後漢の皇位継承は父帝から長子へと順当な相続されることは稀で、しばしば皇位継承権を巡って暗闘が行われましたが、そのような場面に介入することができたのは宦官だけでした。
また、宮中で成長した皇帝は幼少期から女官と宦官だけにしか接することがなく、即位後宦官を完全に信用して重要なポストに任命することも頻繁にありました。このように後漢朝廷内で宦官の勢力は日増しに強くなってゆき、事実上の政権を掌握するようになります。宦官勢力の勢いは桓帝~霊帝の時代にかけて頂点に達しました。
まとめ
■ まとめ
まとめ
あなたは15万人という人数を聞いてどのように感じましたか?多いでしょうか?それとも少ないでしょうか?中国は大変広大な土地なので現代の公務員ともいえる宦官や官吏が15万人いてもおかしい話ではありません。しかしながら、本来政権と国民は皇帝が握るべきなのに1世紀以上に渡って部下の宦官や外戚にそれを委ねてしまったのが漢王朝滅亡の大きな要因です。もしも、後漢王朝の皇帝がしっかりしていれば三国志はこの世に存在していないかも知れません。