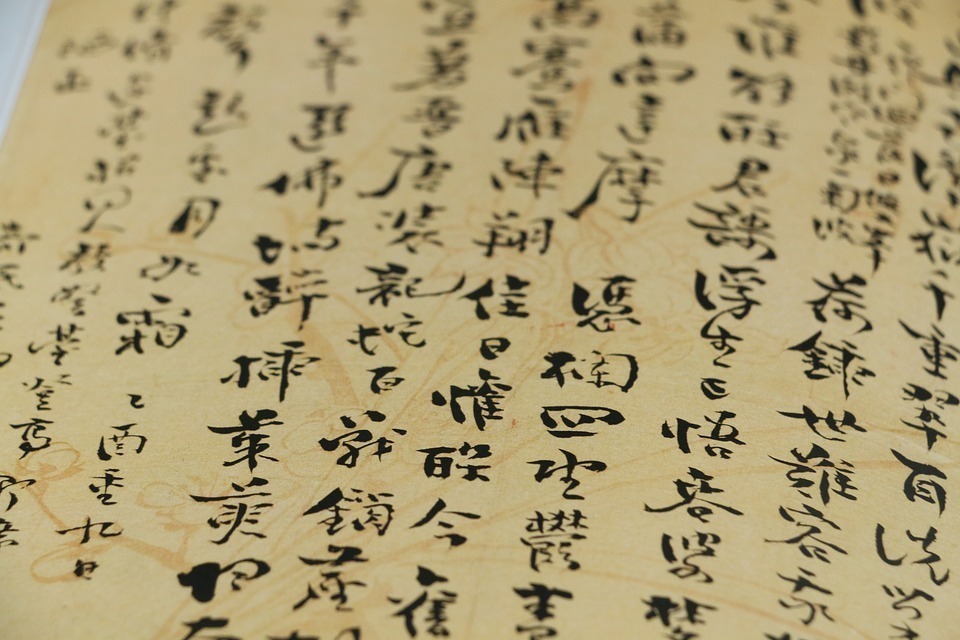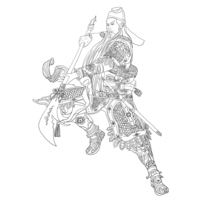若き頃から聡明さを見せた陸遜
■ 若き頃から聡明さを見せた陸遜
若き頃から聡明さを見せた陸遜
若くして名を馳せた周瑜や魯粛、呂蒙らと違い、陸遜は他国では全くの無名ともいえる存在でした。しかし、陸遜の一族は有力者であり、父も九江郡で都尉にまで昇進していました。父は地元でも人徳者で評判も良かったのですが、陸遜が幼いころに死んでしまいます。陸遜は廬江太守の親族である陸康に引き取られ、そのまま移り込みました。
当時の大陸南東は江夏太守だった孫堅が死に、荊州を劉表と袁術が争う姿勢を見せていました。また孫策が袁術の配下として廬江に進出し、陸遜はまだ10歳にも満たない年齢ながら、陸康の子供の面倒を見ながら戦火を逃れています。
すでに聡明さを見せていた陸遜ですが、江東を制圧した孫策が死に、後を継いだ孫権に仕えるようになります。このとき、陸遜はまだ10代後半という若さでもありました。陸遜は文官として従事し、官僚的な仕事をしていました。
あるとき、陸遜が担当していた領地で旱魃が起きてしまいました。領民たちは困窮しますが、陸遜はいち早く蔵を解放し、施しを行っています。領主の財政や兵力を支えているのは民衆であることをいち早く理解していたといえます。
孫権軍で出世していく
■ 孫権軍で出世していく
孫権軍で出世していく
孫策から孫権へと権力が移り変わるころ、孫呉の周辺では反乱を起す山賊や異民族が頻発していました。これには孫権も頭を悩ましますが、陸遜は志願兵を募り、徹底して奥地まで出陣し、力の限り制圧していきました。
反乱軍を制圧することに没頭していたころ、数千規模の反乱を鎮圧したことを受けて、孫権から絶賛されます。事実、孫権は兄孫策の娘を陸遜に嫁がせるなど、重宝していきました。
217年には孫権の側近の一人として仕えるようになり、政治的なの意見を求められることも増えていきます。陸遜は魏の曹操が天下を手中にしようとしている折、国内の安定を図るために軍勢の強化が必要であることを諭します。しかも、孫呉を脅かすのは曹操や劉備(玄徳)などではなく、山越などの周辺民族や反乱軍であると進言します。
孫権は陸遜の話を聞いて同調し、丹陽周辺の三郡を統治させました。曹操は先手を打って丹陽の反乱分子である費桟を扇動し、大軍を以って反乱を起させました。しかし、陸遜はわずかな募兵のみという状況ながら、夜襲を絡めた戦術で翻弄し、兵力の差を補うようにして勝利します。
三郡で精鋭を募り、反乱軍を一層した陸遜のおかげで治安は維持され、民衆からも感謝されるようになっていきます。内部の憂いが無くなったが孫権は、本格的に曹操や劉備(玄徳)に対抗することができるようになっていきます。
荊州攻略に貢献
■ 荊州攻略に貢献
荊州攻略に貢献
荊州では関羽が睨みを効かしており、 対抗する司令官として呉の重鎮である呂蒙が都督を担っていました。呂蒙は前任者の魯粛が打ち出した劉備(玄徳)との共存策を無くし、自力で曹操に対抗しようと考えていました。孫権も関羽の態度に苛立ちを隠せなくなっていきます。
呂蒙は219年に体調が優れなくなり、一時首都の建業に戻ることを決めます。陸遜は呂蒙の帰路で対談することとなり、打倒関羽の策を講じるようになりました。呂蒙は陸遜の先見の明や頭の回転の速さに驚き、孫権と会談した際には、後任の将軍として陸遜を推挙しています。
呂蒙と孫権は、陸遜の優れた才能をお互いに認識し、劉備(玄徳)軍の中でも重鎮となる関羽ですら名前を知らないことで、適任者であることを確認します。陸遜は孫権に召し出されており、呂蒙の代理として荊州方面に赴任させることを決めました。
陸遜は関羽を油断させるために、偽りの手紙を出して自身の遜った印象を植え付けます。関羽は呂蒙に対しては警戒を怠らなかったものの、陸遜のような戦も知らないような若年者であれば、恐れることはないと考え、呂蒙用に布陣させていた軍を荊州北部にある曹操陣の曹仁が守る樊城へと集結させていきます。
関羽は陸遜への備えを怠るようになったのを受け、孫権は関羽討伐の軍を派遣します。当然呂蒙と陸遜が指揮官として先陣を任され、電光石火のごとく周囲を平定していきました。陸遜や呂蒙は降伏してきた城に関しては寛大な措置を取り、朝廷からの褒美とされる品物を降伏してきたものたちに振る舞うようにしました。
荊州南部の城主たちは劉備(玄徳)軍の援軍を期待するよりも、陸遜らに従ったほうが無難であると思い、瞬く間に領土を拡大させていきました。陸遜は関羽軍の残党を決して雑に扱わず、北上して現在戦っている将兵の家族も丁寧に出迎えました。
やがて関羽が曹操軍の徐晃に敗れると、退路を断ち、完全に孤立させていきます。このときよりも前に、孫権は曹操と同盟を結び、共同で荊州を奪取する段取りを付けていました。周囲を包囲された関羽は遂に捕まり、再三の降伏要求を跳ね返したので、呂蒙によって処断されてしまいます。
呂蒙の死後は呉の中枢を担う
■ 呂蒙の死後は呉の中枢を担う
呂蒙の死後は呉の中枢を担う
陸遜が世に名を知らしめたのが30代半ば頃であり、同世代には朱然がいました。朱然は若くから呂蒙らの陣で前線を任されており、軍事面では先に評価をされています。陸遜は地方では若き名将として名を残していましたが、まだ呉の全土を任すには信頼が乏しかったといえます。
呂蒙はその辺りを汲み、病によって自身の死期が近いことを悟ると、荊州などの守備を任す後継者に陸遜ではなく朱然を推しています。呂蒙の前任者である魯粛や周瑜はそれぞれ若くして名を残し、主君である孫策や孫権に最も評価をされていたこともありました。その両者に高く評価されて前線で活躍していたのが呂蒙でしたので、孫堅の頃から仕えている諸将たちも納得して臣下となっていました。
孫権から強い信任を得る
■ 孫権から強い信任を得る
孫権から強い信任を得る
いくら関羽を倒したとはいえ、荊州攻略の主力は呂蒙が自ら率いていたことから、陸遜にはそこまでの実績がないと呉の諸将から評価されていました。しかし、陸遜はそんな周囲の声を気にせず、荊州で関羽軍から投降した者たちが一向に活躍する機会がないことをみて、建業にいる孫権に自ら何とかしてほしいと上奏しています。
自身のことよりも、投降者のことまで気にかけている陸遜の視野の広さに孫権は関心し、陸遜の進言に従うようになっていきます。孫権の強い信任を得ていく陸遜は、呂蒙が亡き後の呉の命運を任されるようになっていきました。呂蒙の心配を寄せ付けないほどに成長していくこととなります。