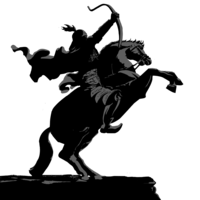陸遜(伯言)の出生
■ 陸遜(伯言)の出生
陸遜(伯言)の出生
陸遜(伯言)は呉の中でも呉郡四姓の名門として知られている陸家の生まれで、陸家のなかでも分家として育った陸遜(伯言)でしたが、父親や祖父が後漢朝の官僚であったため、エリートとして育てられました。早くして陸遜(伯言)は父親を亡くしますが、陸家の本家である陸康のもとで生活を送ることになります。
しかし、この陸康が袁術からの協力要請を断ってしまいます。これにより当時は袁術の傘下にいた、後の小覇王である孫策によって陸家はボロボロにされてしまいます。陸遜は他の一族の子ども達と疎開に出ていたため、この場にはおらず一命を取り留めることになります。そして、疎開組の中でも再燃用であった陸遜が一族を取り仕切ることになります。ちなみにこの時、陸遜はだいたい12歳と言われています。
陸遜初めての仕官
■ 陸遜初めての仕官
陸遜初めての仕官
その後、その土地は孫策の所領となっています。正史では陸遜が出てくるのは孫策がなくなった後に、孫策の弟である孫権が幕府を開いた時に仕えたところです。陸遜は最初、そこまで地位があったり権力がある職から始まったわけではありませんでした。
元々、陸康の子である陸績が孫権に仕えていたため、陸遜は曹令史という立場からのスタートとなります。そんな立場にもめげずに飢餓対策や大規模反乱の討伐などの任務で功績を残していき、自分の立場を徐々に築いていきます。
陸遜は不本意な死を遂げる
■ 陸遜は不本意な死を遂げる
陸遜は不本意な死を遂げる
こうして、呉の中心人物となっていった陸遜が命を落とす原因となったのは、仕えていた孫権の後継者を決める争いである「二宮の変」です。陸遜は丞相という立場まで出世しており、国内でも上の方に立っていた陸遜ですが、後継者争いの問題で孫権と相容れない関係となってしまいます。
後継者争いは「孫和」と「孫覇」のどちらが後を継ぐかという問題でしたが、陸遜は「孫和」を擁護していました。
しかし、これが気に食わなかった孫覇を推す派閥は陸遜のことを孫権に伝えます。これに感化されて孫権は陸遜に罵倒するような手紙を送ります。ずっと仕えていた孫権に罵倒されてしまった陸遜はこの手紙を読んでしまい、体調を崩し憤死しました。こうして、陸遜の一生を幕を閉じることになりました。
陸遜(伯言)が呉を救ったきっかけ
■ 陸遜(伯言)が呉を救ったきっかけ
陸遜(伯言)が呉を救ったきっかけ
陸遜が評価されているのにも理由があります。
生い立ちはそこまで派手ではありませんが、戦場での功績を見ると目を見張るものがあります。
孫権に命を受けていた陸遜は10年以上にわたって、呉に反する異民族や賊などを度々討伐し、その度に自分の兵隊に討伐した兵を加えていき、兵力を兄弟にしていきました。
これは当時兵力が不足していた呉にとってはとてもありがたいことであり、願ってもいないことでした。これが陸遜が名を轟かせるきっかけになりました。
さらに、呉の運命を左右するような出来事でも陸遜はその才能を発揮します。
呉が劉備軍と同盟を結んでおり、曹操率いる魏の勢力と戦っていときまで遡ります。この同盟は魏を倒すために協力する同盟ではありましたが、荊州の地を巡り、険悪な状態が続いていました。
すでに決裂していると言っても過言ではないくらい状況は悪化しており、呉の魯粛の尽力のおかげで領土の一部を割譲するという話で手が打たれました。
陸遜が目立つきっかけをくれた人物
■ 陸遜が目立つきっかけをくれた人物
陸遜が目立つきっかけをくれた人物
しかし、呉の国内では「蜀軍と争うことになったとしても全ての領土を奪い取るべき」という声が止みませんでした。そのあとに孫権が曹操に降伏し停戦状態になると、この声はさらに大きくなりました。この意見を主導していたのがすでに呉の中ではそこそこの地位があった呂蒙とそこまで目立ってもいなかった陸遜でした。
当時、病を患っていた呂蒙と陸遜は面会し、荊州を守っている蜀の武将関羽は油断させれば始末できるという意見を述べます。これに呂蒙も同意して、呂蒙の後任を陸遜が担うことになりました。呂蒙も孫権に「自分の後任は陸遜がよい」ということを伝えています。この進言を受け入れた孫権は陸遜を偏将軍に任じ、荊州に陸遜を送り込みました。
陸遜はとにかく関羽に低姿勢の書簡を送りつけ、油断を誘いました。最初は呉への警戒を強めていた関羽もこの低姿勢な態度や優秀な武将であった呂蒙の病、それに代わってきたのが無名の陸遜ということで、すっかり油断してしまいます。そして戦力を減らし、前線に送り込んでしまいます。
絶好の機としていた呉は関羽を討つために軍を出します。呂蒙と陸遜が荊州を手早く抑えて、関羽を捉えて殺します。これで荊州南部を完全に手中に収めます。当時、軍神と言われていた関羽を討つのは至難のことであり、功績としては大きいことでした。
この荊州制圧の後に呂蒙が本格的に病に倒れてしまい、荊州などの後処理なども六層が対応することになりましたが、見事にこれをこなしました。
軍師としての力量が光りだす
■ 軍師としての力量が光りだす
軍師としての力量が光りだす
ここから陸遜の軍師としての力量が世界に轟くことになります。まずは荊州を奪還したあと、もちろん蜀の軍は関羽の敵として陸遜を討ちにきます。ここで陸遜は劉備を警戒し、ただ衝突しても負けてしまうと悟り、戦力を温存して後退します。これに国内では不満の声が高まります。
しかし、後退して一度劉備の軍の布陣を観察することでその弱点を見抜き、劉備の軍に火種を持って突っ込むことで火攻めにするという作戦を思いつきました。この作戦が的中し、劉備軍は戦力を半分を失って自国に逃げることになりました。
このあと、呉は再び魏と交戦状態に入り、陸遜は魏の対策のために本国に帰ることになります。
そこで孫権が立てた作戦を総指揮を陸遜が務めることになります。この作戦は成功し、当時対呉戦線の総司令官であった曹休が見事に引っかかり、曹休軍が甚大な被害を受けることになります。
魏に対しても蜀に対しても勝利した陸遜の名声はこれを機に広がったと言えるでしょう。この功績が評価され軍部のトップである上大将軍に任命されます。
まとめ
■ まとめ
まとめ
呉の中でもメジャーな武将ではないにも関わらず、次々と功績をあげていき、最終的には軍部のトップに立った陸遜ですが、呉の歴史の中では必要不可欠な人物だったことがわかります。まさに「縁の下の力持ち」という言葉が似合うような武将と言えるのではないでしょうか。