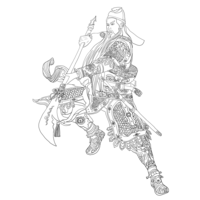貂蝉を巡ってバトル勃発。呂布(奉先)の裏切り
■ 貂蝉を巡ってバトル勃発。呂布(奉先)の裏切り
貂蝉を巡ってバトル勃発。呂布(奉先)の裏切り
三国志初期に猛威を振るっていた董卓(仲穎)ですが、その地位を確固たるものとした一つの要因として挙げられるのが最強のボディーガードである呂布(奉先)です。彼はもともと董卓(仲穎)とは敵対する側でしたが、董卓(仲穎)が天下に名だたる最強の馬「赤兎馬」を送ったり、優遇措置を取ったりするなどの策を施し、自分の軍に迎え入れました。
そんな裏切りの前科がある呂布(奉先)ですが、結局は主(義理の父)である董卓(仲穎)をも裏切ることとなります。
時は暴政を振るう董卓(仲穎)がまさに天下を取ろうとしていたころ、このままではいけないと思う者は多く、董卓(仲穎)を止めなければいけないと思っていたものばかりでした。しかし董卓(仲穎)の軍勢は強く全く歯が立ちません。そこで内政を司る王允は呂布(奉先)と董卓(仲穎)を仲たがいさせるという策を立てました。
二人に対し中華で一番の美女とされる貂蝉を与えるといいました。二人はまんまと貂蝉の取り合いをするようになり、最終的に呂布(奉先)が董卓(仲穎)を殺してしまうのです。あと一歩で皇帝の座につけるというところまでいった董卓(仲穎)ですが、自身の側近呂布(奉先)に裏切られ野望を遂げることはできませんでした。
補給を絶って孫堅(文台)を困らせた袁術(公路)の裏切り
■ 補給を絶って孫堅(文台)を困らせた袁術(公路)の裏切り
補給を絶って孫堅(文台)を困らせた袁術(公路)の裏切り
この裏切りも上記と同じく、董卓(仲穎)が絡む話ですが、ここには中華の覇権争いが凝縮されています。
暴政を振るう董卓(仲穎)を止めようとする武将は多く、考え方は違っても「董卓(仲穎)は倒さなければいけない」という共通認識が生まれました。そこでできたのが「反董卓連合」です。1つの勢力では太刀打ちできない董卓軍でも、全員が結託すれば打ち滅ぼすことができると考えたのです。
これで勃発した董卓軍VS反董卓連合で初陣を任されたのが董卓軍は華雄、反董卓連合軍は孫堅(文台)でした。孫堅軍が有利になり、相手を押していたのですが、ここで思わぬ落とし穴に落ちることとなります。
それは補給係である袁術(公路)が補給を怠ったのです。通常に補給すれば勝ちは見えていたものの、一枚岩になりきれず華雄軍が勝利してしまいました。
「反董卓連合軍が勝利した後に孫権軍が強くなるのを恐れた」という袁術(公路)による裏切りがなければ反董卓連合はあっさり勝利したかもしれませんが、こういった足の引っ張り合いや意見の食い違いにより反董卓連合は瓦解することとなりました。
(キングダムを読んでいる人に分かりやすく言うと秦を滅ぼそうとする合従軍が内輪もめで崩壊してしまったという感じです)
恩を仇で返す。誰もが驚く呂布(奉先)三度目の裏切り
■ 恩を仇で返す。誰もが驚く呂布(奉先)三度目の裏切り
恩を仇で返す。誰もが驚く呂布(奉先)三度目の裏切り
さて、上記で主にして義理の父である董卓(仲穎)を討ってしまった呂布(奉先)ですが、もちろんそのまま董卓軍の大将になったわけではありません。残党兵は躍起になって彼を追い詰めます。しかし元董卓軍のまとまりはなく、呂布(奉先)を追ったり、内乱が勃発したりと大忙しという状態でした。そのため無敵を誇る呂布(奉先)を捕らえることはできなかったのです。
そしてその呂布(奉先)がどうなったかと言うと劉備軍にかくまわれることになりました。劉備軍は当時まだ弱小で豪傑は一人でも欲しいところだったのです。とはいえ義兄弟である張飛(翼徳)は呂布(奉先)を自軍に入れることに大反対でした。それでも劉備(玄徳)の決定に逆らうことはできず泣く泣く承諾しました。
そんな状況下で劉備(玄徳)が城の留守を張飛(翼徳)に任せたことがありました。張飛(翼徳)はホームだから気が緩んでいたのでしょう。酒を飲んでしまい泥酔状態に。呂布(奉先)はこれをチャンスと見るとその城を乗っ取ってしまったのです。
もちろん落ち度は張飛(翼徳)にあるのですが、これに関しては呂布(奉先)の裏切りの方が、インパクトが強く、「最強だけどすぐ裏切る奴」というレッテルが張られるようになりました。
赤壁の戦いで勝利を手繰り寄せた黄蓋(公覆)の裏切り
■ 赤壁の戦いで勝利を手繰り寄せた黄蓋(公覆)の裏切り
赤壁の戦いで勝利を手繰り寄せた黄蓋(公覆)の裏切り
赤壁の戦いの功労者と言ったら大都督として孫権軍、劉備軍をまとめた周瑜(公瑾)、奇策に次ぐ奇策で曹操軍を翻弄した諸葛亮(孔明)が真っ先に頭に浮かぶことでしょう。しかし、黄蓋(公覆)の存在無くしてこの戦で勝利をものにするのができなかったのではないかと思っています。
黄蓋(公覆)がやったことはスパイ工作です。まずは呉の意思に歯向かったとして自分をボコボコにさせます。そして瀕死の状態で「呉に恨みがある」という体で曹操軍に寝返りました。見事曹操(孟徳)をだますことに成功した黄蓋(公覆)は火攻めを成功させ、曹操軍に大打撃を与え孫権・劉備連合軍に大きな戦果をもたらしたのでした。
そして偶然かもしれませんが彼の人生そのものがもはや「いい裏切り」でした。彼は元々武将ではなく文官でした。なのに内政や文化事業を手掛けることはなく、武将としての功績しか残さなかったのです。
官渡の戦いを大きく左右させた許攸(子遠)の裏切り
■ 官渡の戦いを大きく左右させた許攸(子遠)の裏切り
官渡の戦いを大きく左右させた許攸(子遠)の裏切り
赤壁の戦いと並ぶ大規模な戦が官渡の戦いです。この戦いは超がつくほど仲が悪かった袁紹(本初)と曹操(孟徳)の戦いでした。許攸(子遠)は袁紹(本初)側にいました。
ある時許攸(子遠)が曹操軍の兵糧に対しての密書を手に入れることに成功しました。その内容は「曹操軍の兵糧が欠乏している」という内容でした。そのため袁紹(本初)に対し襲撃するよう進言したのです。
ところが袁紹(本初)は許攸(子遠)の話を受け入れず、すぐに曹操軍に攻撃を仕掛けることはありませんでした。
それがきっかけで許攸(子遠)は袁紹(本初)を見限り曹操軍に寝返ったのです。すると立場は逆転します。曹操軍に寝返った許攸(子遠)ですが、周りの者は寝返ったことなど知らず、袁紹軍であるかのようにふるまっていた許攸(子遠)に警戒していませんでした。
袁紹軍の食料を焼き尽くし形勢逆転する形となったのです。これにより曹操軍は勢いを増し、
官渡の戦いでさほど苦労なく勝利することができたのです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
野心から裏切る者、忠誠心から裏切るふりをする者の紹介をしましたがいかがだったでしょうか。一筋縄ではいかないのが三国志です。それゆえここまで魅了される人が多いのではないかと思います。
裏切り行為がなければガラッと歴史が変わってしまう故裏切りエピソードに目を付け「もしこの裏切りがなかったら」と想像してみたらより三国志を知ることになるのではないでしょうか。