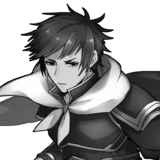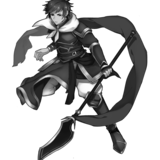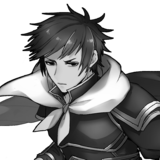姜維の出生
■ 姜維の出生
姜維の出生
三国志のかなり後半の登場にも関わらず活躍し、ファンが多いことでも知られているのが蜀の大将軍・姜維です。
姜維、字は伯約、涼州天水郡冀県の出身になります。もともとは魏に所属し、天水郡の太守・馬遵に仕えていたのです。
しかし蜀の諸葛亮(孔明)が北伐を開始すると、諸県が次々に蜀に呼応して寝返っていきます。疑心暗鬼になった馬遵は、部下である姜維も疑うようになり、行き場を失った姜維は蜀に投降します。
こうして姜維は諸葛亮(孔明)に弟子のように従い、やがて蜀軍を率いる大将軍となって、諸葛亮(孔明)の遺志を継いで北伐を継続していくことになります。
ちなみに三国志演義では、姜維の才に感嘆した諸葛亮(孔明)が、離間の策を用いて姜維を魏から引き抜いたという設定になっています。諸葛亮(孔明)の策略を看破したり、武勇でも趙雲と互角の腕前を披露したことが、諸葛亮(孔明)の目に留まったようです。
姜維の一騎打ち(対蜀戦)
■ 姜維の一騎打ち(対蜀戦)
姜維の一騎打ち(対蜀戦)
姜維は三国志演義において名だたる武将たちと一騎打ちを演じています。相手がなかなか豪華な顔ぶれなことに驚きます。
その登場は三国志演義の第93回ですから、劉備(玄徳)、関羽、張飛などの初期メンバーはすでにこの世を去っていました。
ここで姜維が一騎打ちの相手をした人物こそ、蜀の五虎大将軍の唯一の生き残りである趙雲です。かなり高齢だったと考えられますが、若さあふれる姜維と互角の打ち合いをします。数合戦うと、姜維の勇敢さを評価しつつ退却しています。あの趙雲に黒星をつけた人物こそ姜維なのです。まさに世代交代の象徴的な場面ですね。
直後に姜維は蜀の猛将・魏延と一騎打ちをしています。魏延といえば蜀の大黒柱です。この時の魏延は策があり、数合打ち合うとわざと逃げ出しました。結果としては引き分けですね。
こうして蜀の陣営に組み込まれた姜維は諸葛亮(孔明)の後継者として育成されていきます。
姜維の一騎打ち(北伐)
■ 姜維の一騎打ち(北伐)
姜維の一騎打ち(北伐)
その後、姜維は諸葛亮(孔明)の北伐を継続し、魏領へ度々攻め込みます。
三国志演義は、諸葛亮(孔明)が没してからは加速度的に話が展開していくことになりますので、活躍の期間はわずかではありますが、第107回では魏の武将で陳羣の息子である陳泰を三合も打ち合わずに追い散らしています。さらに司馬懿の息子である司馬師とも一騎打ちを演じ、こちらも数合で打ち破っています。
109回では、蜀の勇将である廖化や張翼を一騎打ちで追い散らした徐質と対戦。姜維は徐質の馬を突いて落馬させ、その隙に討ち取りました。三国志正史にも、郭淮や陳泰に従った徐質が姜維の軍と戦い、戦死したという記載があります。
さらに姜維は大将格である郭淮とも対戦し、郭淮の放った矢を掴み取り、逆にその矢で郭淮を射殺しました。
しかし、車騎将軍にまで昇進した郭淮は、三国志正史において姜維に敗れてはおらず、政敵である司馬懿によって自害に追い込まれています。
110回での姜維は、雍州刺史の王経の配下である張明・花永・劉達・朱芳ら四人を相手に闘うことになりますが、策のためにわざと逃げ出します。四人の武将を相手にしてこの余裕は呂布の武勇を思い出させますね。
姜維の一騎打ち(蜀滅亡)
■ 姜維の一騎打ち(蜀滅亡)
姜維の一騎打ち(蜀滅亡)
大国魏を相手にして、劣勢に追い込まれていく蜀は、もはや風前の灯火となります。
112回以降で姜維が一騎打ちに臨む場面は三回あります。
一度は112回の鄧艾の息子である鄧忠との一騎打ちです。鄧忠は色白で美丈夫ながら、父親同様に武勇にも優れていました。姜維と四十合ほど打ち合いますが、引き分けています。鄧忠はもっと早い時期に登場していれば、かなり人気の武将になったのではないでしょうか。
続いて116回では、姜維はその鄧忠の父親である鄧艾と一騎打ちを演じます。こちらは十数合ほどの打ち合いでしたが、勝敗はつかずに引き分けています。鄧艾親子は姜維にとってまさに天敵だったわけです。
最後の活躍は同じく116回の楊欣との戦いです。三国志正史によると、揚欣は金城太守として蜀征伐の鄧艾に従っています。後に涼州刺史にまで昇進しましたが、異民族との鎮圧戦で命を落としました。
三国志演義では、姜維と一騎打ちを演じ、わずか一合で乗馬を倒され、落馬。部下に助け出されています。
姜維の最期
■ 姜維の最期
姜維の最期
蜀は危険な山越えを決行した鄧艾が成都にいる劉禅を降伏させ、無血開城しています。要塞である剣閣に籠って抵抗していた姜維はその報告を聞いて、攻め寄せてくる鍾会に降伏。その軍師役となり、鄧艾に無実の罪を着せ、護送車で洛陽に召還させます。
姜維は、さらに魏の諸将を虐殺し、最後は鍾会も殺して蜀を復興させようと画策しましたが、看破されて逆に処刑されてしまいました。
姜維は、最期まで蜀に殉じた忠臣ではあるものの、無謀な北伐を繰り返し、蜀の国力を低下させ、滅亡を早めさせた原因とも見られています。三国志ファンでも姜維への評価は大きく分かれるところでしょう。
ただし、諸葛亮(孔明)亡き後、本気で北伐に取り組んでいたのは、姜維だけだったかもしれません。そういう面では、姜維は孤立していたとも考えられます。同じく魏から投降してきた夏侯覇とコンビを組んだりしていますが、もう少し人材が揃っていたら、蜀はこうもあっさりと滅亡しなかったのではないでしょうか。
まとめ・10戦6勝の好成績
■ まとめ・10戦6勝の好成績
まとめ・10戦6勝の好成績
ということで姜維の一騎打ちの対戦成績は、勝率60%ということになります。負けは一度もありません。これはなかなか高い好成績であり、しかも勝利した相手が、趙雲や司馬師、郭淮や陳泰、徐質ですから質も高いですね。
もちろん三国志演義の脚色が強いので、実際に倒したのは徐質くらいのものですが、盛り下っていく後半の物語に彩をもたらしてくれたのは確かです。
魏延、張苞、関興、馬岱、あたりがリタイアせずに、戦場での経験を積んで一騎当千の活躍ができるようになっており(魏延はその器でしたが)、馬謖あたりも処刑されず軍師としての才を開花していれば、姜維や夏侯覇を加えて、かなり期待できる戦力だったのではないかと、妄想してしまいます。もちろんそこに諸葛亮(孔明)が健在であれば、鬼に金棒ですね。
歴史IFの小説があるのであれば、ここからの蜀の巻き返しをぜひ読んでみたいですね。司馬一族を倒し、天下を統一していたかもしれません。