序章:琴音が途絶えた日
■ 序章:琴音が途絶えた日
序章:琴音が途絶えた日
建安十五年、冬。
長江の流れが凍てつく風に震える頃、呉の大都督・周瑜は巴丘の陣営で息を引き取った。享年三十六。赤壁の炎がまだ人々の記憶に新しい、その僅か二年後のことである。
彼の死を最も近くで見届けたのは、妻・小喬であった。
第一章:病床の声
■ 第一章:病床の声
第一章:病床の声
「益州を……取らねば……」
かすれた声が、薄暗い陣幕の中に響く。
小喬は夫の額に当てた布巾を絞り直しながら、その言葉を黙って聞いていた。もう何度目になるだろう。目を覚ますたびに、公瑾は同じことを繰り返す。孫権主公への進言を、天下三分の策を、益州攻略の重要性を――。
「もう、お休みくださいませ」
小喬の声は静かだったが、その奥には十五年分の想いが込められていた。
周瑜の瞳が、わずかに彼女の方を向く。高熱に侵された目は焦点が定まらないが、それでもなお、そこには揺るがぬ意志の光があった。
あの日、廬江の地で初めて出会った時と、同じ光――。
第二章:琴音の記憶
■ 第二章:琴音の記憶
第二章:琴音の記憶
あれは、小喬が十五歳の春だった。
「誤りなど、私には分かりませぬ」
演奏が終わった後、小喬は頬を赤らめながらそう答えた。周瑜の琴はあまりにも完璧で、どこに間違いがあったのか、彼女には分からなかったのだ。
「お嬢様はお優しい。しかし、戦場では一音の狂いが命取りになる」
そう言って、周瑜は再び弦を弾き始めた。
その指は武人とは思えないほど繊細で、けれど一つ一つの音には、刃のような鋭さがあった。小喬は息をするのも忘れて、その姿に見入った。
「私の琴は、天下を治めるためのもの」
彼はそう言い切ったが、小喬にはその音色が、どこまでも寂しく聞こえた。
まるで、彼自身が奏でる音楽に、追いつけないでいるかのように。
婚礼の夜、周瑜は彼女のために『長河吟』という曲を作ると約束した。
「長江の流れのように、永遠に続く愛を込めて」
彼はそう言って微笑んだが、その笑みには、どこか悲しみの影があった。
「でも、完成させられるかは分かりません」
「どうしてですか?」
「私には、時間が足りないかもしれないから」
小喬はその言葉の意味を、あの時は理解できなかった。
第三章:赤壁の傷痕
■ 第三章:赤壁の傷痕
第三章:赤壁の傷痕
「小喬……」
現実に引き戻されたのは、夫の呼ぶ声だった。
しかし、周瑜の次の言葉は、また戦略についてだった。
「荊州と益州を……繋げば……」
「はい、分かっております」
小喬は涙を堪えて頷き、彼の手を握りしめた。その手は、かつてないほど冷たかった。
陣幕の外で、医師が首を横に振るのが見えた。
傷が深すぎる。赤壁の矢が、内に入り込んでいる
医師の言葉が、小喬の胸を突き刺した。
建安十三年、赤壁の戦い。
曹操の百万の軍を前に、周瑜は火攻めの策を用いた。東南の風が吹いた夜、長江は業火に包まれ、北方の覇者は敗走した。
呉軍は勝利に沸いた。
しかし、その喧騒の中で、小喬だけが気づいていた。
夫の顔色が青白いこと。
鎧の下、胸元がわずかに赤く染まっていること。
「公瑾さま、お怪我を……」
「かすり傷です。それより、追撃の準備を」
周瑜は笑って答えたが、小喬にはその笑顔が痛々しかった。
後に知ったことだが、彼は戦いの最中、曹操軍の流れ矢を受けていた。それも、肺に達するほどの深手を。
それでも周瑜は戦い続け、勝利を掴み、そして誰にも傷を悟らせなかった。
「大都督が倒れれば、軍の士気が下がる」
彼はそれだけを理由に、傷を隠し通したのだ。
第四章:最後の琴音
■ 第四章:最後の琴音
第四章:最後の琴音
「小喬……」
再び呼ばれた声は、もう殆ど聞き取れないほど弱々しかった。
小喬は顔を近づけ、夫の唇に耳を寄せた。
「私の琴を……持ってきてくれないか……」
小喬の目から、涙が溢れた。
ようやく――ようやく彼が、天下から私の元へ、戦場から音楽へと戻ってきてくれた。
侍女が琴を運んでくる。小喬は夫の身体を支え、その指が弦に触れるのを助けた。
音は、ほとんど出ない。
それでも周瑜は、満足そうに微笑んだ。
「長河吟……完成させられなかった……すまない」
「とんでもございません」
小喬は涙を拭い、精一杯の笑顔を作った。
「あなた様の音楽は、いつも完璧です」
周瑜はかすかに首を振った。
「君は……あの日と同じ……優しいままだ……」
そして、彼の最後の言葉。
「小喬……来世でも……私の琴を……聴いてほしい……」
琴を抱いたまま、周瑜は静かに目を閉じた。
長江を照らした天才の、その最期は、彼が愛した音楽のように――美しく、哀しく、完璧な終止符だった。
第五章:葬送の日
■ 第五章:葬送の日
第五章:葬送の日
孫権は慟哭した。
「公瑾がいなければ、この孫権に今日はなかった……」
将軍たちは皆、涙を流した。
民は悲しみに暮れた。
しかし、小喬だけは涙を見せなかった。
彼女は夫の愛した琴を抱きしめ、長江のほとりに立っていた。
「あなた様の音楽は、決して絶えません」
小風が吹き、長江の水面が揺れた。
「長江の流れが止まないように、あなた様の志も、琴の音も、永遠に響き続けます」
小喬は琴を胸に抱き、静かに微笑んだ。
夫が作れなかった『長河吟』を、いつか自分が完成させよう。
そう心に誓った。
【史実編】周瑜の死因を医学と歴史から解明する
■ 【史実編】周瑜の死因を医学と歴史から解明する
【史実編】周瑜の死因を医学と歴史から解明する
「既生瑜、何生亮(天が周瑜を生んだのに、なぜ諸葛亮をも生んだのか)」
三国志演義における周瑜の最期の言葉
しかし、これは創作である。
史実の周瑜は、嫉妬に狂って死んだ小人物などではない。彼は度量が広く、才能ある者を認め、天下のために尽くした真の名将だった。
では、なぜ彼は三十六歳という若さで、この世を去らねばならなかったのか?
一、周瑜という人物
周瑜(175年-210年)、字は公瑾。
廬江郡出身の名門の子として生まれ、幼少期から孫策と深い友情で結ばれた。容姿端麗で音楽の才に恵まれ、「美周郎」と称された。
しかし、彼の真価は戦場にあった。
- 赤壁の戦い(208年):三十三歳で大都督として曹操の大軍を撃破
- 荊州攻略:南郡を制圧し、呉の領土を拡大
- 益州進出計画:劉備に先んじて蜀を取る構想を立案
孫権は彼を「兄」と呼び、呉の柱石として頼りにしていた。
二、周瑜最期の記録
『三国志』呉書・周瑜伝によれば:
建安十四年(209年)、周瑜は孫権に益州攻略を進言。自ら大軍を率いて出陣する準備を開始。
建安十五年(210年)、巴丘へ向かう途中、突如として重病に倒れる。
病状は急速に悪化し、数日のうちに死去。享年三十六。
三、死因の諸説
説1:戦傷の悪化
最も有力な説である。
周瑜は赤壁の戦いの前年、江陵攻防戦で流れ矢を受けて負傷している。『三国志』には「周瑜が矢に中(あた)る」と明記されている。
当時の医療水準では:
- 矢の摘出が不完全だった可能性
- 傷口からの細菌感染
- 慢性的な内部出血や化膿
これらが二年後に再発し、致命傷となったと考えられる。
特に、遠征という身体への負担が、傷の悪化を招いた可能性が高い。
『三国志演義』と史実の違い
■ 『三国志演義』と史実の違い
『三国志演義』と史実の違い
羅貫中の『三国志演義』では、周瑜は諸葛亮への嫉妬で吐血して死ぬ。
しかし、『三国志』正史には:
- 周瑜と諸葛亮の直接対決の記録はない
- 周瑜は諸葛亮を「才人」と評価していた
- 嫉妬による死という記述は一切ない
演義の描写は、物語を劇的にするための創作であり、周瑜の人格を貶める誤解を生んだ。
史実の周瑜は:
- 孫権から絶大な信頼を受けた
- 部下からも慕われた
- 魯粛など優秀な人材を推薦した
- 大局を見据えた戦略家だった
「既生瑜、何生亮」という言葉は、後世の創作に過ぎない。
長江に響く琴の音
■ 長江に響く琴の音
長江に響く琴の音
「美周郎」と呼ばれた天才は、なぜ三十六歳で逝かねばならなかったのか。
答えは、時代そのものにある。
戦乱、疫病、医療の限界、過酷な軍務――それらが重なり合い、一人の輝かしい命を奪った。
しかし、周瑜の死は無駄ではなかった。
彼の築いた呉の基盤は、その後も続いた。
彼の戦略思想は、後世の軍師たちに学ばれた。
そして、彼の愛した琴の音は――今も長江のほとりで、風に乗って響いている。
小喬は、夫の死後も長く生き、その琴を守り続けたという。
未完の『長河吟』は、いつか彼女の手で完成されたのかもしれない。
あるいは、完成しないままであることこそが、周瑜という人物の本質なのかもしれない。
――永遠に続く旋律のように、彼の志は時を超えて、今も私たちの心に響き続ける。
長江の流れは今日も悠々と続き、かつて美周郎が見た景色を、変わらず映し出している。

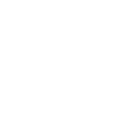
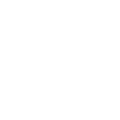
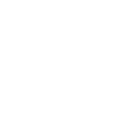











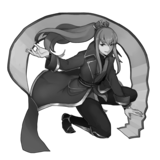











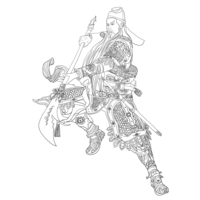


古代の雑学を発信