馬良の白眉は、優れた人の象徴
■ 馬良の白眉は、優れた人の象徴
馬良の白眉は、優れた人の象徴
「白眉」という言葉をご存知でしょうか。実はこの言葉、中国三国時代の一人の人物から生まれた故事成語なのです。その人物こそが、今回ご紹介する馬良(ばりょう)。蜀の名参謀として劉備と諸葛亮を支え、外交や内政で大活躍した人物です。
そんな馬良の人となりと功績が分かる、選りすぐりのエピソードを5つご紹介します。これを読めば、なぜ「白眉」が優れた人の代名詞となったのか、きっとご理解いただけるはずです。
馬氏の五常、白眉最もよし ~兄弟の中で最も輝いた星
■ 馬氏の五常、白眉最もよし ~兄弟の中で最も輝いた星
馬氏の五常、白眉最もよし ~兄弟の中で最も輝いた星
後漢末期の荊州襄陽。名門・馬家には五人兄弟がいました。長男から五男まで、全員の字(あざな)に「常」の字が入っていたため、世間では「馬氏の五常(ばしのごしょう)」と呼ばれていました。
五人とも優秀でしたが、四男の馬良(字は季常)は格別でした。彼の最大の特徴は、眉の中に混じる白い毛。この珍しい容貌と、その卓越した才能から、人々はこう評しました。
「馬氏五常、白眉最良」(馬家の五兄弟の中で、白い眉の馬良が最も優れている)
単に「兄弟一番」というだけでなく、もともとハイレベルな集団の中で、さらに抜きん出ていることを示す最高の賛辞。この故事から、同類の中で特に優れた人や物を「白眉」と呼ぶようになったのです。
ちなみに末弟の馬謖(ばしょく)は、後に「泣いて馬謖を斬る」の故事で有名になりますが、それはまた別の話…。
諸葛亮を「尊兄」と呼んだ唯一の人物
■ 諸葛亮を「尊兄」と呼んだ唯一の人物
諸葛亮を「尊兄」と呼んだ唯一の人物
馬良と諸葛亮(孔明)の関係は、単なる同僚を超えた特別なものでした。
劉備が益州(四川)攻略を進めていた頃、荊州に残っていた馬良は、雒城(らくじょう)陥落の知らせを聞き、諸葛亮に祝いの手紙を送りました。その手紙の中で、馬良は諸葛亮のことを「尊兄(そんけい)」と呼んでいます。
これは目上の人に対して「兄貴」のような親しみを込めた呼び方。通常、天才軍師・諸葛亮に対してこんな親密な呼び方をする人はいませんでした。しかし諸葛亮は一切不快を示さず、むしろ喜んだといいます。
歴史家の裴松之は、二人が義兄弟の契りを結んでいたのではないかと推測しています。冷静沈着な諸葛亮がここまで心を許した人物は、他にほとんどいません。諸葛亮は馬良を「私の右腕となってほしい」とまで言っていたそうです。
孫権を魅了した外交の達人
■ 孫権を魅了した外交の達人
孫権を魅了した外交の達人
建安年間、蜀と呉の同盟関係を強化するため、馬良は呉の孫権への使者として派遣されました。
当時、荊州の領有を巡って蜀と呉の関係は微妙でした。一歩間違えれば戦争になりかねない緊張状態。そんな中での外交任務は、まさに針の穴を通すような難しさでした。
しかし馬良は、その洗練された礼儀と教養、そして誠実な人柄で孫権の心を掴みます。明晰な頭脳で蜀の立場を説明し、同盟の重要性を理解させ、見事に任務を成功させました。
孫権は馬良の人物を高く評価し、「このような人材を持つ劉備は侮れない」と改めて認識したといいます。単なる学者ではなく、実践的な交渉力と政治力を兼ね備えた人材だったのです。
異民族を味方につけた先見の明
■ 異民族を味方につけた先見の明
異民族を味方につけた先見の明
劉備が関羽の仇討ちのため呉に向かう「夷陵の戦い」(222年)。馬良はここで重要な進言をします。
「この地域には武陵蛮という異民族がいます。私は以前から彼らと交流があります。彼らを味方に引き入れれば、戦いを有利に進められるでしょう」
劉備はこれを認め、馬良は見事に異民族の説得に成功。彼らは劉備軍に協力し、呉軍に対して奮戦しました。
このエピソードから分かるのは、馬良が単に中央政府の視点だけでなく、地方の実情や異民族の動向まで把握していたこと。そして彼らとの信頼関係を築く人間力を持っていたことです。現代でいえば、グローバルな視点を持つ国際派エリート官僚といったところでしょうか。
夷陵での壮絶な最期 ~忠節を貫いた文人の死
■ 夷陵での壮絶な最期 ~忠節を貫いた文人の死
夷陵での壮絶な最期 ~忠節を貫いた文人の死
夷陵の戦いは、陸遜の火計により蜀軍の大敗に終わりました。劉備軍は総崩れとなり、混乱の中で撤退を余儀なくされます。
馬良は文官でありながら、最後まで戦場に留まり、敗走する味方部隊をまとめようと奮闘しました。しかし、呉軍に包囲され、ついに戦死。享年わずか36歳でした。
彼は逃げることもできたはずです。文官として後方に下がることも許されたでしょう。しかし馬良は、最後まで劉備への忠節を貫き、武将のように戦場で散ったのです。
もし馬良が生き延びていれば、その後の蜀の苦難の時代に、諸葛亮の右腕として内政・外交の両面で大きく活躍したことは間違いありません。彼の死は、蜀にとって計り知れない損失となりました。
なぜ馬良は「白眉」と呼ばれるにふさわしかったのか
■ なぜ馬良は「白眉」と呼ばれるにふさわしかったのか
なぜ馬良は「白眉」と呼ばれるにふさわしかったのか
馬良のエピソードを振り返ると、彼がなぜ「白眉」の代名詞となったのかがよく分かります。
人格者:誠実で教養があり、誰からも信頼される人柄
知性と教養:学識が深く、物事を深く洞察する力
実務能力:外交交渉や異民族対策など、理論だけでない実践力
人間関係構築力:諸葛亮から異民族まで、幅広い層から信頼を得る力
忠節:最後まで主君への忠義を貫く高潔な精神
「白眉」という言葉は、単に「兄弟で一番優秀」という意味を超えて、多方面で卓越した能力を持ち、人格的にも優れた理想の人物像を表す言葉となりました。
現代でも、組織やチームの中で最も優れた人を「白眉」と呼ぶことがあります。それは2000年前の馬良という一人の優れた人物の記憶が、今も私たちの言葉の中に生き続けているということ。歴史の重みと言葉の美しさを改めて感じさせてくれる、素晴らしい故事成語ですね。
馬良の「白眉」は、単なる容姿の特徴ではなく、その人物の内面の輝きを表す象徴でした。私たちも、外見だけでなく内面を磨き、真の「白眉」を目指したいものです。














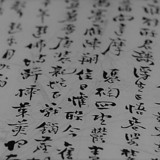











古代の雑学を発信