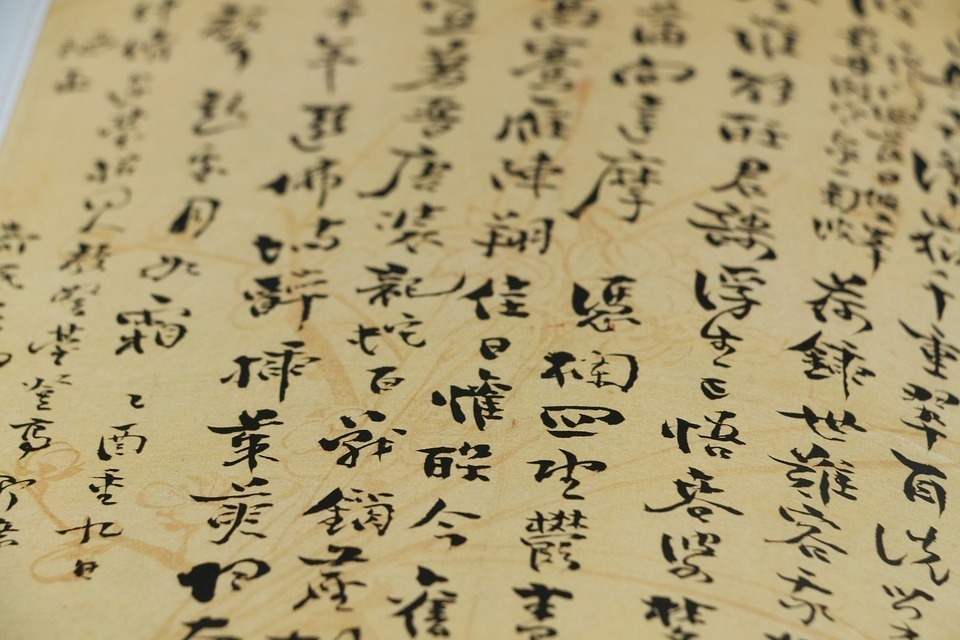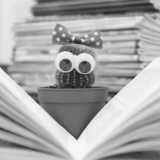冷静なのに熱い漢
■ 冷静なのに熱い漢
冷静なのに熱い漢
武将は熱い者、で軍師は冷静な者というイメージがないでしょうか。実際蜀の人物を見ても張飛(翼徳)は激情型で熱い人物。諸葛亮(孔明)は常に先を見据えている冷静な人物です。しかし、必ずしもそういったわけではありません。趙雲(子龍)は言うことをよく聞き、泥臭いことも不満を言わずこなす温厚な人物ですし、武将に勝るとも劣らない気性の荒い軍師もいます。
徐庶(元直)はまさにその冷静さと熱さを同時に持っている面白い人物といえるでしょう。
彼の冷静な面が分かるのは劉備(玄徳)に「あなたの馬は乗るものに災いをもたらすからまずは他の人に貸して厄を落としましょう」といった時のことです。この時徐庶(元直)は劉備(玄徳)に「人を陥れるようなことをするような者はいらん」と一喝されてしまうのです。ここで徐庶(元直)は冷静に「すいません。あなたがどんな人物か確かめたかったのです」と切り返しました。
一方熱い面はというと、義に熱いため、友人の敵討ちをすることを引き受け、本当に敵を斬ってしまうのです。役人に捉えられるのですが、そのさい違う友人が助けてくれて学問の道に入ることとなります。
偽名を使って生活をする
■ 偽名を使って生活をする
偽名を使って生活をする
元は撃剣の使い手でしたが、仲間に助けられてからは剣を捨て学問に励むようになった徐庶(元直)。そんな彼はそれと同時に名前まで捨ててしまうのです。以降、単福という名前を使い、兵法を学び諸国を旅している浪人となりました。
漫画「三国志」では大きな声で歌っているところを劉備(玄徳)に留められ、そのまま飲みに行き、意気投合し彼の軍師になったのです。
軍師になってからも徐庶(元直)という名を明かさず劉備(玄徳)の元で能力をいかんなく発揮しました。
徐庶(元直)の初陣
■ 徐庶(元直)の初陣
徐庶(元直)の初陣
徐庶(元直)の性格がより分かるのが劉備(玄徳)の元で初陣を飾った際のエピソードです。彼の初陣は自軍2000に対して魏軍5000を相手にしなければいけませんでした。そんな状況にも関わらず「演習にはちょうどいいではありませんか」と笑いながら言っているのです。
実戦を経験したことがない徐庶(元直)でしたが、戦は偶然勝つものではなく、学問からなる「法」によって勝つものだと信じていたのです。
関羽(雲長)、張飛(翼徳)、趙雲(子龍)といった豪傑がいれば2000でも十分に勝てると思っていた徐庶(元直)はあっさり敵軍5000を退けてしまうのでした。
さらにその後曹仁(子考)が25000の兵を引き連れてやってきた際にも「相手は全軍できたので城ががら空きです。奪っちゃいましょう」といい、あっさり敵軍の本拠地である樊城を占有し、この戦に勝利してしまうのでした。
それまで関羽(雲長)、張飛(翼徳)、趙雲(子龍)の個の力に頼った戦い方をしていた劉備(玄徳)ですが、ここで軍師の重要さを知ることとなりました。
徐庶(元直)を欲しがる曹操(孟徳)
■ 徐庶(元直)を欲しがる曹操(孟徳)
徐庶(元直)を欲しがる曹操(孟徳)
さて、こんな優れた才能を持っている徐庶(元直)を曹操(孟徳)が欲しがらないわけがありません。曹操(孟徳)はなんとしてでも徐庶(元直)を自分の軍門に加えようと思ったのです。そこで考えたのが徐庶(元直)の母親(母親は魏国で生活をしていた)を口説くということでした。母親思いの徐庶(元直)なら自分の母親が「魏のために働け」と言ったら魏の軍師になると思ったのです。
しかし徐庶(元直)の母親は劉備(玄徳)が優れた人物だということを知っていたため息子を呼び戻すということはしませんでした。
それでも諦めきれない曹操(孟徳)は程昱(仲徳)に徐庶(元直)の母親の世話をさせ、彼女の字をまねることができるようにしました。
程昱(仲徳)に偽の手紙を書かせ徐庶(元直)に送ると、徐庶(元直)は母親が手紙を書いたものだと勘違いし、魏に戻ってしまうのでした。
母親、まさかの自殺
■ 母親、まさかの自殺
母親、まさかの自殺
魏に戻った徐庶(元直)を見て最初母親は喜びました。しかし「なぜ戻ったのだ?」と言いました。徐庶(元直)は「あなたが手紙を書いたからだ」と言いました。しかし母親は自分が書いたものではないと見破ることができなかったわが子にショックを覚えてしまうのです。さらに自分の君主を捨てて戻ってきたことに対しても憤っていました。
それもこれも自分のせいだと思った母親はなんと自殺してしまうのです。
悔やんでも悔やみきれない徐庶(元直)でしたが、劉備(玄徳)の元に戻ることはしませんでした。
徐庶(元直)の置き土産
■ 徐庶(元直)の置き土産
徐庶(元直)の置き土産
そんな徐庶(元直)ですが、劉備(玄徳)の元を去る際に置き土産を残すのでした。それは諸葛亮(孔明)の存在を教えることです。さらには自ら彼の元に行き劉備(玄徳)の手助けをしてあげてくれと頼むのでした。
この直談判ははっきり言って失敗に終わりましたが、最終的に三顧の礼を経て諸葛亮(孔明)が劉備(玄徳)の元で軍師となったということは彼の助言なくしては起きえなかったのではないでしょうか。
徐庶(元直)は「諸葛亮(孔明)の足元にも及ばない」といっていましたが劉備(玄徳)の元に残って彼と二人で蜀の軍師として活躍していたら三国のパワーバランスは変わっていたかもしれません。
徐庶(元直)のその後
■ 徐庶(元直)のその後
徐庶(元直)のその後
徐庶(元直)は後悔の念と劉備(玄徳)への恩義からその後曹操(孟徳)に一計も系ずることはなかったと言われています。生年だけでなく没年も不詳ということから曹操(孟徳)もどこかで見限って自由の身となった、もしくは処刑されてしまったのかもしれません。
ポテンシャルがありながらもあまり三国志の舞台で活躍できなかった背景にはそういった彼の能力とは直接かかわりのない要因が大きく働いてしまったためです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
波乱万丈にとんだ徐庶(元直)について記載しましたがいかがでしたか。友人想い、母親思いということから彼の行く道が大きく変えられてしまったのが分かっていただけたでしょうか。
とんでもない才能の持ち主、そして熱さもあり冷静さも兼ねそろえている徐庶(元直)を好きになったという人が一人でも増えてくれたらうれしいです。
もし彼がいなかったら劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)は会うことがなかったかもしれない。もし彼がそのまま劉備(玄徳)の元で軍師として活躍していたら諸葛亮(孔明)と共に最強の蜀を作り上げることができたかもしれない。そんな想像を張り巡らせてしまいます。