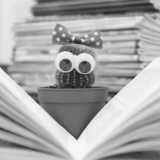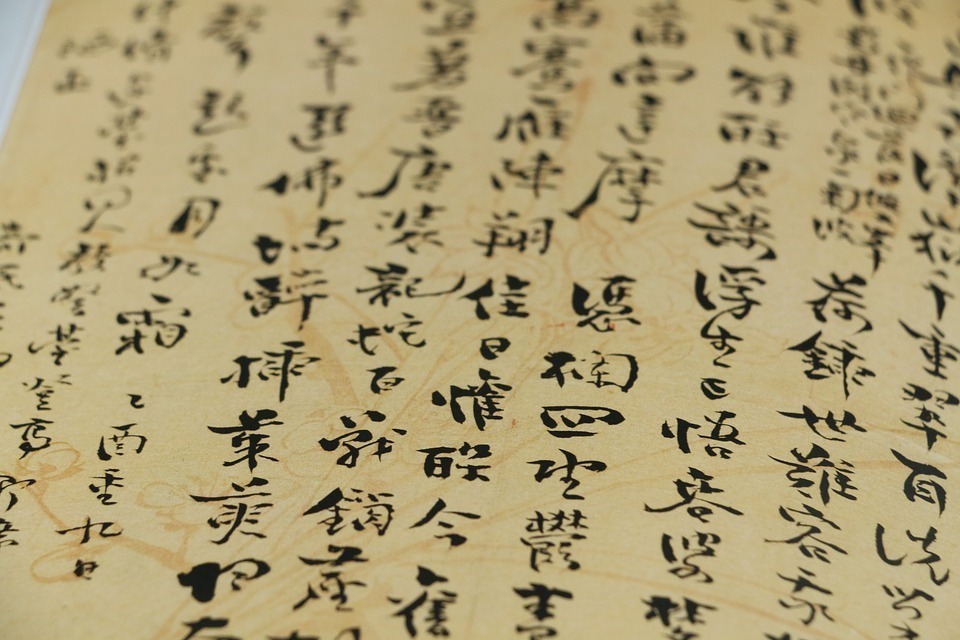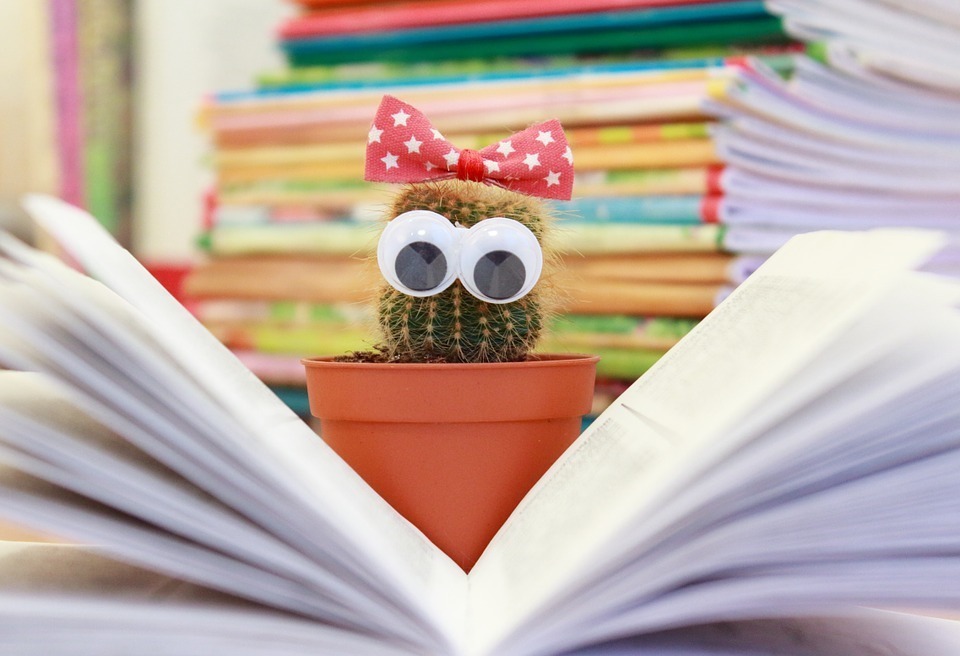赤壁の戦いで徐庶(元直)は全てを見破っていた
■ 赤壁の戦いで徐庶(元直)は全てを見破っていた
赤壁の戦いで徐庶(元直)は全てを見破っていた
赤壁の戦いと言えば劉備軍と孫権軍が手を結んだため、諸葛亮(孔明)と周瑜(公瑾)という夢の軍師タッグが結成されました。数で圧倒する曹操軍に対してありとあらゆる策を施した両軍氏はまさにあっぱれというしかありませんでした。特に諸葛亮(孔明)に至っては敵を出し抜いただけでなく周瑜(公瑾)の考えをことごとく先回りしてまるで未来を知っているかのようなふるまいをしていたのです。
そんな中孫権軍に加わった軍師が龐統(士元)です。諸葛亮(孔明)が「伏龍」と呼ばれていたのに対し、龐統(士元)は「鳳雛」と呼ばれていて二人のうちどちらか一人を軍師として迎えることができたのであれば天下を取れるといわれるほどの天才軍師でした。
二人はことごとく曹操(孟徳)の上を行き緻密な戦略で戦う前から曹操軍を圧倒していました。
ところがこの二人の魂胆を読み切っていた人物が曹操軍の徐庶(元直)です。しかしこの徐庶(元直)は劉備(玄徳)に恩があるためこの戦にはかかわろうとはせず、龐統(士元)の行動を見逃しました。
もし徐庶(元直)が手柄を立てようと龐統(士元)を捕らえ曹操(孟徳)に突き出していたら赤壁の戦いの結果は変わっていたことでしょう。
何がしたかったのか全く読めない焦触、張南コンビ
■ 何がしたかったのか全く読めない焦触、張南コンビ
何がしたかったのか全く読めない焦触、張南コンビ
赤壁の戦いの幕が上がろうかというまさにその時、曹操軍の中に手柄を立てようと先鋒隊を立候補した将軍がいます。それが焦触、張南です。水軍での戦いに絶対の自信を持っていて、陸と変わらない動きができると豪語していました。
船二十艘を与えてくれたら岸辺に突入し、孫権軍の指揮を下げることができるといったのです。曹操(孟徳)は「こいつら大丈夫か?」と思いつつも小舟でいいということと、やる気があったため船を捨てるような気持ちで二人に二十艘を預けました。結局何の手もなく、さらには精鋭ぞろいという訳でなかったためあっさり孫権軍にやられてしまいました。
血気盛んに突っ込んでいった割に何の策もなく、何一つダメージを与えることができなかった焦触、張南は「何がしたかったの?」と言った感じです。
周瑜(公瑾)、曹操軍に尻込みして寝込む
■ 周瑜(公瑾)、曹操軍に尻込みして寝込む
周瑜(公瑾)、曹操軍に尻込みして寝込む
赤壁の戦いで曹操軍を打ち滅ぼした大都督が周瑜(公瑾)です。諸葛亮(孔明)と共に奇策に奇策を重ね圧倒的不利な状態にも関わらず孫権・劉備連合軍を勝利に導きました。
映画「レッドクリフ」では諸葛亮(孔明)に押しも押されもしない天才軍師として描かれ、常に冷静沈着というのが適した大都督でした。
しかし横山光輝の漫画「三国志」ではいささか彼の評価は低かったので紹介します。まず力量に関しては諸葛亮(孔明)の方が圧倒的に上で、周瑜(公瑾)の魂胆をことごとく分かりきっていました。諸葛亮(孔明)の能力の高さを危険に感じた周瑜(公瑾)は曹操軍との戦いのさなかだというのに「後々危険な存在となる」ということから諸葛亮(孔明)を何度も暗殺しようとたくらみます。しかしそれすらも読まれてしまい結局逃げられてしまうのです。
それだけではありません。曹操(孟徳)自ら大軍を率いて呉に攻め入った際、その数に圧倒されただ見るだけしかできませんでした。しかしその際強風が吹き曹操(孟徳)は撤退した為事なきを得ました。ところが強風が吹いたことで旗が折れ、周瑜(公瑾)の上に落ちてしまいました。
外傷はなかったのですが、曹操軍の大軍に尻込みしてしまい、「立つとめまいがする」と言ってまさかの仮病を使ってしまうのです。諸葛亮(孔明)が策を授けるとたちまち元気になるという軽い感じで描かれというあまり頼りのない大都督ぶりでした
陰の功労者、闞沢(徳潤)の存在
■ 陰の功労者、闞沢(徳潤)の存在
陰の功労者、闞沢(徳潤)の存在
赤壁の戦いは正に知略を重ねに重ねて孫権・劉備連合軍が曹操(孟徳)を出し抜いたといっても過言ではない戦いでした。そしてその勝利の功労者の一人として挙げられるのが黄蓋(公覆)です。彼は老将という身でありながらも、自分が曹操軍に潜入すると志願しました。ただ潜入してはばれてしまうので周瑜(公瑾)に自分に対して杖百打の刑をさせることを提案するのです。「ボロボロにされた自分はさぞ周瑜(公瑾)を恨んでいる」とし、曹操軍に寝返り、後方から火責めを行おうとしたのです。
そんな黄蓋(公覆)を曹操軍に潜伏させるために一役買ったのが闞沢(徳潤)です。闞沢(徳潤)は黄蓋(公覆)の手紙をもって曹操(孟徳)の元へ行きます。
曹操(孟徳)は「黄蓋(公覆)が軍門を下ろうとしているのは罠ではないか」と思うのですが、闞沢(徳潤)が機転を利かし曹操(孟徳)を説得することによって黄蓋(公覆)を迎え入れることに決めたのです。
もしかしたら闞沢(徳潤)がいなかったら黄蓋(公覆)が曹操軍に潜入することはできなかったかもしれません。
赤壁の戦いでは黄蓋(公覆)が最大の功労者と言われることもありますが、それを陰で支えていた闞沢(徳潤)という男がいたということを覚えておいてください。
赤壁の戦いのキーワード
■ 赤壁の戦いのキーワード
赤壁の戦いのキーワード
赤壁の戦いはいくつかの要因によって曹操軍の敗北に終わってしまったのですが、その結果を招いたキーワードを上げるとしたら「裏切り」「船」「風」「火」が上がってきます。
まずは「裏切り」について紹介します。これは曹操軍から孫権軍への裏切り、孫権軍から曹操軍への裏切と双方に裏切りは存在しました。(ともに偽りの裏切り)しかし曹操軍の裏切りは孫権軍にばれていたのに対し、孫権軍の裏切りは見事敵軍大将曹操(孟徳)を出し抜いています。無防備の状態で信じ切っている味方から攻撃を食らうのですから大打撃を受けずにはいられません。
次に「船」「風」「火」ですがこれらはセットです。まず曹操軍は水上戦が苦手だったため船を鎖で一つなぎにさせました。ちなみにこの策は孫権軍の裏切り者、龐統(士元)の授けた策です。そして風が吹いたら火を放ちたちまち敵軍を火の海に沈めたというわけです。
これにより大打撃を受けた曹操軍は圧倒的有利という状況にもかかわらず孫権・劉備連合軍の前に大惨敗を喫してしまったのです。
しかし実はキーワードがもう一つあります。それは「疫病」です。曹操軍が敗北した最大の理由は実はこの疫病にあります。いくらまんまと火の海に沈められたとしても疫病がなかったら勝敗は変わっていたでしょう。そのためこの戦の勝敗を決めたのは周瑜(公瑾)の策、諸葛亮(孔明)の策というのももちろんありますが、最大の要因は疫病だったのです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
赤壁の戦いの裏話について書きましたがいかがだったでしょうか。ド派手な大戦の裏で緻密な策略があったり、曹操軍の使えない将軍たちが敵兵の士気を上げてしまったり、周瑜(公瑾)が尻込みしてしまったりということがあったのです。
もちろん諸説様々ですが、「こういったこともあったのではないか」という目で見てみるのも楽しいと思います。