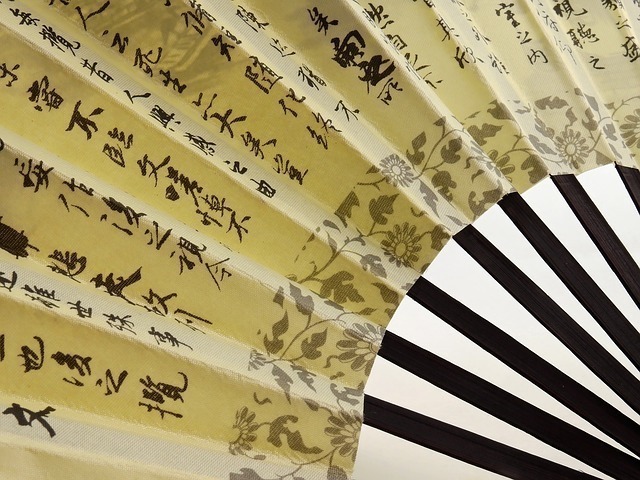劉表(景升)の基本方針
■ 劉表(景升)の基本方針
劉表(景升)の基本方針
劉琮を語る上で忘れてはならない人物が父・劉表(景升)です。劉表(景升)ははっきり言ってそこまで評価は高くありません。それは攻めるべき時に攻めず、優柔不断の君主というイメージが強いからです。
しかし彼は反乱を収めるのが得意で、さらには江東の虎との異名がある孫堅(文台)を打ち取りました。そうなってもガンガン攻めようというのではなく、教育を奨励し学校を建てたり、田畑を耕したりと内政の強化を図ります。
最初は荒れ果ててどうしようもなかった荊州ですが劉表(景升)のおかげで肥沃な土地を作り上げることに成功しました。
袁紹(本初)と曹操(孟徳)の争いの際にはどちらつかずという態度をとってしまったため「優柔不断」というレッテルを張られてしまい、評価は下がる一方でした。
その後も曹操軍に攻め入る隙はあったものの、重い腰は上がらず、最終的に「曹操(孟徳)を攻めればよかった」と後悔するのです。
武人としてはぱっとしませんが、国を肥やすという意味ではいい働きをしたと言えるでしょう。
こういった君主は今の日本では受けがいいことでしょう。しかし、戦国時代においては評価が高くないというのも頷けます。
劉琮、荊州を治めることになる
■ 劉琮、荊州を治めることになる
劉琮、荊州を治めることになる
治政に力を注いだ劉表(景升)ですが、曹操(孟徳)に攻め入られる直前にぽっくり逝ってしまいます。あわただしい中跡目を継ぐのは息子の劉琮か劉琦かという状況でした。
劉琮は劉表(景升)の長男ではなかったため、本来家督を継ぐ立場ではありませんでした。劉琮の母である蔡夫人(蔡瑁(徳珪)の姉)は宮廷内に権力を持っていて、劉琮を擁立しようと奔走しました。蔡夫人の影響力がものを言い、宮廷内では劉琮を推すものが多くなり、長男の劉琦を差し置いて君主になってしまうのです。
ちなみにこの時長男の劉琦には劉備(玄徳)達がついていましたが、劉備(玄徳)はいわばよそ者であるため影響力はあまり強いものではありませんでした。劉琦の後ろ盾が劉備(玄徳)しかいなかった理由の一つとして「母親不明」というのが挙げられるでしょう。
結局、この跡目争いは劉琮がものにし、荊州を統治するようになりました。
劉表(景升)の後を受けた劉琮
■ 劉表(景升)の後を受けた劉琮
劉表(景升)の後を受けた劉琮
さて、そんな劉琮ですが、すぐに曹操(孟徳)に降伏してしまうのです。父である劉表(景升)は優柔不断といわれたものの中立の立場をとり、さらには土地を豊かにしたと言う功績がありますが、劉琮に至っては何もせず国を終わらせたといっても過言ではありません。曹操(孟徳)に対し戦っていたら勝てなかったかもしれませんが、せっかく君主になったので何の爪痕も残さなかったのは「もったいない」の一言に尽きますね。
この時曹操(孟徳)の勢いは計り知れないものでした。しかしその一方で「このあたりで曹操(孟徳)を止めておかないとやばいことになる」と思っていた武将は少なくないはず。そのため「反董卓連合」ならぬ「反曹操連合」たるものを作ればなんとかなったことでしょう。
しかし劉琮は周りと連携をとるという選択肢は取らず曹操(孟徳)の下につくことを選んでしまったのです。
なぜ劉琮は簡単に降伏したのか
■ なぜ劉琮は簡単に降伏したのか
なぜ劉琮は簡単に降伏したのか
劉琮は当初、曹操(孟徳)と戦う予定でした。しかし劉琮を支える将軍達(主に上記で挙げた跡目争いの際、劉琮を推した将軍達)が降伏することを勧めたので戦うことはしませんでした。
さらにこれは推測ですが、劉琮が曹操(孟徳)に降伏した理由として挙げられるのが劉備(玄徳)達とは連携が取れなかったということが挙げられます。のちに赤壁の戦いで孫権軍と劉備軍が手を結んだということは「ここで曹操(孟徳)を抑えなければいけない」という想いがあったからにほかなりません。
しかし劉琮は劉琦との跡目争いの際に劉備(玄徳)を敵に回しています。いまさら「手を結ぼう」などとは言えなかったのでしょう。
さらに劉備(玄徳)達と手を結んだところで、「曹操(孟徳)には勝てない」という頭があったのかもしれません。
いずれにせよ全力を出し切って分が悪い戦いをするよりも無難に降伏し、後々差しさわりのない生活をする方がいいという選択肢を選びました。
父同様、戦うことに関してはこだわりやセンスというものがなかったように思えます。遺伝というのも作用したかもしれませんね。
劉琮への評価
■ 劉琮への評価
劉琮への評価
せっかく父が肥やした土地をいきなり曹操(孟徳)に明け渡してしまうという劉琮に対して、高評価を与えている三国志ファンは少ないことでしょう。しかし何も戦うことだけが正解というわけではありません。劉琮が曹操(孟徳)に降伏した後に孫権軍と劉備軍が手を結び、赤壁の戦いで曹操軍に大勝利を収めました。
その結果だけを見ればそこに劉琮も加われば自分の土地を手放すことなく曹操(孟徳)を撃退できたのにと思わずにはいられません。しかし赤壁の戦いで曹操軍が敗北したのは必然ではないと私は思っています。
つまり、劉琮が孫権軍、劉備軍に混ざって曹操軍と戦っても勝てるという保証はなかったのです。勝てる可能性にすがる君主の方がまぶしく見えますが、こういった「危険な橋は渡らない」という君主がいるからこそ三国志が楽しいと感じられるのではないでしょうか。
そういった意味で私の劉琮に対する評価はあまり低くはありません(高くもありませんが……)
劉琮のその後
■ 劉琮のその後
劉琮のその後
実は劉琮の最後は記述がありません。曹操(孟徳)に降伏した為、厚遇され、青州刺史に就任しましたが、実は亡くなった年は不明とされています。もしかしたら劉琮に降伏を勧めた家臣・蔡瑁同様にミスをしてどこかで曹操(孟徳)に斬られているかもしれません。
あるいはうまく取り入ってその後もいい暮らしができたのかもしれません。
どうなったか分かりませんが、少なくとも「戦って負ける」という最悪な人生を歩むということだけは避けました。
言ってみれば「ギャンブルをしなかった」というあまり面白くはないエピソードになってしまうかもしれませんが、この時代において「無難な選択肢を選ぶ力を備えていた」と捉えてもいいかもしれません。
劉琦が劉表(景升)の後を継げばよかったと言う人は少なくありません。しかし、赤壁の戦いで曹操軍が勝っていたらそういう声は少なかったでしょう。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志においてあまりぱっとしなかった君主・劉琮について紹介しましたがいかがでしたか。「勝てなくても戦って散る」という武将は人気も高く、後世において評価されることが多々あります。しかし、その時を生きている君主であればまず「自分や家族、自国の民が生き残るにはどうしたらいいか」という選択肢を選ぶ必要があります。
そういった意味で、「劉琮は悪い君主ではなかったのではないか」という考え方をしてもらえれば幸いです。