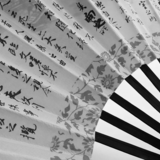劉備(玄徳)を信頼し、お家の悩みまで相談し始める劉表(景升)
■ 劉備(玄徳)を信頼し、お家の悩みまで相談し始める劉表(景升)
劉備(玄徳)を信頼し、お家の悩みまで相談し始める劉表(景升)
同族のよしみもあったのでしょうが、それだけではなく、人間性、カリスマ性、学識、礼節等々を踏まえて、劉表(景升)は劉備(玄徳)に絶大な信頼を寄せて行きます。度々宴席に招いては、天下の話に耽る…。所有している領土はなくとも、接しているうちに劉表(景升)は劉備(玄徳)を格上の存在と認識するようになったのでしょう。そんな人物と話をしていると目から鱗となる話ばかりで楽しい…。これは、曹操(孟徳)に対する劉備(玄徳)や龐統(士元)、劉備(玄徳)に対する諸葛亮(孔明)の関係がこれに相当します。
ちなみに、劉備(玄徳)は、呂布(奉先)との攻防に敗れ、一時、曹操(孟徳)のもとに身を寄せていた時期がありました。この時、曹操(孟徳)は劉備(玄徳)と酒を酌み交わし天下の話をすることを楽しんでいました。
江夏の乱をあっという間に鎮圧 ますます深まる劉表(景升)の信頼
■ 江夏の乱をあっという間に鎮圧 ますます深まる劉表(景升)の信頼
江夏の乱をあっという間に鎮圧 ますます深まる劉表(景升)の信頼
ある時、荊州で反乱が起こります。首謀者は張虎、陳生と名乗る賊でした。慌てる劉表(景升)に食客としてお世話になりっぱなしであるという理由で、劉備(玄徳)が反乱鎮圧を申し出ます。派手に暴れまわっていた張虎、陳生でしたが、張虎は趙雲(子龍)に、陳生は張飛(翼徳)にいずれも一太刀で敗れます。首謀者を失った反乱軍ですが、元々賊の寄せ集め兵…。劉備(玄徳)軍に散々な目にあわされて四散。あっという間に鎮圧。劉表(景升)の劉備(玄徳)への信頼はますます深まります。
しかし、これをよかれと思わない人物がいました。当時、劉表(景升)の側近だった蔡瑁(徳珪)です。
蔡瑁(徳珪)が劉備(玄徳)の命を狙う理由は何だったのか
■ 蔡瑁(徳珪)が劉備(玄徳)の命を狙う理由は何だったのか
蔡瑁(徳珪)が劉備(玄徳)の命を狙う理由は何だったのか
一言で言えば「跡継ぎ争い」です。劉表(景升)には劉琦、劉琮というふたりの子供がいました。長男劉琦は前妻の子、次男劉琮は後妻の子、蔡瑁(徳珪)はその後妻の弟にあたります。劉表(景升)はかねてから「跡継ぎ」に関して悩んでいました。長男劉琦は温和な性格で聡明であり、側近に恵まれれば、問題なく国を治めて行ける人物でしたが、病弱で政務に耐えうる身体ではありませんでした。なので、「跡継ぎは次男劉琮で…」という迷いを抱いていたのです。
そんな劉表(景升)の迷いを察してのことか…単なる野心からなのか…蔡瑁(徳珪)は姉の子である劉琮を跡継ぎにしようとします。事あるごとに劉表(景升)に劉琦の失態を報告したり、劉琦の能力は低く、太守として跡継ぎにはふさわしくないと周囲に吹聴したり…様々な工作を行いました。そんな工作に乗せられたせいか、劉表(景升)自身も徐々に「跡継ぎ劉琮」に心を傾けて行きます。
しかし、そこに待ったを掛けたのが劉備(玄徳)でした。
「お家は長男が受け継ぐもの、何かの事情で悩むようなことがあれば、お家騒動の元となります」とキッパリ言い切ってしまいます。
これを聞いた蔡瑁(徳珪)、今までの努力が水の泡になりかねないと…劉備(玄徳)の暗殺を計画します。
玄徳、的廬踊らせて檀渓を跳ぶ
■ 玄徳、的廬踊らせて檀渓を跳ぶ
玄徳、的廬踊らせて檀渓を跳ぶ
ある時、蔡瑁(徳珪)が近年は豊作が続いているので、各地の官吏を襄陽に集めて慰労の大宴を張ってはどうかと進言します。劉表(景升)は快諾しますが、体調が思わしくないため、劉備(玄徳)に自身の代理を委ねます。これは劉備(玄徳)暗殺を目論む蔡瑁(徳珪)の思惑通りでした。
この時、既に蔡瑁(徳珪)の目論みを察していた劉備(玄徳)でしたが、蔡瑁(徳珪)の吹聴工作(劉備が荊州を乗っ取ろうとしている…など噂を流す)がある中、大役を断れば劉表(景升)に疑いを掛けられる可能性もある…仕方なく劉備(玄徳)は国主代理として「襄陽の会」に出席します。
案の定、宴会場のいたるところに劉備(玄徳)暗殺のための兵が伏せられていました。劉備(玄徳)暗殺実行目前を察した伊籍(機伯)は、宴会中の隙を伺い「あなたの命、風前の灯火」と劉備(玄徳)にそっと伝えます。これを聞いた劉備(玄徳)は厳重な警戒(表向きは警備だが、真の目的は劉備暗殺)が張られる中、「ちょっと厠へ…」と言って会場を抜け出し、そのまま襄陽脱出を図ります。
劉備(玄徳)の逃亡に気付いた蔡瑁(徳珪)は追っ手を差し向けます。そして、追い込まれた劉備(玄徳)に決定的な不運が立ち塞がります。
目の前に見えるのは「檀渓」と呼ばれる深い谷間の急流…。さらに劉備(玄徳)が乗っている馬は兼ねてから乗るのを止めるように指摘されていた凶馬「的盧」です。もはや万事休すの様相。劉備(玄徳)は凶馬に身を委ね、檀渓を飛び越えます。そして、奇跡的に檀渓を渡り追っ手から逃れることに成功します。
この出来事は三国志の中でも有名なシーンで「玄徳、的廬踊らせて檀渓を跳ぶ」と謳われ、「絶体絶命のピンチに一か八かの勝負に出る」という意で語り継がれています。
劉琦、難を逃れて江夏城へ赴任
■ 劉琦、難を逃れて江夏城へ赴任
劉琦、難を逃れて江夏城へ赴任
後日、この事実を知った劉表(景升)は激怒します。蔡瑁(徳珪)は謹慎処分(打ち首でもよさそうですが…)、体調不良の自身に代わって長男劉琦を謝罪のため劉備(玄徳)の滞在している新野城へ向かわせます。これを受けた劉備(玄徳)は劉表(景升)の謝罪の意を快諾します。しかし、その直後、今度は劉琦から「別の問題」を持ち掛けられます。
劉琦も食べ物に毒を盛られるなど、命を狙われていると言うのです。
「身内から命を狙われるとは…」と劉備(玄徳)はひどく心配し、自身も加わりつつ、諸葛亮(孔明)にも劉琦の相談に乗るよう指示します。しかし、諸葛亮(孔明)は受入れるものの、あまり前向きではありません。「他人の私事に口を挟むことを好まない」という諸葛亮(孔明)自身の志向もありましたが、劉備(玄徳)に荊州太守への就任(病気がちな劉表から同族の劉備が国を譲り受けることは人道に反しないと主張)を勧めている手前、お家騒動へ下手な介入をして荊州の官吏とトラブルを起こしたくない…という考えもありました。
しかし、劉琦も必死です。必要に諸葛亮(孔明)にアドバイスを求めます。ある日、求めを拒む諸葛亮(孔明)の目前で「もはやこれまで」と自害しようとします。これを見た諸葛亮(孔明)は慌てて自害を止め、「そこまでのお覚悟ならば…」と一策を劉琦に授けます。
諸葛亮(孔明)は、かつて中国で起きたお家騒動の難を逃れた王家の次男(晋王朝の太子申生の弟、重耳)の話を例に出し、夏江・夏口一帯の守備に就くと称して、一旦、襄陽城から離れるように進言します。
これに劉備(玄徳)も助け船を出します。劉琦が早速、劉表(景升)に相談すると、劉表(景升)は劉備(玄徳)に相談を持ち掛けます…ややこしいですね(笑)。
劉備(玄徳)は「夏江・夏口は呉にも近い重要地、御息子が赴任されるのであれば、荊州全体の士気高揚にもつながるでしょう」と伝えます。
こうして、劉琦は夏江太守として赴任し、命を狙われる難を逃れるのです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
このお家騒動は劉備(玄徳)にとっては「巻き込まれた」感があります。しかし「檀渓を跳ぶ」の直後に水鏡先生に出会い、これが「三顧の礼のきっかけ」になりますし、劉琦が江夏城にいたことで、後年、曹操(孟徳)の荊州攻略の難から助けられたりします。戦国の世、何が幸いするかわからないモノです。