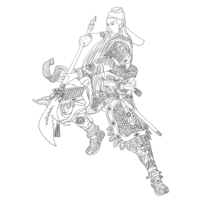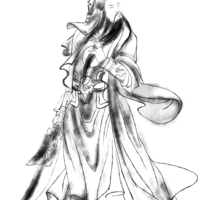第12代皇帝・霊帝
■ 第12代皇帝・霊帝
第12代皇帝・霊帝
後漢第11代皇帝である桓帝に子がいなかったために擁立されたのが、劉宏です。霊帝と呼ばれています。在位は167年から189年までです。ちょうどこの頃に日本では邪馬台国の卑弥呼が女王に即位したと考えられています。
167年には霊帝を擁立した太傅の陳藩と外戚の竇武が、宦官を一掃しようとして失敗し、逆に殺されてしまいます。これにより宦官がさらに力を持つようになっていきました。
173年には霊帝と何氏との間に劉弁が生まれました。何氏は180年には皇后となり、その兄である何進は侍中となります。そして外戚として何進が力を持つようになるのです。
184年には、黄巾の乱が起こります。それに呼応するかのように各地で反乱が相次ぎました。その中には河北の張挙のように天子を自称する者も現れます。後漢王朝の権威はどんどんと失墜していくことになるのです。
第13代皇帝・少帝
■ 第13代皇帝・少帝
第13代皇帝・少帝
霊帝は181年に王美人との間に子を得ています。後に献帝となる劉協です。霊帝はこの劉協を後継者にしようと考え、宦官と謀って外戚の何進殺害を企てますが、実行に移す前に崩御してしまいます。後継者は何皇后の子である劉弁のままです。
189年、劉弁が大将軍・何進に擁立され、17歳という若さで第13代皇帝に即位します。これが4月のことです。8月には宦官らが何進を暗殺、さらにその宦官らが袁紹らに虐殺されることになります。
混乱の中で少帝と劉協を保護した董卓が洛陽に入ったのが9月のことです。そして董卓は朝廷を牛耳り、少帝を廃して劉協を皇帝に即位させました。少帝は弘農王に降格され、その後、李儒によって暗殺されています。
少帝はわずか5ヶ月ほどの在位で、「後漢書」には帝紀がなく皇帝として認めてもらっていません。
第14代皇帝・献帝
■ 第14代皇帝・献帝
第14代皇帝・献帝
189年、廃された少帝の代わりに、陳留王に封じられていた劉協が第14代皇帝に即位します。年齢はわずか9歳でした。後漢最後の皇帝の誕生です。
当然のように董卓の傀儡政権でした。朝廷から外戚と宦官による権力闘争は消え失せましたが、その代わりに暴虐の限りを尽くす董卓が台頭したのです。問題はまったく解決されていません。それどころか皇帝は完全に力を失ってしまいます。
相国となった董卓は完全に政治を独占することになりますが、190年にはこれに対抗する勢力が生まれ、袁紹を盟主として連合を組んで洛陽の都に攻め寄せました。ここで董卓は洛陽を焼き払い、西の長安へ強制遷都することになります。
無力な献帝でしたが、司徒の王允が呂布を抱き込み董卓を殺害、クーデターに成功します。ようやく献帝が政治を舵取りする時代が到来したのです。
しかし董卓の残党が長安を襲撃し、呂布は逃亡、王允は処刑されてしまいます。董卓に代わり朝廷を支配したのは李傕でした。献帝はまたも傀儡と化すのです。
長安からの脱出と遷都
■ 長安からの脱出と遷都
長安からの脱出と遷都
195年、献帝は隙を見て長安の都から脱出します。東へ向かう献帝を保護したのは兗州や豫州を支配する曹操でした。そして都は長安から許に遷されることになります。
しかし、献帝の苦悩の日々は続くことになります。許都に入っても献帝の権威が増すことはなかったからです。董卓・李傕による専横が、曹操に代わっただけだったのです。
200年、20歳となった献帝は、車騎将軍である董承に密勅を与えて曹操暗殺を企てました。しかし計画は事前に露見して失敗。呼応して徐州の小沛で反乱を起こした劉備(玄徳)もあっさりと曹操に敗れて袁紹のもとに逃げてしまいます。
董承は処刑され、娘で献帝の側室であった董貴妃も引き出されて処刑されてしまいました。献帝まで害が及ぶことはありませんでしたが、これにより献帝は完全に孤立してしまうことになります。
曹操が魏王となる
■ 曹操が魏王となる
曹操が魏王となる
曹操は四方を敵に囲まれながらも戦い抜き、袁術や呂布、袁紹と強敵を次々と倒していきます。そして曹操は208年に丞相となりました。董卓が相国となったのと同様です。
曹操の勢いは止まることなく、荊州の劉琮を降してさらに勢力を拡大しています。赤壁の戦いには敗れたものの、その後の韓遂・馬超の反乱を鎮圧、涼州まで支配することになり、213年には曹操は魏公となりました。(荀彧は曹操が魏公となることに反対し、自害しています)
215年に合肥で孫権を破り、漢中の張魯を降した後、216年に曹操は魏王となりました。もはや後漢王朝の滅亡は目前に迫っています。
それ以前に献帝は、暗殺を謀ったという罪で伏皇后を処刑され、二人の皇子も毒殺されていました。そして強制的に曹操の娘である曹節が皇后に立てられており、曹操は外戚としての地位も確立していたのです。もはや誰も曹操が魏王になることに反対などできませんでした。
曹丕への禅譲
■ 曹丕への禅譲
曹丕への禅譲
220年に曹操が病没し、後継たる曹丕が魏王となります。曹操は最期まで皇帝に即位することはなかったのです。しかし曹丕は別でした。魏王となったその年の末には検定に禅譲を迫り、ここで後漢王朝は滅びることになるのです。
献帝は山陽公に封じられました。益州の劉備(玄徳)は献帝が弑されたと聞き、皇帝に即位します。蜀漢の誕生です。しかしその矛先は帝位を簒奪した曹丕にではなく、関羽を処刑した孫権に向けられていました。
221年には文帝(曹丕)に孫権が臣従し、呉王に封じられています。劉備(玄徳)は呉王の領土を攻めますが、夷陵の戦いで敗北。223年には劉備(玄徳)も病没しています。文帝は226年に病没。魏王朝の第2代皇帝には曹叡が即位しました。
まとめ・山陽公は何年まで生きていたのか
■ まとめ・山陽公は何年まで生きていたのか
まとめ・山陽公は何年まで生きていたのか
220年に山陽公に封じられた献帝は、暗殺されるようなこともなく、蜀漢の地へ逃れるようなこともなく、そのまま余生をまっとうしています。亡くなったのは234年と記されています。これは、蜀漢の大黒柱として何度も魏への北伐を試みた諸葛亮が陣中で没したのと同じ年になります。
幼少期から董卓や李傕に操られ、その後は曹操の陰に怯える日々を過ごしてきた献帝。後漢王朝が滅亡し、皇帝という立場から解放されてからの15年余りは、重圧のない自由な生活が送れたのではないでしょうか。そして、曹操よりも劉備(玄徳)よりも、そして曹丕よりも長く生きることができたのです。