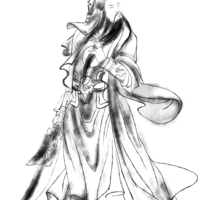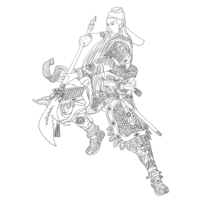若き日の董卓 豪快な生きざまがスゴイ!
■ 若き日の董卓 豪快な生きざまがスゴイ!
若き日の董卓 豪快な生きざまがスゴイ!
董卓と聞くと、なにやらとんでもない野蛮人(やばんじん)を想像するかもしれません。
まあ、三国志に描かれる彼の行いを見れば、無理もないところですが……
そこは(一時期とはいえ)後漢王朝の実権をにぎり、天下を取った男です。記録から見ると、ただ野蛮なだけの男ではなかったようなのですね。
董卓は、涼州(りょうしゅう/注1)に生まれた男で、父は現地の役人をしていました(いまの日本でたとえれば、県庁か市役所につとめてそこそこエラくなったレベルです)。つまり董卓は、地方役人の家のおぼっちゃんとして生まれたわけです。
(注1)涼州(りょうしゅう)……現在の甘粛省(かんしゅくしょう)一帯を中心とする州。三国志の時代は中国の西北部に位置し、異民族との境界線でもあった。
しかし董卓は、決しておぼっちゃんのワクに収まる人間ではありませんでした。若き日の彼は、よりワイルドで、男らしい生き方を目指すようになるのです。それには、涼州出身ということも、大きく関係していました。
三国志の時代、涼州は中国西北のすみっこにあり、漢民族と異民族の境界線になっている場所でした。こうした環境で育った董卓は、若いころから羌族(きょうぞく/注2)という異民族と親しくつきあい、彼らの住んでいる地方に旅をし、放浪生活を送っています。さらには羌族の顔役たち(現地の有力者)たちすべてと親密になったといいますから、なんともスケールが大きい!
さすがは後に天下を取るだけあって、この男、器が違う……と感じさせられますね。
(注2)羌族(きょうぞく)……中国の西方に住む異民族のひとつ。
羌族との交わりからは、董卓という男の人間的魅力が浮かび上がってきます。
放浪生活の後、郷里にもどっていた董卓のもとを、かつて親しくなった羌族の顔役がおとずれたことがありました。すると董卓は顔役をあたたかく歓迎し、農業で大切な耕牛(こうぎゅう)を殺して、ご馳走してあげたというのです。
羌の顔役たちは、董卓の心意気に感激して、お礼に1000頭もの家畜をプレゼントしてくれたといいます。
なんだかすごいエピソードですよね。そう。董卓はとっても豪快な男だったのです。
武術も一級品 そこにシビれるあこがれるっ!
■ 武術も一級品 そこにシビれるあこがれるっ!
武術も一級品 そこにシビれるあこがれるっ!
また董卓には、武力で乱世をのし上がってきたイメージがあると思いますが、彼の「強さ」の背景にも、羌族との交友関係があったと考えられます。
羌族は漢民族以上に馬に親しんでいる人々で、戦いでは騎馬戦術を得意としていました。よって馬を使った戦いでは、漢民族相手に優位に立てる面があります。若いときから羌族と積極的に交流してきた経験は、後に「武将・董卓」の台頭に大いに役立ったのでしょう。
董卓は腕力にすぐれていたのはもちろん、「騎射」(きしゃ)という武術をとても得意にしていました。
これは馬に乗りながら弓矢を射る技術です。騎射で強い矢を、正確に放てることは、一流の武人の証明でもありました。しかも董卓は、その騎上からの射撃を、左右どちらの腕からも放つことができたのです。
もしあなたの周りに、弓道や馬術をやっている人がいれば、この技術のスゴさを分かってくれると思います。弓矢というのは、基本的には自分の利き腕で放つものであり、左右どちらからも放てるというのは、ハッキリいってスゴイ腕です。
ましてやそれを、馬に乗って駆けながらこなすのですから、董卓のウデのスゴさが想像できます(走る馬の上から正確に弓を放つのも、大変な技術ですからね)。
この例からも分かるように、董卓の武人としての戦闘力は、なみ外れたものがあったのです。
彼をそこまで強い男に育てたのは、騎馬をたくみに操る羌族との交友だったのでしょう。
気前のよさも天下一! 大将アンタについてくぜ
■ 気前のよさも天下一! 大将アンタについてくぜ
気前のよさも天下一! 大将アンタについてくぜ
さて、そんな董卓もあるていど大人になると、父親と同じく役人への道を進みます。
役人といっても、徐々に世の中が乱れはじめた時期ですので、盗賊や反乱の取締りが大きな仕事になります。そう。武術に優れた董卓には、もってこいの仕事だったのです。
あるとき、胡(えびす/北方の異民族)が涼州に侵入してきて、略奪をはたらき、住民をたちを連れ去る事件がありました。涼州の長官は董卓に騎兵隊をあずけ、胡を討伐するよう命じました。董卓はみごと抜擢(ばってき)にこたえ、1000人以上もの異民族を、討ち取ったり捕らえたりしたのです。
時は後漢末期。政治の乱れは中国全土の乱れとなり、各地の治安も悪化していきました。
こうした乱世のなかで、董卓はその武勇でもって、出世への道を開いていくことになります。
また、董卓の部下に対する接し方を示す、こんなエピソードがあります。
あるとき并州(へいしゅう)で異民族が反乱を起こしたため、後漢王朝は討伐軍を組織することとなり、董卓も従軍しました。朝廷の軍は大勝を収め、多くの異民族を討ち取る戦果をあげました。
(注3)并州(へいしゅう)……山西省を中心とする一帯に存在した州。中国と、北方異民族の領域との境界線であり、しばしば衝突が起きた。
董卓も活躍が認められ、朝廷から褒美として大量の絹(きぬ)をもらいました(昔は絹がとても高価なものでした)。
この貴重なご褒美を、董卓はどうしたかというと……
なんと、すべてを部下に分け与えた上で、こう言ったというのです。
「功績を成したのは私だが、諸君こそが功績とともにあったのだ」
なんともシビれるセリフですね。
そもそも絹は当時、とても高価なものだったので、売れば相当な軍資金(お金)になったはずです。にもかかわらず、それらをすべて部下に与えてしまうのですから、董卓はとても気前のいい将軍だったといえます。
(後に董卓は、富豪を殺して財産を奪ったり、皇帝の墓をあばいて財宝をぬすんだりしたらしいので、ちょっと意外なエピソードではあるのですが)
ともあれ、こうやって部下の心をつかむ術を心得ていたからこそ、董卓は一軍の将としてのし上がっていけたのでしょう。
歴史に大悪人として名を残した董卓ですが、若き日の羌族との交友や、優れた武勇、豪快なエピソードをひも解いていくと……また違った実像が見えてくるのです。
目指したのは「カッコイイ男の生きざま」
■ 目指したのは「カッコイイ男の生きざま」
目指したのは「カッコイイ男の生きざま」
結局、董卓とはどういう人物だったのでしょうか?
史書には、若き日の董卓が「男伊達(おとこだて)を気取っていた」という風に記されています。
男伊達とは、「男の面目(めんぼく)を立てる」という意味です。
つまり董卓は、「不良でありながらも、強きをくじき弱きを助け、義理人情を重んじる」
……そんな、男らしい男であろうとしていたようです。
たとえるなら、昔のヤクザ映画の主人公と、目指す生き方が近いといえます。
こう考えると、董卓の人物像の知られざる面が浮かんできます。
「すぐれた武勇」「豪快な性格」「部下へのやさしさ」「気前のよさ」
これらはみな、董卓の目指していた「カッコイイ男の生き様」と、ぴったり符合する要素なのです。
そして記録からも、若き日の董卓は、自分が目指す「男の生き様」を、あるていど実現していたことも読み取れるのです。
そんな「男の中の男」を目指していたはずの董卓が……
どうして中国史上に残る「大魔王」になってしまったのか?
彼はどこで間違えちゃったのか?
次回以降、その歩みをじっくり見ていきましょう。