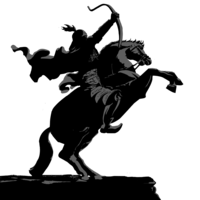楽進の生い立ち
■ 楽進の生い立ち
楽進の生い立ち
楽進、字は文謙。兗州陽平郡の生まれです。父親の名前は不明、どのような境遇に生まれたのかも不明です。恐らくは人の才能を引き出すことに長けた曹操に目をつけられたのでしょう。曹操も小柄だと伝わっていますが、この楽進も小柄だったようです。はたしてどちらの方が小柄だったのか、興味がありますね。曹操も最初はその容姿を見て軍人として起用するのは難しいと感じたのでしょう。しかし実直さに光るものを感じ、文官として採用しています。主君の命令には生涯忠実だった楽進は断ることもなく、その任を受けています。このときの楽進は傍若無人な董卓の専横ぶりに憤りを感じての参加でしたから、それを討ち倒す協力ができるのならば、武官・文官どちらでも良かったのかもしれません。魏の武将の筆頭にまで登りつめる楽進は、何と最初は曹操に雇われた記録係だったのです。
楽進の最初の活躍
■ 楽進の最初の活躍
楽進の最初の活躍
楽進といえば戦場にあっても動じず、がむしゃらに先陣を進むイメージですが、最初の活躍はまったく違いました。なんと募兵活動です。このとき曹操は旗上げしたもののどこの太守でも刺史でもなく、私財を投じて集めた兵だけの小勢力です。あまりの兵の少なさに見かねた張邈、張超の兄弟が兵を貸し与えたと伝わっているぐらいでした。このときの曹操にとって最も必要なのは兵力、軍事力でした。それが反董卓連合内での発言権に繋がっていきます。楽進はそんな事情の中、故郷で募兵を行い、なんと千人を超える兵を連れて戻ってきました。曹操の喜びはかなりのものだったでしょう。楽進の統率力、感化力を認めた曹操は、文官ではなく武官として起用することを決めました。
楽進の武勇
■ 楽進の武勇
楽進の武勇
楽進は小柄ながら気性が激しく、闘争心の塊のような漢です。おそらく曹操のもとに馳せ参じる前にはある程度の武芸を積んでいたと思われます。もしかするとその武勇に惹かれて兵は集まったのかもしれません。楽進は武将として扱われるようになった後、反董卓連合のメンバーとして董卓軍と戦います。そして曹操が兗州の牧となってからは青州から押し寄せてくる黄巾の残党百万と戦いました。ここでどれほどの武功をあげたかはわかりませんが、楽進のことですから傷だらけになっても退かずに戦い続けたのだと思われます。実際に楽進の武勇が知れ渡ることになるのは呂布との戦い以降です。
一番槍の大手柄
■ 一番槍の大手柄
一番槍の大手柄
日本でも古来より武士は一番槍を誇りとしてきました。率先して敵陣に突っ込むのには勇気と覚悟がいります。楽進はそのどちらも持ち合わせていました。楽進は常に一番槍を争って活躍していくのです。最強の武将として紹介される呂布との濮陽の戦い、曹操を裏切って呂布と反乱を起こした張超との雍丘の戦い、そして寿春に本拠を置く袁術軍の橋蕤との戦い、いずれの戦いでも楽進は一番槍の武功をあげました。
将に武勇があり、率先して統率すると兵もまた勇猛果敢になります。小覇王とよばれた孫策がそのいい例でしょう。楽進の部隊は無類の強さを誇り、敵陣を撃破していきます。徐州に拠点を置いた呂布軍との戦い、荊州に拠点を置いた張繍との戦いでは敵将を破りました。張楊の後継者である眭固、徐州で反旗を翻した劉備(玄徳)の撃退でも活躍しています。そしてこれまでの実績から楽進は討寇校尉に昇格しました。
名士・淳于瓊を斬る
■ 名士・淳于瓊を斬る
名士・淳于瓊を斬る
さらに楽進の名を高めたのが河北の雄・袁紹との戦いです。果敢に先陣を率いて敵を攻撃、さらに烏巣の兵糧庫襲撃の際には敵の大将である淳于瓊を討ちました。淳于瓊といえば袁紹や曹操と並び霊帝から「西園八校尉」に選ばれたほどの実力者です。おそらくはかなりの家柄の出身でしょう。淳于瓊は袁紹に仕える重臣であり、名士だったのです。しかし同じく重臣の許攸が袁紹を裏切り、曹操に秘密情報を提供したことから兵糧庫を襲われることになり戦死します。敵の兵糧を焼くことに成功するだけでなく、楽進は敵将も討ったのですから大手柄です。
その後は袁紹の息子たちである袁譚や袁尚を攻めて成果をあげ、河北の平定に貢献しています。こうして楽進は折衝将軍となり、于禁、張遼、徐晃、張郃らと並ぶ魏の驍将のひとりに数えられるようになります。曹操はこの五人をかなり信頼しており、先陣や殿はこの五人が代わる代わる担当していたと伝わっています。蜀の五虎大将軍に匹敵する魏の五虎大将軍というわけです。
相性の悪さ
■ 相性の悪さ
相性の悪さ
そんな名将のひとりとなった楽進ですが、好き嫌いははっきりとしていたようで、他の名将とはなかなか上手くいっていません。楽進との相性が悪かった武将で有名なところでは張遼があげられます。張遼はもともと呂布の配下でしたから死力を尽くして戦った相手ということです。張遼と楽進の仲が悪かったことは三国志正史にも記されているほどですから間違いないでしょう。
しかし曹操はそんな二人を組ませて戦わせています。河北平定の際にも二人は組んでいますし、孫権と戦った合肥の戦線では、これに李典を含んだ三人が組んでいます。実は李典も張遼とは不仲でした。李典は呂布軍によって叔父を殺されています。張遼は仇のひとりというわけです。武将と武将が仲たがいから争うケースも珍しくないのですが、合肥が孫権軍に囲まれた際には李典は私情を捨て協力し合うことを提案し、この三人の結束によって孫権軍を打ち破ることになります。はたして曹操はどこまで計算してこの三人を組ませたのでしょうか。意図が気になりますね。
まとめ・楽進のプライド
■ まとめ・楽進のプライド
まとめ・楽進のプライド
戦場でほとんど負け知らずの楽進は、やがて右将軍にまで登りつめます。古参の武将として曹操軍のほとんどの戦いに参加していますが、最初は記録係です。そこから魏の筆頭武将となったわけですから、積み上げてきた武功は他を圧倒するものだったのでしょう。そのプライドもあり、他勢力から降ってきた将と衝突することが多かったのかもしれませんね。
三国志演義ではあまりスポットライトが当たらない楽進ですが、その武勇と武功は関羽や張飛に匹敵するものです。いえ、その二人を凌ぐのではないでしょうか。渋い活躍が多いとはいえ、楽進ファンが少ないのは残念ですね。もっともっと評価されてもいい名将ではないでしょうか。