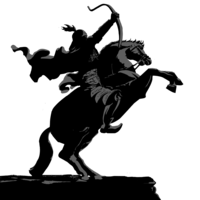曹操にとってなくてはならない特攻隊長 楽進
■ 曹操にとってなくてはならない特攻隊長 楽進
曹操にとってなくてはならない特攻隊長 楽進
曹操(孟徳)の周りには許褚(仲康)や李典と言った優れたボディーガードがいました。そのため、楽進(文謙)そこまで目立つ存在というわけでは無かったと言えます。
しかし楽進は常に相手に突っ込んでいく精神を持っていたので曹操軍団の切り込み隊長として全軍の士気を上げる事が出来たというのは間違いないでしょう。矢が飛び交う中迷わず飛び込む武将がいてくれたら「俺も、俺も!」と続くので、楽進の存在は曹操(孟徳)にとって貴重な存在と言えました。
楽進はそれだけの忠誠心があった上、戦闘力、知力、統率力はかなり高かったので野球で言うと走攻守揃った一番バッターと言えたでしょう。そして周りとの連携もよく取れていて人望もあったので最終的に右将軍にまで昇進したのです。
家柄もよくなく小柄でしたが楽進には根性があったのだと思います。
曹操の従兄弟の中で最もバランスのとれた 曹仁
■ 曹操の従兄弟の中で最もバランスのとれた 曹仁
曹操の従兄弟の中で最もバランスのとれた 曹仁
曹操の従兄弟と言ったら夏侯惇(元譲)や夏侯淵(妙才)と言った武力に優れた派手な人物らが真っ先に名を上げられることでしょう。そして曹仁(子考)は曹家であるため曹操(孟徳)の兄弟や子供と勘違いされることもありますが、実は夏侯惇(元譲)達同様曹操(孟徳)の従弟(いとこ)です。
曹仁は気性は荒く大人達からは嫌われていました。そのため家督は曹仁ではなく弟の曹純が継いだ訳ですが、その反面曹操(孟徳)とはウマが合いました。腕っ節も強く弓術、馬術に優れていたため狩猟の腕前はプロ級と言われていたほどです。
上のものからはあまり理解されなかった曹仁(子考)ですが、忠誠心はもちろんのこと下からの人望もありました。さらに知力も夏侯惇(元譲)らよりあったとされているためバランスのとれた武将と言えるでしょう。
派手な従兄弟に囲まれた曹操(孟徳)ですが、その中でも曹仁(子考)は唯一無二の存在といっても過言ではありません。なぜなら、息子の曹丕や曹植に対して「お前達も曹仁(子考)のようになれ」と言わしめたくらいで、そこからも曹仁の総合力の高さが伺えるのではないでしょうか。
魏国最大のピンチを救った男張遼(文遠)
■ 魏国最大のピンチを救った男張遼(文遠)
魏国最大のピンチを救った男張遼(文遠)
三国志で最強な武将は?という問いに、真っ先に挙げられるのは呂布ではないでしょうか。そして10番以内に声があげられそうなのが張遼(文遠)(もしかしたら5番以内に彼の名前を挙げる人もいるかもしれません)です。しかしこの張遼(文遠)は戦闘力が高いだけではなく、統率力、忠誠心も相当なものでした。
合肥の戦いで孫権軍に攻め込まれた曹操軍は敗色濃厚でした。しかし張遼(文遠)が先頭になり魏を守りきりました。難攻不落の張遼(文遠)に対して攻めていた孫権軍が恐れ慄いたくらいです。その後、呉の民にとって張遼(文遠)に恐怖を感じたため悪さをする子供に対して「遼来遼来」(日本でいうなまはげが来たぞと言う感じでしょう)と言われるほどでした。
そんな張遼(文遠)ですが何も戦闘力が高かっただけという訳ではありません。君主が何度か変わったにも関わらず曹操(孟徳)への忠誠心は高く、さらにそれ以上に人望があったので彼の軍は他の軍以上に連携が高く一枚岩となっていました。
小覇王の異名は伊達ではない。孫策(伯符)の存在感は別格
■ 小覇王の異名は伊達ではない。孫策(伯符)の存在感は別格
小覇王の異名は伊達ではない。孫策(伯符)の存在感は別格
親譲りの戦闘能力に加えそれ以上の人望を兼ねそろえた孫策(伯符)は小覇王という異名が付けられたほどの逸材でした。さらに知力、統率力に優れ孫堅(文台)が「コイツがいれば俺がいつ死んでも孫家は安泰だ」と言わせるほどでした。(そんなことを口にしてしまうから孫堅(文台)がすぐに亡くなってしまったというのは笑えない冗談になってしまいましたが)
驚きは総大将という立場にもかかわらず、「三国志で最強の一人」と謳われる武将、太史慈(子義)と一騎打ちしてしまうのです。勝った時のメリットは確かにありますが、それ以上に負けた時のデメリットが多いこの戦いをしてしまう度胸も見事です。戦闘力の自信の表れとも取れますが、それ以上に彼の場合「財力の乏しい自分が力を誇示すれば周りがついてくる」という頭もあったに違いありません。
結局その戦いでは決着がつきませんでしたが、その後太史慈(子義)は彼の男気に惚れ配下となり、呉になくてはならない武将となりました。まさに圧巻としか言いようのない孫策(伯符)はオールマイティーな将軍と言えたでしょう。
周瑜の才能は諸葛亮孔明をも凌駕する?
■ 周瑜の才能は諸葛亮孔明をも凌駕する?
周瑜の才能は諸葛亮孔明をも凌駕する?
諸葛(孔明)の最大のライバルとして多々挙げられる周瑜(公瑾)ですが、諸葛(孔明)と違い戦闘力の高さにも定評がありました。そういった意味では総合力では諸葛(孔明)をはるかに上回っていたと言えるでしょう。
さらに酒を飲んでいても演奏の間違いに気づくほど音楽の才能にもあふれていました。容姿端麗で家柄もよく、幼馴染の孫策(伯符)その弟である孫権(仲謀)にとってなくてはならない存在だったのは言うまでもありません。
もしかしたら周瑜(公瑾)は自分のライバルを周瑜(公瑾)ではなく孫策(伯符)という天才と見ていたかもしれません。そうして二人が切磋琢磨し合い、お互いがお互いを高めていったのかもしれません。
蜀の武将としては異質な総合力の持ち主趙雲(子龍)
■ 蜀の武将としては異質な総合力の持ち主趙雲(子龍)
蜀の武将としては異質な総合力の持ち主趙雲(子龍)
劉備(玄徳)、関羽(雲長)、張飛(翼徳)、諸葛(孔明)と言ったまさに一点突破的な能力の持ち主が多い蜀にして唯一高い総合力を兼ねそろえていたのが趙雲(子龍)と言えるでしょう。
戦闘力の高さはもちろんのこと、忠誠心が高く、統率力、人望、知力にも富んでいました。
軍の司令官である諸葛(孔明)にとっては古参の関羽(雲長)、張飛(翼徳)に対してより趙雲(子龍)に対して指示を出しやすかったのでさらにありがたい存在だったことでしょう。
『三国志』の「趙雲伝」では簡潔にしか書かれていませんが他の正史には彼の記述は多く、そこからも彼の活躍は後世に残したい!という意志が伝わってきます。
趙雲(子龍)が一番好きという三国志ファンは少なくなく、彼の功績は多大な物だったと言えるでしょう。
まとめ
■ まとめ
まとめ
総合力の高い武将を挙げましたがいかがでしたか?趙雲(子龍)は知力も優れていたのか?とか、周瑜(公瑾)の戦闘力は実は高かったのかということが分かってもらえれば幸いです。
現代でも同じように文武両道の人より文が飛び切り優れている、逆に武において一番である、という人の方がインパクトは強いです。しかし、秀才の人が「実はあの人はスポーツもできるんだよ」とか、トップアスリートが「あの人は博士号も持っている」となったらやはり見方は変わりますよね。
三国時代でもすべてを兼ねそろえていた武将に対し意を払いたいと思い特に総合力の高いと思った武将を挙げさせてもらいました。