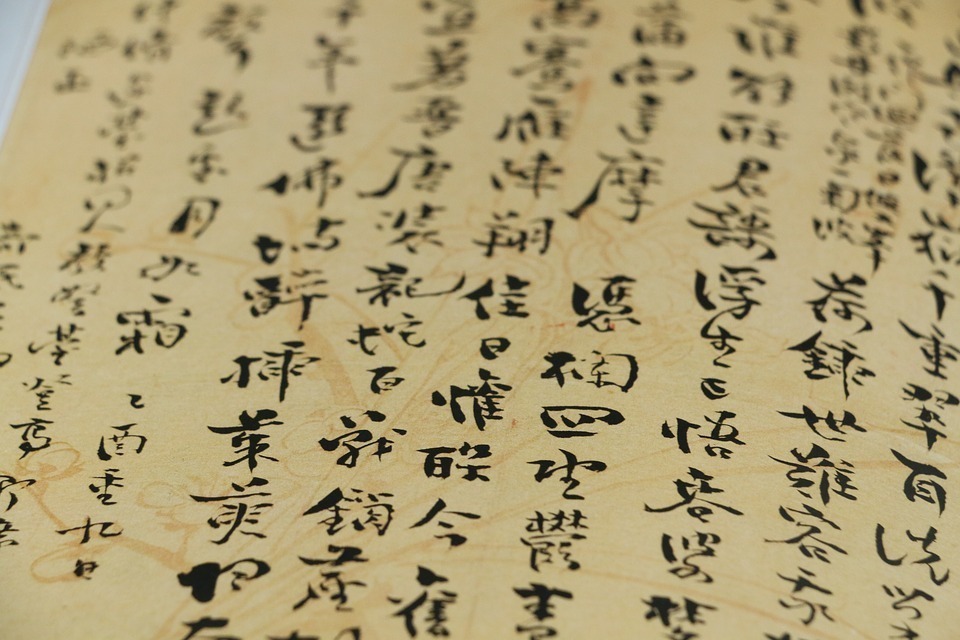曹操軍の古参の将
■ 曹操軍の古参の将
曹操軍の古参の将
曹操と同族にあたる曹洪(字は子廉)は、曹操が反董卓連合に参加するために旗上げしたときから従う古参の将になります。他に曹仁、夏候惇、夏侯淵などの武勇に優れる名将がこのときに揃っています。曹操の四天王などと呼ばれることもありますね。三国志ファンであれば曹洪の名はご存知だと思いますが、どのような活躍をしたのかと問われたらいかがでしょうか。意外に曹洪の活躍の場面は知られていないかもしれません。曹操配下の四天王の中で、戦場で討ち死にしたのは夏侯淵だけですから、曹洪は曹操同様に数多の過酷な戦場を駆け抜けながら寿命をまっとうしたことになります。はたしてどのような生涯だったのでしょうか。
早々と戦場で散る危機
■ 早々と戦場で散る危機
早々と戦場で散る危機
曹洪といえば、董卓との戦いにおいて命がけで主君である曹操を守ったシーンが有名です。袁紹を盟主とした反董卓連合は待機したままで、なかなか本格的な進撃を行いません。連日宴会ばかりを開いて董卓が降参するのを待っていただけでした。そこで曹操がしびれを切らして出撃します。そして洛陽までの中間地点の滎陽で董卓軍の徐栄に迎撃されるのです。兵の数が足りない曹操軍は大敗します。曹操も戦場で乗っている馬を失うほどでした。ここで曹操に馬を譲り、退却を助けたのが曹洪なのです。徐栄は深追いせずに撤退していますが、追撃が厳しければ、もしかすると曹洪は早々とこの190年に討ち死にしていたかもしれません。これは曹操にも当てはまります。曹洪がいなければ曹操の生涯はここで幕を下ろしていたかもしれないのです。曹洪の最大の見せ場は、その重要性を鑑みてもこの戦いになるでしょう。
吝嗇家としての一面
■ 吝嗇家としての一面
吝嗇家としての一面
曹洪は吝嗇家としても有名です。簡単にいうと「ケチ」なわけです。貧乏とは違います。収入がなかったわけではありません。曹操が許都に献帝を迎え司空に就任した際に自分の資産を調べさせたところ、なんと配下の曹洪と同じだったと記されています。曹洪は曹操配下の中でも指折りの大金持ちだったわけです。吝嗇家だからこそ資産を残せたのかもしれませんが、曹洪のケチぶりはかなりのものでした。それを物語っているのが曹丕とのやり取りです。曹丕といえば曹操の後継者で、後に魏の初代皇帝に即位します。曹丕が太子だった頃に曹洪に百匹の絹を借りようとしたところ、曹洪はこれを断ったというのです。シルクロードを「絹の道」と呼ぶほどですから、当時でも絹はとても貴重なものであったことは間違いありません。古代ローマでは同量の金と同じ価値とされています。しかしやがて自分の主君になるだろう相手の頼みを断るというのはなかなかできることではありませんね。ちなみに曹操は曹洪の「財に対する執着」、「女性に対する欲深さ」はよく熟知していたようで、曹洪の側近である辛毗や曹休に警告しています。本人を諫めたこともあるのでしょうが、命を救われた過去がある曹操は少し遠慮していたのかもしれません。
文帝との対立
■ 文帝との対立
文帝との対立
しかし曹丕もなかなかしつこい性分です。魏の初代皇帝(文帝)になってから曹丕は曹洪に仕返しをしようと考えます。呉の孫権あたりもよく配下にちょっかいをかけていますが、彼にはユーモアがあり、曹丕にはユーモアではなく憎しみがあります。対照的な主君像です。もともと曹洪の食客は横柄な態度をとることが多かったようですが、曹丕はそこに目をつけて、食客が罪を負った際に曹洪にも責任をとらせようとしました。吝嗇家ではあるものの、長く戦場で活躍したこれだけの功臣を連座で処刑しようとしたのです。多くの家臣が曹丕を諫めましたが曹丕の決意は変わりませんでした。ここで最後に登場するのが曹丕の実の母親である卞太合です。曹丕と後継者争いをした曹植も卞太合の助命によって命を救われています。曹丕も母親の頼みだけは断り切れず、曹洪の命を助け、その代わりに爵位と所領を削りました。とりあえず命拾いした曹洪は喜んだと記されています。
漢中攻防戦
■ 漢中攻防戦
漢中攻防戦
お話がやや前後しますが、曹洪の見せ場のひとつといえば漢中を巡る劉備(玄徳)との戦いでしょう。まだ曹操も健在だった頃です。益州を征服した劉備(玄徳)は漢中を目指して進軍してきます。その先鋒は猛将で知られる張飛、そして馬超です。さらに呉蘭、雷銅らを率いて下弁に攻め込んできます。曹操は曹洪を総大将に命じ、曹休、辛毗、曹真、張既、楊阜を率いさせて迎撃しています。劉備(玄徳)軍は二手に分かれます。ここで張飛は曹洪の兵站を断つ動きを見せるのです。参軍の曹休は冷静にこの動きを分析し、張飛の陽動を見抜いて曹洪に呉蘭らを先に討つべきだと進言しました。曹洪はその意見を取り入れて呉蘭、雷銅を撃破。これにより張飛と馬超も退却しています。あまり注目されていませんが、曹洪は総大将として張飛、馬超を撃退しているのです。三国志ではトップクラスの武勇を誇る二人を相手にしてのこの活躍は見事ですね。夏侯淵が定軍山で討たれるのは、この後の話になります。
まとめ・明帝の時代に復帰
■ まとめ・明帝の時代に復帰
まとめ・明帝の時代に復帰
曹丕が皇帝だった頃は不遇の時代を送っていた曹洪ですが、二代目皇帝(明帝)に曹叡が即位してからは後将軍に復帰、さらに驃騎将軍となります。改めて楽城侯に封じられました。そして232年に死去しています。曹操が亡くなったのが220年ですから、曹洪はかなり長命だったのではないでしょうか。
曹洪は、三国志演義では張飛や馬超を撃退した英雄の姿ではなく、潼関の戦いにおいて馬超との戦いで、血気に逸り出撃して潼関を奪われるという失態を犯した姿が描かれています。三国志演義は蜀びいきなので曹洪の活躍ぶりは消されている感じでしょうか。そのために曹洪の武将としての評価はあまり高くありません。
ということで今回は魏の名将・曹洪をご紹介しました。ちなみに曹操が徐州に侵攻し、その隙に兗州の大半を張邈と呂布に奪われた際には、本陣に先行して兗州に舞い戻り東平や范を占拠しています。官渡の戦いでも敵の兵糧庫である烏巣を曹操が襲撃する際に留守を守り抜いています。呂布や袁紹を相手にしても成果を出しているのです。やはり曹洪は名将と呼ぶにふさわしい活躍をしているといえるでしょう。