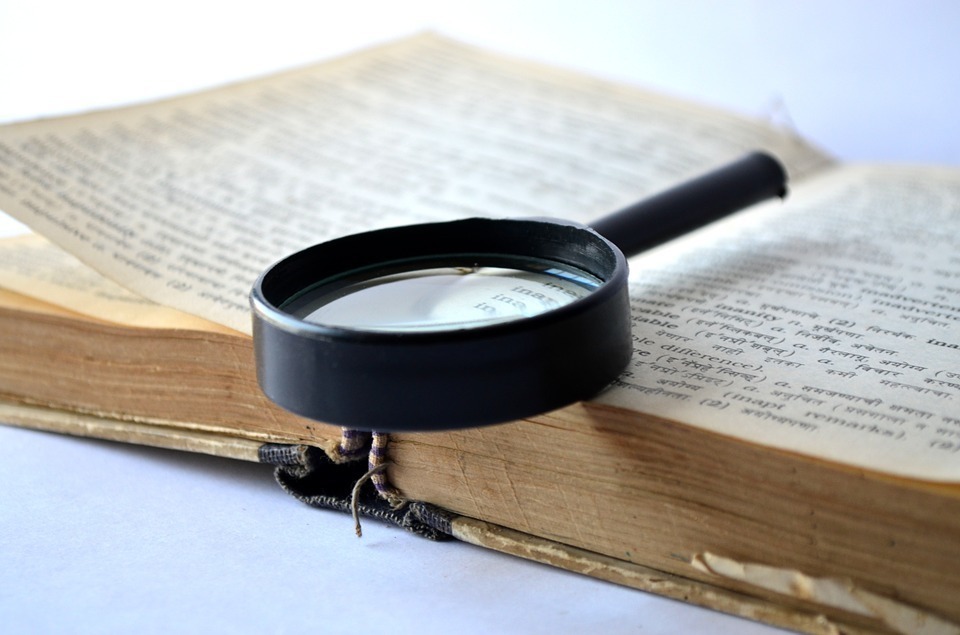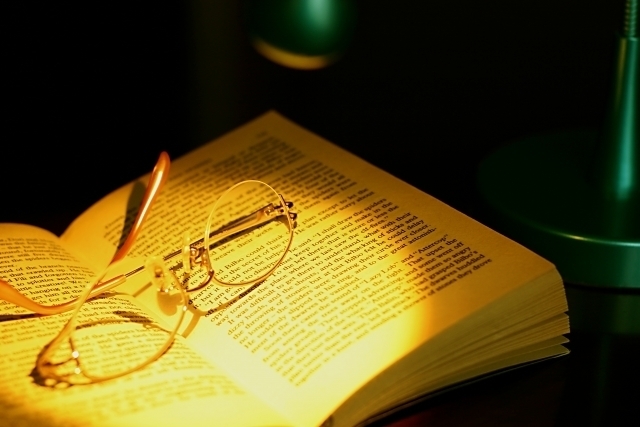魏の君主 曹操
■ 魏の君主 曹操
魏の君主 曹操
曹操が「曹」という姓である理由は、祖父の曹騰にあります。宦官だった曹騰は子を産めなかったため、養子が後継ぎすることを許されました。その養子は、曹操の父である曹嵩(そうすう)です。曹嵩は夏侯氏の元で育てられ、やがて曹操が誕生したのです。曹操が夏侯惇らと関係がある理由は、ここから来ています。
かつて少年だった曹操はやんちゃで世間から疎まれていましたが、橋玄が「君は英雄になれる」と言ったことで人生は変わります。
三国志初期の頃から逆賊の討伐に貢献していた曹操。力を確実に蓄えることで橋玄の予言通りの存在となりました。
蜀や呉は共闘が多かったのに対し、魏は単体でもあっさりと勝ち抜くほどの兵力を有しています。
従兄弟の曹仁と曹洪
■ 従兄弟の曹仁と曹洪
従兄弟の曹仁と曹洪
魏には、曹操の従兄弟である曹仁と曹洪がいました。彼らはどんな活躍をしたのでしょうか?
曹仁
幼い頃から武勇に優れていた彼は、騎兵として敵軍を追い込みました。敵軍の配下を捕えたほか、仲間と協力して猛将の関羽を攻撃したこともあります。冷静な騎兵隊長だった彼は、死後に曹操と並ぶ豪華な墓が建てられました。
曹洪(そうこう)
曹操が馬を失くしたとき、馬を譲って徒歩で付き添ったそうです。曹操が窮地に陥った際は、一番に駆け付けました。極度の女たらしであることは玉にキズでしたが、蜀の張飛(関羽と並ぶ名将)らを破った戦歴も残しています。
夜襲に巻き込まれた長男 曹昂
■ 夜襲に巻き込まれた長男 曹昂
夜襲に巻き込まれた長男 曹昂
曹操の息子は多くいますが、ここでは印象的な5人についてご紹介します。
曹昂(そうこう)は読みこそ曹洪と一緒ですが、字は「子脩」です。曹操の正妻(母)からは大事にされましたが、ある事件で自らを盾にしたためこの世を去りました。この流れは、張繍という人物が関係しています。
曹操は張繍の降伏を受け入れたのち、(張繍の)叔父の未亡人と関係を結びます。曹操は激怒した張繍の暗殺を企てますが、張繍が先回りして夜襲をかけたのです。
そこで曹昂は自分の馬を父に差し出し、大量の矢を浴びて死亡しました。
また、正妻はこれを機に曹操と離縁します。深々と謝罪する曹操に対し、「よく平気な顔をしていられるわね」と言葉を残したそうです。
魏の初代皇帝になった次男 曹丕
■ 魏の初代皇帝になった次男 曹丕
魏の初代皇帝になった次男 曹丕
曹操は曹昂の件を機に、正妻だった丁夫人と離縁します。卞夫人を正室として迎え入れたのち、曹丕が誕生しました。やがて曹丕は、魏の初代皇帝となります。
弟の曹植とは後継者争いになったものの、曹操が不在中も魏を守り抜いたことで地位を獲得します。父が考案した制度を受け継いだことで、魏はより安定感のある国となりました。また、曹丕は「九品官人法」という制度を生み出しました。これは1人の官僚を9段階で評価する制度で、300年以上続いたといいます。
しかし、彼は関係者の心に深い傷を残したことで有名です。次は、彼の不評が後世に受け継がれる3つのエピソードをご紹介します。
曹丕の評価が低いエピソード3つ
■ 曹丕の評価が低いエピソード3つ
曹丕の評価が低いエピソード3つ
1.曹洪への恨み
かつて曹丕は曹洪からお金を借りようとしましたが、曹洪がこれを拒否。曹丕はこのことで曹洪の地位を落とすよう仕向け、死刑に追い込んだそうです。しかし、これら全ては卞夫人が回避してくれました。
2.甄皇后に自殺を命ずる
甄皇后は、第2代皇帝・曹叡の生母です。元々曹丕のメイドだった郭は、主人に気に入られて妾となります。愚痴をこぼした甄皇后は、事実上曹丕に殺害されました。
3.于禁を憤死させる
于禁は長く活躍した武将ですが、関羽との戦いで降伏します。曹丕はこの出来事を曹操の墓に描き込んだことで、魏に戻った于禁を怒らせました。于禁はこのことがきっかけで病気となり、世を去ってしまいます。
詩人として生きた三男 曹植
■ 詩人として生きた三男 曹植
詩人として生きた三男 曹植
曹植は、現在も中国で有名な文学者として知られています。作詩を好んでいた彼は、同じ趣味を持つ父の曹操から可愛がられました。
やがて曹植は、後継者争いで曹丕と激しい衝突を起こします。曹丕が初代皇帝に決まった際、曹植の側近は次々と殺されました。ある日、曹丕は曹植に対し「7歩歩く間に作詩しろ」と難癖をつけます。
こうしてできた「七歩の詩」は、「同じ兄弟なのに何故いがみ合う」という意味が込められました。
母の卞夫人によって迫害が落ち着いたこともあります。しかし、彼女の死後も領地を次々と移されるという不遇な人生を歩みました。
詩人として評価される曹植ですが、本人は「男らしくない」と卑下していました。
武勇に長けた四男 曹彰
■ 武勇に長けた四男 曹彰
武勇に長けた四男 曹彰
曹家の中でも武勇に大変優れていた人物です。黄色いヒゲを生やしていたことから、「黄鬚児(こうしゅじ)」と称賛されていました。反乱を起こした異民族を追い払ったこともあります。
また、遊牧民族・鮮卑のカ比能(かびのう)が襲撃した際は、見事追い返したことでカ比能が魏に降伏します。
曹操が魏の王となった際は、現在の許昌市エン陵県に配置されます。曹丕が在位すると曹彰も冷遇されたのち、任城郡に移されました。
曹丕は、武勇で功績を挙げる曹彰のことも良く思っていなかったそうです。
13年間生きた曹沖
■ 13年間生きた曹沖
13年間生きた曹沖
曹家には、わずか13歳で早世した曹沖という人物がいます。優しい心の持ち主で、学問が好きだった彼は曹操から愛されていました。
身内に冷酷な曹丕も、「曹昂より曹沖の方が後継者として優れていただろう」と認めたほどです。
魏は呉の君主・孫権から象を受け取ったことがありましたが、その重さを知る者は誰一人いません。しかし、曹沖が「船に乗せてみればいいんじゃない?」と提案したことで、曹操は彼を大いに褒めました。
名医の華佗が些細な事で曹操に殺されたため、病気で倒れた曹沖はなす術もなく夭折。
曹操は自分の過ちによって息子を救えなかったことをずっと後悔しました。
まとめ 安定した治世の裏側
■ まとめ 安定した治世の裏側
まとめ 安定した治世の裏側
三国志では、今回紹介した人物がちょくちょく登場します。息子なら特に曹丕や曹植が有名です。
曹操は文武に優れていたため、その後も父と同じくらい有能な息子が多く誕生しました。
しかし、曹丕が初代皇帝となったことで、皇族と配下が迫害を少なからず受けています。そのたびに卞夫人が取り成してくれましたが、根本的な解決には至っていません。
曹操が生み出した制度は曹丕へと引き継がれたことで、魏に安定をもたらします。しかし、曹家を知ることは「魏の裏側を知ること」と同じ意味なのかもしれません。
曹叡死後の魏はやがて部下の司馬懿に滅ぼされますが、すでに力を奪われてしまったらどうしようもないはずです。