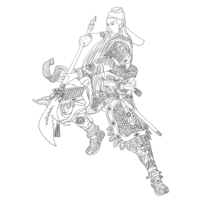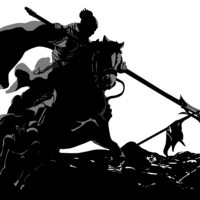少年の霊帝が即位し宦官が実権を握る腐敗した政治情勢
■ 少年の霊帝が即位し宦官が実権を握る腐敗した政治情勢
少年の霊帝が即位し宦官が実権を握る腐敗した政治情勢
後漢の第12代皇帝となった霊帝は若干12歳という若さで、政治の実権は側近の宦官が行い、強い権力を奮っていました。霊帝は若い頃から宦官たちに女性や酒を勧められ、政治に興味を示さず、毎夜宴会を行っていました。このような背景から実権を掌握していた宦官たちは賄賂を持って人事を施し、不平不満をこぼすものを断罪していきます。
時を同じくして中国大陸に周辺の異民族が侵攻し、各地では反乱が勃発することとなり、都の将軍たちはその対応に追われていきます。とても宦官たちに対応する余裕もありませんでした。天候も不順が続き、農作物にも被害が多大となって、社会情勢は混乱を極めていきます。
黄巾の乱の首謀者【張角】の登場
■ 黄巾の乱の首謀者【張角】の登場
黄巾の乱の首謀者【張角】の登場
太平道という宗教組織を用いて張角(チョウカク 生年不明―184年)が多くの信奉者を集めていました。張角はものの10年余りで数十万人ともいわれる信者を集めており、一大組織の頂点に君臨していました。奇しくも社会情勢が不安定なのを受けて、各地の民の要望も聞き入れられず、張角のような民衆出で、カリスマ性のある人物は多くの民にとって英雄視されていました。
張角は表向きは善道を以て天下の人々のために立ち上がるように見せていましたが、実際には信者を使って大規模な反乱を起し、政権を奪取しようと企んでいました。張角は自らを天公将軍と称し、弟の張宝(チョウホウ)、張梁(チョウリョウ)らとともに各地で反乱を起します(184年)。太平道の信者たちは黄色の頭巾を巻いており、黄巾の乱と後に呼ばれるようになりました。
大規模な反乱も1年持たずに終息となる
■ 大規模な反乱も1年持たずに終息となる
大規模な反乱も1年持たずに終息となる
広大な中国大陸で大軍で反乱を起しても鎮圧される可能性は高く、張角も計算無しに立ち上がったわけではありませんでした。部下の馬元義(バゲンギ)を首都の洛陽に送り込み、一部の宦官を買収して首都の内外から一斉蜂起する段取りを進めていました。しかし、腹心の一人が霊帝直属の宦官に密告し、さすがの霊帝も激怒して馬元義を捕えて処刑し、何進(カシン 生年不明―189年)を大将軍に任命して張角の捕縛を命じます。
この裏切りによって張角は一斉に反乱を起すしかなく、10万人ともいえる大規模反乱軍も各地の豪族や中央の将軍たちの的となっては次第に劣勢になっていきました。ほどなくして張角も病に倒れてしまい、指揮官の弟たちも戦死してわずか半年足らずで終息に向かいました。
黄巾の乱によって目の当りになった政治の腐敗ぶり
■ 黄巾の乱によって目の当りになった政治の腐敗ぶり
黄巾の乱によって目の当りになった政治の腐敗ぶり
しかし、指揮官を失っても、政治の腐敗ぶりに各地方では小規模の反乱が起こり、略奪などで治安がままならない情勢にも陥っていました。これを受けて霊帝は皇帝直属の部隊である西園三軍(西園八校尉)を配下のアイデアもあって創設し、霊帝自身や何進を含めた8人の指揮官の元に兵を配置しました。この中には袁紹(エンショウ 154年―202年)や曹操(ソウソウ 155年―220年)といった後に覇権を担う英雄もいました。
この黄巾の乱を受けて中央国家の腐敗ぶりが目の当たりになり、地方の豪族や将軍などの実力者たちの台頭につながっていきます。
悪の象徴【十常侍】の独占政治と大将軍【何進】の対立
■ 悪の象徴【十常侍】の独占政治と大将軍【何進】の対立
悪の象徴【十常侍】の独占政治と大将軍【何進】の対立
霊帝の時代、政治の実権を握っていたのは一部の宦官で十常侍(正史上は12人)といわれていました。十常侍は自身たちに災いが降りかかることを良しとせず、黄巾の乱後も権力を握り続けていました。十常侍たちは大軍を動かせる何進が権力の座を脅かすのではないかとヒヤヒヤしていました。
平民の出でありながら大将軍にまでなった【何進】
■ 平民の出でありながら大将軍にまでなった【何進】
平民の出でありながら大将軍にまでなった【何進】
そもそも何進は名門出身の貴族でもなく、屠殺業を営む平民でした。何進と同郷である十常侍の一人郭勝(カクショウ)は、何進の妹の美貌に目を付け、霊帝の女中となるように仕向けます。妹が宮中入りすると、何進は王宮の役職や地方の太守(郡の長官)に付き、やがて妹が霊帝の寵愛を受けて皇后(何皇后)となると、都に戻ってきて将軍となり出世を果たしていきます。何皇后は男子を生み、劉弁と名付けられ、跡取りを生んだことによって何皇后は宮中の地位を盤石にしていきます。一方で、霊帝の寵愛を他にも受けていた王美人が男子を生むと(劉協)、何皇后は嫉妬から王美人を毒殺してしまいます。
霊帝の死後に権力者争いで何進が一歩リード
■ 霊帝の死後に権力者争いで何進が一歩リード
霊帝の死後に権力者争いで何進が一歩リード
霊帝が189年に34歳の若さで崩御すると、跡取りを決めていなかったことから、劉弁(リュウベン)と劉協(リュウキョウ)の間で後継者争いが繰り広げられます。何進は妹の子供である劉弁を推し、袁紹の協力を受けて反対派を押しのけました。劉弁が第13代皇帝(小帝)に即位すると、十常侍は一旦何進に加担しますが、その権力が強くなるにつれて何進の抹殺を図ります。一方で何進側の袁紹や袁術(エンジュツ 生年不明―199年)ら有力武将は、すべての原因は腐敗政治を行っている十常侍にあると進言し、何進と十常侍の対立が決定的となっていきます。
十常侍によって暗殺される何進
■ 十常侍によって暗殺される何進
十常侍によって暗殺される何進
袁紹は各地の諸将を都に集結させて、十常侍に対する圧力をかけようとします。ただでさえ混乱している社会情勢に加え、兵力を持った各地の実力者たちを都に呼ぶのは危険が生じると曹操らに反対されますが、涼州の董卓(トウタク 生年不明―192年)などが駆付けます。身の危険を感じた十常侍は、一刻を争うために何太后(何皇后)を利用して何進を労うために宴会を施すという嘘とついて呼び寄せさせます。妹の呼びかけに気を良くした何進は、罠と言い張る袁紹らの忠告を無視して無警戒に宮中入りをし、十常侍が配した兵たちによって殺されてしまいました。
何進の死後、宮中は大混乱に陥る
■ 何進の死後、宮中は大混乱に陥る
何進の死後、宮中は大混乱に陥る
十常侍は何進たちの軍を掌握しようと、偽造した小帝の詔を用意しましたが、何進の姿が見えないことに部下たちは不審に思ってしまいます。十常侍は討ち取った何進の首を一緒に掲げると、逆に何進の配下たちの反撃を喰らうことになります。
何進は平民の出ということもあり、大軍を操って先を見通すような武将の能力を擁していませんでした。しかし、部下には厳しさよりも優しさを持って接しており、何進に恩義を感じている部下たちは怒り狂って宮中に侵入していきます。普段から賄賂によって政治をしていた十常侍たちはそのことを見抜けませんでした。
小帝を保護した【董卓】が台頭する
■ 小帝を保護した【董卓】が台頭する
小帝を保護した【董卓】が台頭する
この混乱に袁術や袁紹は宮中入りを果たし、十常侍を次々と打倒して何太后を無事に保護しますが、肝心の小帝や劉協の姿を見失います。小帝と劉協は十常侍の一人である段珪(ダンケイ)によって連れ去られますが、董卓の軍勢によって保護され、無事に都へ帰ることができました。
以後、董卓が皇帝を手中にして、多くの軍勢を引き入れていき、一大勢力を築いていきます。各地の諸侯は董卓の狂暴な性格を知っていましたが、小帝を盾にされている以上、手出しができず、董卓の独占政治が始まっていきます。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志の歴史に必ず登場する黄巾の乱の原因といえるのが、十常侍による腐敗した政治でした。権力争いに敗れた何進ですが、万一にも十常侍を打ち倒していたとしても、野望の大きい董卓によって、都は結局のところ大混乱に陥っていたかもしれません。この混乱があったからこそ、劉備や曹操といった志の高い武将たちが後に支持されていく要因となったといえます。