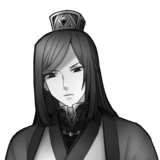街亭の戦
■ 街亭の戦
街亭の戦
227年、諸葛亮孔明は、準備を整え蜀軍の第1次北伐に向かいました。
そして、大変重要な街亭の戦で、馬謖に戦略的要地である街亭を死守するよう命じたのです。
道筋を押さえ魏軍をそこで足止めする作戦でした。
しかし、馬謖は功を焦り、自身の才覚に溺れ、足止めではなく戦を仕掛けようと、その命令に背き山頂に布陣してしまいました。
結果、馬謖率いる蜀軍は水路を断たれて、孤立、惨敗してしまいます。
結果、戦略的要地を失った孔明は、北伐の兵を退くことになりました。
泣いて馬謖を斬る
■ 泣いて馬謖を斬る
泣いて馬謖を斬る
諸葛亮孔明が一目置いていた馬謖という武将が戦いで命令違反を犯し、大敗の原因を作ってしまったことは、指揮に関わるだけでなく、蜀軍の衰退にもつながります。
いかに、その才能に惚れて目をかけてきたとしても国の転覆にもつながりかねない大敗が馬謖の独断専行によるものだということに厳重な処罰が必要でした。
愛弟子の馬謖の処刑に踏み切るにあたり諸葛亮は涙を流しました。
後に蔣琬から「馬謖ほどの有能な将を」と彼を惜しむ意見もありましたが、諸葛亮孔明は「軍律の遵守が最優先」と再び涙を流しながら答えたといいます。
現在は「どんなに優秀な者であっても、法や規律を曲げて責任を不問にすることがあってはいけない」という意味で使用されることが多く「正史(三国志)」の記述に則したものであると言えます。
このことから、違反者は厳しく処分することを【泣いて馬謖を斬る】という故事成語が用いられます。
「泣いて馬謖を斬る」とは「大切な人であっても、決まりを破った者は厳しく処分する」という意味の言葉となります。
「心を鬼にする」「手加減しない」「情けをかけない」など現代の類義後は、いくつかあり、時代背景も違うので「泣いて馬謖を切る」の使われる機会は少なくなっているかもしれません。
補足ですが、「三国志」の蜀書・馬謖伝では「馬謖は牢屋に入れられて亡くなった。諸葛孔明は馬謖のために涙を流した」となっています。
また、諸葛孔明が馬謖を信頼していたこと、参謀に抜擢したこと、馬謖に戦で重要なポジションを任せて失敗したことなどが書かれています。
そして、三国志をもとにしたフィクション「三国志演義」には「孔明涙を揮(ふる)いて馬謖を斬る」と書かれています。
このため「泣いて馬謖を斬る」と言われるようになったと考えられています。
孔明が馬謖に目をかけた出来事
■ 孔明が馬謖に目をかけた出来事
孔明が馬謖に目をかけた出来事
孟獲(もうかく)という武将が蜀の南方を支配していました。
諸葛亮孔明が北伐に向かうためには、南方を平定しておく必要がありました。
そこで、孟獲の度重なる反抗に「捕らえても解放」し、それを7回も続け、とうとう孟獲も降参して軍門に加わりました。
これは「七縦七禽(しちちょうしちきん)」と呼ばれています。
実は、この時に「心を攻めるのが上策です」と馬謖の献言があったということです。
馬謖の才能を諸葛亮が認めた逸話かもしれません。
劉備の不信任
■ 劉備の不信任
劉備の不信任
劉備が臨終の際、劉備は諸葛亮孔明に対して「馬謖は口先だけの男だから信用してはならない」言ったそうです。
この直前、呉との夷陵(いりょう)の戦いで、蜀は手痛い敗戦を喫し、馬謖の兄・馬良も戦死してしまいました。
このことが劉備の心身に大ダメージを与え、死の床につかせてしまったという経緯があります。
どうして劉備に心酔して仕えてきた諸葛亮孔明が「馬謖を信用し過ぎるな」という遺言を守らなかったことは疑問が残るところですが、劉備が亡くなっても、諸葛亮孔明は馬謖を重用し続けてしまったのです。
自分にとって大切な人であれば罰するのは辛いもの。
処罰を軽くしたい行動に出たくもなります。
しかし、そうすることで和(組織・チーム)が乱れるわけで、厳しい決断を下すことも必要でしょう。
このように、個人の感情を持ち込まず、規律を保つことを優先して正当に処分をすることを「泣いて馬謖を斬る」と表現できます。