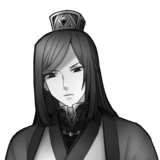エリート馬謖
■ エリート馬謖
エリート馬謖
馬謖、字は幼常。荊州襄陽郡の生まれです。名士として名は知られていましたが、さらに五人の兄弟が皆優れていたことから「馬氏五常」と評判でした。劉備が荊州に拠点をもったころに、劉備(玄徳)は馬謖の兄の馬良を左将軍掾として採用しています。本来ならば五人とも召し抱えたかったのですが、父親がそれを許しませんでした。劉備(玄徳)が滅べば馬氏もまた滅ぶことになるからです。そこで劉備(玄徳)は「白眉」として名高い馬良だけを召したのです。これに納得いかなかったのが末弟の馬謖です。彼もまた「経書」の他に「三史」「孫子」「呉子」「六韜」などの兵法を修めており、自信があったのです。劉備(玄徳)が漢中王を自称するようになった頃に馬謖は父親の許しを得て劉備(玄徳)に仕えるようになりました。馬謖の才能に驚いたのは諸葛亮です。もともと馬良と諸葛亮は親交がありましたが、馬謖の打てば響くような才までは気づいていなかったようです。馬謖は県令として経験を積んだ後は、南方の異民族慰撫のために越嶲郡の太守に任命されています。
叩き上げの王平
■ 叩き上げの王平
叩き上げの王平
王平、字は子均。益州巴西郡の生まれです。異民族の出自ともいわれています。ほとんど字が書けず、自分の名前以外では「仁義礼智信忠孝」の文字しか知らなかったそうです。無学だったために周囲から侮られることが多かったようで、王平の実力をきっちり見極められていたのは曹操と諸葛亮ぐらいのものでした。蜀の将にあって魏から降ってきたものは珍しく、王平はその一人になります。定軍山の戦いの際に蜀に降っていますが、三国志演義では魏の徐晃と仲たがいをして蜀に降ったと記されています。主将の徐晃もまた王平を軽んじていたのです。しかし王平には実戦で磨いてきた戦の感覚があります。兵法は知りませんでしたが、戦場の地形からどこに兵を配置すべきか、どう戦うべきか的確に見抜く目を持っていたのです。
第一次北伐への参加
■ 第一次北伐への参加
第一次北伐への参加
この馬謖と王平が諸葛亮に従って魏の領土を目指したのは、228年のことになります。蜀の建国者である劉備(玄徳)はすでに病没しており、皇帝には劉禅が即位していました。馬謖の兄の馬良も戦死しています。魏では曹操の後を継ぎ、献帝から禅譲を受けて皇帝に即位した曹丕もすでに没しています。曹丕の後を継いだのは曹叡でした。即位してまだ二年しか経過していません。諸葛亮は南征を成功させ魏と戦うだけの準備ができていましたから、これを好機と捉えて出師の表を奉って北伐に出陣しました。しかし蜀は深刻な人材難を迎えており、前線で活躍が期待できる有力な将は老将・趙雲と魏延くらいのものです。五虎大将と呼ばれた関羽・張飛・馬超・黄忠ももはやこの世を去っています。どうしても馬謖や王平などの若手に頼らざるを得ない状況でした。
北伐の戦略
■ 北伐の戦略
北伐の戦略
魏の総大将は曹真でしたが、皇帝である曹叡が長安にまで親征していました。兵力でも軍事物資の量でも蜀は魏に敵いません。勝つためには策が必要でした。それが二方向からの挟撃作戦です。本来は荊州上庸の孟達が寝返り、さらに敵兵力を分散させることができるはずでしたが、敵将の司馬懿に看破されて孟達は討たれていました。そこで諸葛亮は趙雲に褒斜道を進ませ長安西の郿へ進軍させます。こちらが囮で、本陣は漢中よりはるか西の祁山から反時計回りに長安を突くという戦略です。涼州、雍州を占領し、長安を突くことを考えたのです。魏延だけは長安への最短距離にあたる子午道への進軍を進言しましたが、敵の守りが厚いことを考慮し、諸葛亮に却下されています。諸葛亮の作戦は上手く進み、天水・南安・安定の三郡が速やかに蜀に呼応しました。後は大軍を動かしやすい天水から街亭の道筋を抜け、長安へ東進することになります。
街亭の重要性
■ 街亭の重要性
街亭の重要性
諸葛亮はここで魏よりも先に街亭を押さえることを決断します。街亭さえ押さえておけば長安の魏軍は涼州へ進むことができず、さらに武都を突くこともできません。武都を突かれると祁山の本陣は漢中との兵站を断たれることになります。街亭さえ押さえておけば、敵の動きに合わせて祁山の本陣を効果的に進軍させられます。諸葛亮は人手不足の中でこの街亭守備の任に楊儀を当てるつもりでしたが、馬謖が願い出ました。諸葛亮は馬謖の才能を認めてはいたものの、馬謖には魏と真っ向からぶつかり合うような実戦の経験がありません。しかし馬謖は執拗に主張します。諸葛亮は根負けし、副将に王平、後詰に向朗をつけ、三万の兵を率いさせて街亭守備を馬謖に命じました。諸葛亮のこの人事の決断が敗北を招くことになりますが、陣容を見る限り、仕方ない人選だったともいえます。
街亭の戦い
■ 街亭の戦い
街亭の戦い
魏でも街亭に向けて長安から五万の兵が出陣していました。率いるのは名将・張郃です。官渡の戦い以降曹操に帰陣し、幾多の戦場で武功をあげたベテランでした。街亭に蜀軍がすでに布陣しているのを知り、諸葛亮の鬼謀を恐れましたが、敵兵が山上にいることを知り喜びます。あっという間に山麓の水源を押さえてしまいました。山上の馬謖の兵は包囲され、どう動いていいのかまごついている間に水が尽き、士気が下がった状態で下山し壊滅的な損害を受けます。王平は馬謖の指示に反論し、街道に伏兵を配置していたために張郃は追撃できませんでした。馬謖は命からがら後詰の向郎の陣に逃げ込みます。こうして確保した大切な拠点をあっさりと失うことになり、第一次北伐は失敗に終わるのです。
まとめ・王平を侮った馬謖のプライド
■ まとめ・王平を侮った馬謖のプライド
まとめ・王平を侮った馬謖のプライド
もし馬謖が王平の助言を聞いて街道に布陣していれば、そうたやすくは突破されることはなかったはずです。仮に張郃が勝利していたとしても大勢の兵を失い、街亭を確保することはできなかったでしょう。諸葛亮は勝つことを馬謖に求めてはいなかったのです。守ることだけに専念していればそれでいい話でした。五万の兵をここに引きつけておく間に諸葛亮は次の手を打てたからです。しかし無学の王平の助言を馬謖は聞き入れようとはせず、山上に布陣することの有効性を兵法書から引用して、得意げに王平に言い聞かせたのです。馬謖のプライドがなせる業でした。これが馬謖の器だったのです。諸葛亮は成都に撤退し、その後、敗戦の責任をとって丞相から退きました。そして「泣いて馬謖を斬る」ことになるのです。