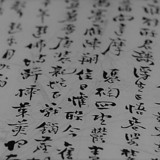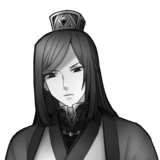白眉
■ 白眉
白眉
白眉とは「同類のものが数あるなかで最も優れている人物やもの」という意味です。
兄弟の中で最も秀でた人、あるいはたくさんの中で最も優れた者のことを「白眉」といいます。
この白眉の語源になった人物が、蜀の劉備玄徳に仕えた馬良なのです。
馬氏の五常
■ 馬氏の五常
馬氏の五常
蜀に馬氏の5人兄弟がいました。
この兄弟全員が、字(あざな)に”常”という字がつくことから「馬氏の五常」と呼ばれていました。
馬良の字は、季常と言い、馬氏の五常の四男とされています。
劉備が荊州を支配下に置くと、弟の馬謖(ばしょく)とともに劉備に取り立てられました。
そして、劉備が益州に移った後も、荊州の留守を預かり務めていました。
諸葛孔明を尊兄と呼び、二人は義兄弟の契りを結んでいたとされています。
馬良
■ 馬良
馬良
222年、夷陵の戦い として知られる蜀と呉の戦いに従軍します。
異民族を呉との戦いに協力させる任務を与えられると、馬良はその任務をこなし、異民族を蜀に帰伏させることに成功させました。
しかし、その後、劉備が率いる蜀軍は陸遜が率いる呉軍に敗北し、馬良も戦死してしまいます。
三国志演義では、呉軍と対峙する劉備の布陣に疑問を抱き、蜀の都、成都に残っていた孔明の元へ意見を求めるために赴きます。
孔明は劉備の布陣の欠陥に気付き、急ぎ馬良を劉備の元に戻らせますが、時、すでに遅く、蜀軍は大敗を喫してしまいます。
史実とは異なり、馬良は、夷陵の戦いでは死なず、後に孔明の南蛮征伐と時期を前後して病死したことになっています。
馬良は、5人兄弟の中でも最も才覚に恵まれた人物であると言われました。
彼の眉には白髪が混ざっていたことから、白眉(はくび)とあだ名され、人々は馬良を称えるのに、「馬氏の五常、白眉、最もよし」と言ったとされています。
これが故事成語「白眉」の語源です。
馬氏の五常のうち、氏名や来歴が明らかになっているのは、4男の馬良と5男の馬謖だけで、残りの3人の兄弟については歴史的資料が残されていません。
弟 馬謖
■ 弟 馬謖
弟 馬謖
馬謖も、また、兄の馬良に劣らぬ才覚の持ち主であったようです。
弁舌に優れ、孔明は彼のことを高く評価しましたが、劉備は馬謖を信頼しませんでした。
劉備はその死にあたり、孔明に馬謖は口先だけの男だから、重要な職につけてはいけないと戒めましたが、彼の死後、孔明は馬謖を自分の幕僚として登用します。
孔明が第1次北伐の兵をあげたとき、彼は馬謖に戦略的要地である街亭の守備を命じます。
孔明は道筋を押さえるよう馬謖に命じていましたが、自身の才覚に溺れる馬謖はその命令に背き、山頂に布陣してしまいます。
結果、馬謖率いる蜀軍は水路を断たれて孤立、惨敗してしまいます。
戦略的要地を失った孔明は、北伐の兵を退かざるをえませんでした。
泣いて馬謖を斬る
につながります。