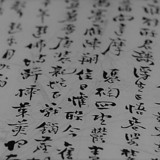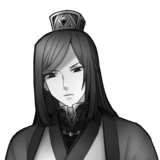荊州では名の通った両家の5兄弟なのだが…
■ 荊州では名の通った両家の5兄弟なのだが…
荊州では名の通った両家の5兄弟なのだが…
馬良(季常)は、荊州襄陽郡宜城県の名家・馬氏の5兄弟の四男として生まれます。不思議なことに、名家であるにも関わらず、上の3人の兄については三国志正史、演義ともにまったく登場せず、名前すら不明ということなのです。ちなみに末弟の五男は、三国志フリークにはおなじみで、何度「泣いて斬られた」かわからないくらい有名な馬謖(幼常)です。
馬良(季常)が、なぜ四男かわかったかというと、それは字の付け方に理由があります。もっともメジャーなのは「伯・仲・叔・季」。子供が生まれたら、長男には「伯」、次男には「仲」というネーミングの法則があるのです。このため、季常という字の馬良は四男だと推測されます。ちなみに、五男には「幼」と付けることが多かったようです。
さて、そんな馬良(季常)は「白眉」と呼ばれていましたが、これは若いときから眉毛に白髪が混じっていたためです。5兄弟の中でも、飛び抜けて俊才だった馬良(季常)を称し、地元の人々は「馬氏の五常、白眉もっとも良し」と賛辞を送ったそうです。でも、こういう逸話って誰が言っていたのでしょうね。他の兄弟がまったくその名を知られていないのに、馬氏の五常って……。
弟の馬謖(幼常)とともに蜀の劉備(玄徳)に仕える
■ 弟の馬謖(幼常)とともに蜀の劉備(玄徳)に仕える
弟の馬謖(幼常)とともに蜀の劉備(玄徳)に仕える
そんな俊才の馬良(季常)は、三国志のシミュレーションゲームでは高い知力を持つ参謀タイプの武将として人気があります。でも、その人物像を明確に説明できる人は少ないかもしれません。筆者も馬良(季常)に関しては、知将ではあるものの、正直あまり印象に残っていないというのが正直なところです。そもそも、いったいいつ劉備(玄徳)傘下に加わったのでしょうか。
記録によると、馬良(季常)は、弟の馬謖(幼常)とともに、赤壁の戦い以降、荊州を支配することになった劉備(玄徳)に請われ、仕えるようになったと言われています。その後、劉備(玄徳)は劉璋(季玉)が刺史を務める益州に向かうわけですが、ここで馬良(季常)が印象が薄くなってしまう分かれ道が待っていたのです。
俊才であったがゆえに大事な拠点を任されてしまうことに…
■ 俊才であったがゆえに大事な拠点を任されてしまうことに…
俊才であったがゆえに大事な拠点を任されてしまうことに…
劉備(玄徳)が益州へ向かったのは、三顧の礼によって配下に加わった軍師・諸葛亮(孔明)の「天下三分の計」によるものです。中国全土を三分割し、北を曹操(孟徳)、南東を孫権(仲謀)、そして南西を劉備(玄徳)が支配することこそ、お互いの均衡が保たれ、富国強兵を可能とするという策略だったのです。そのためには、劉備(玄徳)が荊州だけでなく、益州も支配下に入れる必要があると諸葛亮(孔明)は説いたのです。
そこで劉備(玄徳)は、配下の武将を引き連れて益州を奪いに行くわけですが(厳密には奪う目的ではなかったのですが、その話はまたいずれ)、その際に連れて行く武将として馬良(季常)ではなく、弟の馬謖(幼常)を選んだのです。これが、後に馬良(季常)がまるで歴史からいなくなってしまったかのように影が薄くなってしまう分かれ道となりました。
というのも、馬良(季常)は荊州の名家出身であり、地元の人たちから絶大なる人望があったことが荊州に留めておく理由だったと言われています。また、当時の荊州は北に曹操(孟徳)、東に孫権(仲謀)というライバルの領土と接している重要な拠点で、ここをしっかりと守れる人材として馬良(季常)に白羽の矢が立ったのです。ちなみに、劉備(玄徳)が益州入りした後、諸葛亮(孔明)も随行のために荊州を離れるのですが、そのときも馬良(季常)は荊州に留まったと見られています。
諸葛亮(孔明)と義兄弟の契りを結んだ白眉
■ 諸葛亮(孔明)と義兄弟の契りを結んだ白眉
諸葛亮(孔明)と義兄弟の契りを結んだ白眉
劉備(玄徳)は益州を手に入れるために兵を動かします。でも、あまり戦は得意ではなかったようなんですね。軍師代理として諸葛亮(孔明)の代わりに付き従っていた龐統(士元)を参謀に、雒城を攻めるわけですが、劉璋(季玉)軍の守将で息子の劉循(字は不明)と、その配下の武将・張任(字は不明)が籠城し、なかなか攻め落とすことができませんでした。そして、なんと落鳳坡という場所で龐統(士元)が張任の矢を受けて死んでしまうという事件が起こってしまうのです。
なお、龐統(士元)はこのとき、劉備(玄徳)の愛馬で、白馬の的盧に乗っており、張任は劉備
(玄徳)と間違えて射殺したと言われています。その直前、落鳳坡という土地だということを聞いた龐統(士元)は不吉な名前の土地だと思ったそうです。なぜなら、自分のニックネームが「鳳雛(おおとりのひな)」で、その鳳が落ちる場所という意味だったからです。
さて、龐統(士元)を失った劉備(玄徳)は、参謀となる軍師が必要となり、やむを得ず諸葛亮(孔明)を招集します。そして、あっさりと雒城を落とすと馬良(季常)は諸葛亮(孔明)にお祝いの手紙を書きます。その文中に諸葛亮(孔明)のことを「尊兄」と呼んでいるため、後に陳寿「三国志」に注釈を入れた裴松之が、諸葛亮(孔明)と馬良(季常)は義兄弟の契りを結んだのではないかと推測しています。
劉備(玄徳)の戦下手が招いた馬良(季常)の最期
■ 劉備(玄徳)の戦下手が招いた馬良(季常)の最期
劉備(玄徳)の戦下手が招いた馬良(季常)の最期
その後、馬良(季常)は左将軍掾に任命されたり、使者として呉の孫権(仲謀)のもとへ赴き、自らの文才で同盟関係を強固なものにするのに一役買ったり、五渓の異民族を帰順させるなど、手堅い仕事ぶりで才を発揮してはいます。
そして、年を経て劉備(玄徳)が呉の大都督・陸遜(伯言)と対峙した際、前後に長い戦線を敷いたことで、大軍を壊滅状態にまで追い込まれてしまうことになり、このとき馬良(季常)も戦死してしまうのです。これが、世にいう「夷陵の戦い」です。
まとめ
■ まとめ
まとめ
これが、三国志正史および演義に登場する馬良(季常)のエピソードとして残されている内容になります。荊州の名家出身で、知力は非常に高かったものの、戦術を組み立てたり、謀略を操ったりといった軍師型のタイプではなかったようです。逆に、弟の馬謖(幼常)は知力に加え、戦略を練ることに才能がありそうだと諸葛亮(孔明)は見ていましたが、皆さんご存知の「街亭の戦い」で大失態を犯してしまうことになります。
馬良(季常)は決して華々しい活躍を戦場で見せた知将ではありませんでしたが、こうした地味でも堅実な仕事をする人は上司からの信頼も厚かったのでしょうね。