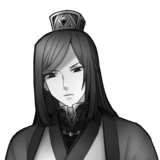蜀の北伐
■ 蜀の北伐
蜀の北伐
228年になってついに蜀は魏を倒すべく「北伐」を開始します。劉備(玄徳)が魏を滅ぼすために蜀を建国し、皇帝に即位したのが221年のことですから7年もの月日が経過していたことになります。
北伐が遅れた理由は「夷陵の敗戦」によるものです。この戦いによって劉備(玄徳)と孫権は完全に敵対関係になってしまいました。さらに陸遜の火計に敗れ甚大な損害を出したことで蜀は国力を大きく低下してしまうことになります。孫権との外交修復、国力の回復にこれだけの時間が必要だったということです。これも蜀に有能な諸葛亮がいたからこそ7年間で回復できたわけで、諸葛亮がいなければ北伐など永遠に始めることはできなかったかもしれません。
第一次北伐のメンバー
■ 第一次北伐のメンバー
第一次北伐のメンバー
北伐の作戦の総司令官は蜀の丞相・諸葛亮です。名軍師として知られる諸葛亮でしたが、南蛮の平定で指揮はとった経験があるものの、大国である魏との戦争で指揮をとるのは初めてのことです。不安もかなりあったに違いありません。蜀建国の志を再確認すべく、「出師表」を上奏し、自分自身と将兵を奮い立たせ出陣しています。
このときの蜀の北伐に出陣した人材で名を知られていたのは、諸葛亮の他に五虎大将の趙雲、猛将で知られる魏延くらいです。あとは廖化、鄧芝、楊儀、張翼、馬岱、馬謖、王平、向朗、これに加えて「三国志演義」では南蛮統治で活躍していた張嶷や馬忠、張飛の子の張苞、関羽の子の関興などの名前があります。どちらにせよ人材不足だったことは間違いありません。
第一次北伐の作戦
■ 第一次北伐の作戦
第一次北伐の作戦
当初の作戦では荊州の上庸郡を守る敵の孟達が寝返り、大きく戦況を動かすことになっていましたが、この計略は看破した司馬懿によって潰されています。荊州方面の道は閉ざされ、諸葛亮は漢中から北上するしか手がなくなってしまうのです。
それでもルートは様々ありました。問題は漢中から北上するには秦嶺山脈を踏破しなければならないことです。最短ルートは長安に続く子午道でしたが、こちらは険峻であり道が狭く大軍の移動には適していません。他に駱谷道、郿に続く褒斜道(斜谷道)、さらに西の陳倉に出る道、そして陽平関から武都、天水を通って迂回する道もありました。
諸葛亮は趙雲と鄧芝を褒斜道から侵攻させ、箕谷に駐屯させます。魏は皇帝である明帝(曹叡)が直々に親征していましたが、対蜀の総司令官は曹真です。曹真は敵の主力である趙雲を迎撃するために褒斜道を進みます。しかし諸葛亮は趙雲の軍を、曹真を引きつける囮にしていました。自身は本当の主力を率いて武都からさらに西の祁山に侵攻します。こうして長安の西に位置する南安・天水・安定の三郡を降しました。
諸葛亮はもっともリスクの少ない遠回りのルートを選んだのです。
泣いて馬謖を斬る
■ 泣いて馬謖を斬る
泣いて馬謖を斬る
ここで諸葛亮は天水郡より北東にある要衝・街亭を馬謖に守らせました。街亭を魏軍に奪われると、そのまま南下して武都が侵攻を受けます。すると祁山に主力を置く諸葛亮は漢中との兵站を断たれることになり、全滅する可能性が出てくるのです。
おそらく諸葛亮は敵の主力を褒斜道に封じ、街亭を守っている間に涼州全域を平定したかったのでしょう。そして万全の態勢で長安の攻略に臨む予定だったのです。かなりの時間を費やすことになりますが、これがもっとも堅実な作戦でした。
しかし馬謖が山頂に陣を築き、魏の張郃に大敗するという予想外の事態になります。作戦は瓦解し、諸葛亮は三郡を放棄して全軍退却することになるのです。そして敗戦の責任をとって諸葛亮は降格、馬謖は処刑されました。
こうして第一次北伐は失敗に終わったのです。
馬謖が街亭を守り抜いていたら戦局は変わったのか
■ 馬謖が街亭を守り抜いていたら戦局は変わったのか
馬謖が街亭を守り抜いていたら戦局は変わったのか
馬謖が街亭を守り抜いていたら戦局は変わったのか
諸葛亮はまだ涼州の隴西郡を落とせずにいました。隴西郡は天水・南安郡より西にあり、ここさえ落としてしまえば主力を天水郡より東に向けることができました。そうすれば五万の兵を率いて街亭を攻略しようとしていた張郃の軍も撃退することができたはずです。このあたりがかなり微妙な時間との戦いだったのでしょう。隴西郡が落ちるのが先か、街亭が落ちるのが先か。諸葛亮の計算では、馬謖が徹底的に守りを貫けば、街亭が落ちるより先に隴西郡を平定できるはずでした。
しかしこれはあくまでも希望的観測です。馬謖が山頂に陣を築いていなくても先に街亭は落ちていたかもしれません。そうすれば諸葛亮は撤退しなければならなかったわけです。むしろ山頂に陣を築いていたからこそ五万の敵兵を完全に足止めできていたともいえます。もしかすると、馬謖の計算ではその間に隴西郡が先に落ちると予想していたのではないでしょうか。
果たして馬謖の失策によって第一次北伐は失敗に終わったのでしょうか。隴西郡攻略に時間をかけすぎたことが作戦の失敗につながったという可能性もあります。
まとめ・もし馬謖が街亭を守り抜いていたら
■ まとめ・もし馬謖が街亭を守り抜いていたら
まとめ・もし馬謖が街亭を守り抜いていたら
馬謖が街亭を守っている間に隴西郡を攻略できたとすると、諸葛亮は主力を一気に東に向けることになります。張郃を破り、陳倉、五丈原を抜けて郿にたどり着くでしょう。すると褒斜道にいる曹真は前から趙雲、背後から諸葛亮に挟まれる形になるのです。おそらく曹真軍は全滅するでしょう。すると明帝が守る長安は丸裸の状態です。当然、明帝は洛陽や鄴に下がることになるでしょうが、蜀は益州に涼州・雍州を加えることになり、国土・国力ともにかなりパワーアップすることになります。
この影響はもちろん遠く東の地の合肥の戦線にも響きますので、孫権は合肥を落とし、徐州や豫州に迫ることになります。魏は危機的状況に陥ったはずです。戦線を黄河まで下げることになったかもしれません。圧倒的だった魏の国力は大きく低下します。もはや三国は完全に拮抗した勢力構図となるのです。
というのが、「もし馬謖が街亭を守り抜いていたら」という歴史IFになります。しかしはたしてここまで上手く事が進んだかどうか。かなり希望的観測を含んでいます。魏の司馬懿が必ず立ちふさがったことでしょう。
ただ、涼州だけでも押さえておけば、以後の戦いで蜀は兵糧不足に悩むことはなかったかもしれません。どうなっていたのだろうと考えると、想像が膨らみますね。