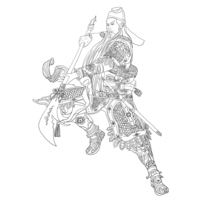孫権の信任が厚くなる陸遜
■ 孫権の信任が厚くなる陸遜
孫権の信任が厚くなる陸遜
蜀は劉備(玄徳)が死去すると、劉禅が蜀の皇帝に即位し、政務は丞相の諸葛亮が執り行うようになりました。諸葛亮は呉と連携して魏に攻め入ることを念頭に置き、呉との和平を望んでいました。これは孫権や陸遜と共通した認識となり、これ以降は諸葛亮の窓口として陸遜が外交を取り仕切る形となっていきます。孫権は陸遜の自分の印章を預け、魏と呉の手紙に関しては陸遜が最終的にチェックするほど孫権からの信任を得ていました。
呉の領土は広大なので、まだまだ耕されていない領地があり、孫権は民衆が疲弊しているのを受け、何か良案がないか思案していました。そこで陸遜は軍部や政務に勤しむ諸将たちが自ら農地を開墾すればいいと考え、自ら頼むように仕向けます。これを受け、孫権は自らが実践するようにし、呉の諸将たちが率先して農地を耕すようになっていきました。
また、陸遜は孫権が長く政権を担っていることから、呉の今後を憂い、奸臣に耳を貸すことのないよう、孫権に上奏しています。政治の分野では孫策時代の良臣たちが亡くなるのにつれて、孫権の子どもたちに付き従うものたちは、野心を持って行動していることが多く、孫権に正しい政治を導いてほしいという願いからきていました。
後に呉は孫権の後継者争いで国を乱すことになるので、陸遜の考えは正しいといえました。孫権もこのときは陸遜の考えに同調し、幕僚の諸葛瑾に対して今の法令を見直すよう指示を出しています。
石亭の戦いで勝利
■ 石亭の戦いで勝利
石亭の戦いで勝利
曹丕が226年に死去すると、曹叡が跡を継ぎました。蜀と呉は共同で北上遠征する計画をしますが、思わぬ形で蜀が街亭の戦いで敗れてしまい、魏の主力が呉へと向かうことが可能となりました。そこで、新しい皇帝は魏が混乱していると思わせないためか、呉に対して大規模な遠征軍を向かわせます。
対呉の総司令官で、長年に渡って孫権を悩ませた曹休だけでなく、荊州方面からは司馬懿仲達も参戦し、呉に迫ってきました。この戦いに先立ち、曹休は10万の軍を率いる大将軍であり、切れ者でもあるので、生半可な策では通用しないと考えて呉では一計を案じます。それは魏との国境を構えた太守である周魴が偽の降伏を魏に申し出て、曹休の軍を石亭に誘い込もうと考えました。
曹休陣営では周魴が偽りの投降ではないかと疑うものもいましたが、使者の迫真の演技もあり、これが本当ならばたやすく呉を征服できると踏んだ曹休によって降伏を認めました。策が成ったことを受け、陸遜は軍を分けて中央の軍を率い、左右には朱桓と全琮にそれぞれ3万ずつの兵を与えました。
曹休は石亭まで進軍すると長い隊列になり、ここで呉軍の気配を気づいて自分の過ちを悟りましたが、大軍であることからこのまま戦いに挑みました。その刹那に陸遜らが急襲してきます。曹休も万が一を考えて伏兵を用意していましたが、これは陸遜が見破り、すべて蹴散らしています。
陸遜らは追撃をかけて追い込み、義軍を散々に打ち破りました。かろうじて脱出できた曹休は、皇族にあることから処罰には問われませんでしたが、この惨敗の責任を重んじ、重病となって死去しています。
呉の内政にも活躍し、皇族の教育係でご意見番となる
■ 呉の内政にも活躍し、皇族の教育係でご意見番となる
呉の内政にも活躍し、皇族の教育係でご意見番となる
数年前から計画していた呉王朝の設立へ向け、229年に孫権が皇帝に即位しました。これを受けて陸遜は上大将軍に昇進し、軍務だけでなく、太子の後見として教育係も兼ねるようになります。陸遜は当初太子のみの教育となっていましたが、他の皇子や公子も面倒をみる様になっていきます。
孫権の寵愛を受けた公子たちも、好き放題に政務を取り繕っていましたが、陸遜は政治ととはすべては民衆のためにあるものと説き、孫呉の命運を司る若い皇族たちを諭していきます。一般に役人や諸将が口を出せないのをいいことに、職務が怠慢になっていく公子もいましたが、陸遜は直接注意するほど、真剣に向き合っていきました。
陸遜は厳罰化する刑罰を憂い、罪人にももう一度チャンスを与えるように孫権に上奏しています。陸遜は先を見通す目が光り、孫権と意見が食い違うときも務めて冷静に進言していました。その甲斐もあり、陸遜と孫権が噛み合っているときは、蜀や魏から侵略されることもなく、呉の領土は豊かに安定していきます。
荊州侵攻軍でまさかの失態もすぐにカバー
■ 荊州侵攻軍でまさかの失態もすぐにカバー
荊州侵攻軍でまさかの失態もすぐにカバー
諸葛亮が実権を掌握していた蜀は、度々北伐を繰り返し、魏とせめぎ合いを繰り返していきました。若くして君主の座についた孫権でしたが、長期政権となっても安定した政務だけが取り柄というわけではなく、234年には孫権自らが合肥に出兵しています。この時は陸遜が別働隊となって襄陽から侵攻していきます。この戦いは第五次北伐となった蜀が西から北上し、南から陸遜、東から孫権と魏の主力を引き離す意味合いもあり、とても重大な一戦といえました。
陸遜は孫権との連携を確かめるべく、自軍の戦況報告を腹心に託していました。しかし、この部下が魏軍に捕まる失態を犯し、捕虜となってしまいます。副将の諸葛瑾は自軍の機密情報が漏えいしたかもしれない不安に駆られ、慌てて陸遜の元へと尋ねます。
さすがの陸遜もこのときばかりは呆然となり、すぐに行動に出ることができませんでしたが、並みの将軍ではないことを理解している諸葛瑾は、陸遜が何かを考えているに違いないと察しました。
落ち着きを取り戻した陸遜は、改めて状況を冷静に分析し、自軍の撤退を指示します。陸遜は撤退のさ中、別働隊を作って狩猟をすると見せかけて、江夏の城を攻め立てました。油断しきっていた各城は多くの被害を出し、陸遜らは追撃を受けることなく退却することができました。
敵方の民衆を見方につける
■ 敵方の民衆を見方につける
敵方の民衆を見方につける
この撤退戦では魏軍にも大きな被害が出ており、ある城では民衆をなぎ倒して退却し、まだ味方の将兵や民が取り残されているのに城門を閉めた魏の将もいました。陸遜は彼らを哀れに思い、捕虜として丁寧に扱い、軍にも規律を守って乱暴を禁止し、自由な帰宅を許しました。
この時代に捕虜になれば、辱めを受けたり、拷問や惨殺されたりと悲惨な目に遭うのを覚悟しなければならないともいえますが、捕虜となった魏の民や将兵たちは陸遜の寛大な処置に感激して自ら呉に投降するものも相次いだといいます。
また、呉との国境にある江夏に対し、陸遜は魏の江夏太守を欺き、降伏の準備が整っているとした偽の手紙を送り付けて動揺させ、江夏の将兵の信頼を削ぐことに成功しています。この結果、江夏太守は交代となり、呉の国境を脅かす余裕を与えさせない陸遜の手腕が冴えわたりました。