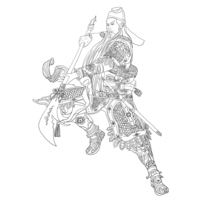司馬懿と公孫淵
■ 司馬懿と公孫淵
司馬懿と公孫淵
諸葛亮の死後、蜀漢及びその同盟国である呉が攻めてくることもなくなり、魏はしばらく平和でした。ところが、その魏で国を揺るがすような大事件が起こります。遼東の公孫淵の反乱です。公孫淵の父は袁尚・袁煕を討ち、首を曹操に届けた公孫康です。その時から遼東で勢力を持っていました。そして、公孫淵の代になると、呉と連絡をするなど、外交戦略をとります。そのことが魏を怒らせ、上洛を命じられます。公孫淵は反抗し、ついに挙兵します。毌丘倹率いる魏の征討軍を撃退した公孫淵は独立を宣言し、燕を建国します。それに対して、魏の明帝(曹叡)は司馬懿に征討を命じます。明帝の命令に対して司馬懿は
「公孫淵は城を捨てて逃げるのが上策、遼水を利用して我軍を迎え撃つのが中策、城に立てこもって籠城するのが下策で我軍の虜になるでしょう。ですが、公孫淵は頭が回らず下策をとるでしょう」
「行きに100日、攻撃に100日、帰りに100日、休息に60日を当てれば1年で充分です」
と答えており、いずれもその通りになります。
また、遼東が大雨で遠征には不利だとの情報が入り、明帝の側近が遠征の中止を進言すると
「司馬懿は状況に合わせて兵を動かすことの出来る人物だ。彼に任せておけば何の心配もない」
と答えました。一方公孫淵が呉に援軍を求めると、皇帝孫権は
「司馬懿は兵を扱うこと神のごとくだと聞いている。そんな人物を相手に戦うことになるとはあなたも大変なことだ。」
と返信しました。公孫淵の反乱の時代には司馬懿の高名は中国中に広まっていたことがわかります。
そして、明帝や孫権が言った通り、司馬懿は公孫淵を討ち破り都へ凱旋してきます
司馬懿と曹爽
■ 司馬懿と曹爽
司馬懿と曹爽
明帝が死去し、少帝(曹芳)が即位すると、後事を託されたのは司馬懿と曹爽(曹真の息子)でした。司馬懿と曹爽の間では権力争いが行われます。まず、権力独占を狙う曹爽によって司馬懿は名誉職である太傅に祭り上げられます。ですが、ここが演義と微妙に違うところですが、軍権はそのままで、相変わらず対蜀漢の最前線を任じられていました。つまり内政は曹爽、軍事は司馬懿が握ることになりました。
そうこうしている内に二人の権力争いはエスカレートしていきます。ここで司馬懿の策略が炸裂します。まずは70歳近い年齢を理由に引退をし、病気ということで家に引きこもります。ですが、曹爽はそれくらいでは油断せず、引き続き司馬懿を警戒します。続いて曹爽の命令で見舞いに来た使者の前でボケ老人を演じます。わざと薬をこぼしたり聞き間違えをしたりしました。使者がそれを曹爽に
「司馬懿はもう恐れるに足りません」
と報告すると、曹爽もいよいよ油断をします。
少帝が明帝の墓参りに行く際に曹爽もお供をし、首都洛陽から離れます。その機会を狙っていた司馬懿はクーデターを起こします。郭太后より曹爽免官の詔勅をもらい、洛陽を征します。そして、曹爽に対して
「免官するだけです。命までは取りません」
と伝え、降伏させると監視下に軟禁状態にします。結局、最終的には謀反を企んでいるとして曹爽及びその一族郎党を処刑します。
この結果、魏の実験は完全に司馬懿が握ることになります。
司馬懿とその息子
■ 司馬懿とその息子
司馬懿とその息子
司馬懿には司馬師・司馬昭と二人の息子がいました。演義では麒麟児と表現されていますが、二人共聡明で才能ある者たちでした。魏での実権を完全に掌握した司馬懿ですが、その時には70を超えており、間もなく死亡します。死ぬ間際には
「私は常に謀反を疑われないように慎重に行動してきた。私の死後、お前たちも慎重に国を治めていくように」
と言い残します。後を継いだのは長男の司馬師です。
少帝は司馬師を排斥し一族である夏侯玄に執政させようとしました。それを知った司馬師は先手を打ちます。夏侯玄一味の三族を皆殺しにしました。さすがに皇帝を直接害することは出来ませんでしたが、皇帝から斉王に格下げします。また、それを知った毌丘倹が反乱を起こしますが、司馬師自ら討ち果たします。
毌丘倹の乱の後司馬師が死亡します。男児がなかったため、後を継いだのは司馬昭です。司馬昭の時代、諸葛誕が反乱を起こします。司馬昭はそれを討ち滅ぼします。その際に、処刑したのは首謀者のみでその他のものは釈放しました。また、諸葛誕の援軍で呉から来た兵士も皆帰しました。これによって司馬昭の名声が上がることになるのです。
諸葛誕の乱の後、皇帝である高貴郷公(曹髦)が司馬昭打倒のために兵を挙げます。ところが、既に権力が違いすぎ、勝ち目はありません。司馬昭の兵は皇帝を直接害することを恐れ、切りかかってこそ来ませんが、完全に包囲されてしまいます。そして、最後には成済に剣で刺殺されます。ところが、司馬昭は成済を皇帝殺害の罪で処刑します。成済は死ぬ間際、屋根に登り司馬昭を散々罵倒したと言われています。この乱の後、魏の最後の皇帝である元帝(曹奐)が即位します。
司馬昭は蜀漢討伐の軍を起こします。鍾会・鄧艾・諸葛緒に三方面から攻めさせ、蜀漢を滅亡させます。この功績で司馬昭は相国・晋公の地位を得ます。そして晋王へとなりますが、皇帝へと即位することはありませんでした。司馬昭は間もなく死亡し、皇帝への即位はその息子である司馬炎が行うことになるのです。
司馬懿とその地位
■ 司馬懿とその地位
司馬懿とその地位
司馬懿は曹操に召し出された際には文官で、主な役割は太子・公子に仕えることでした。特に皇太子である曹丕には絶大な信頼を得ていました。その後、軍事の進言などをしていくと、そのセンスが認められ曹丕の時代になると将軍としての地位を得ることになります。
演義では蜀漢の諸葛亮と対陣するため、軍師というイメージが強い司馬懿ですが、正史では軍師というよりは自ら兵士を率いる将軍でした。また、曹爽との権力争いがあり、それに勝利したため、董卓や曹操のように丞相や相国といった地位に着いたのかと思うと、そういった内政のトップである宰相的な地位についたこともありません。曹爽との権力争いの後、丞相の位を与えられることになった時も辞退しました。
司馬懿が漫画やゲームでラスボスや黒幕のように書かれることが多いです。おそらく、権力争いに勝ち残ったので裏で謀略を練るに優れているとか、国のトップであるとか、そんなイメージが有るのでしょう。ですが、正史での司馬懿は将軍として自ら兵士を率いて矢面に立つ人物だったのです。決して裏にこもっているタイプではありませんでした。