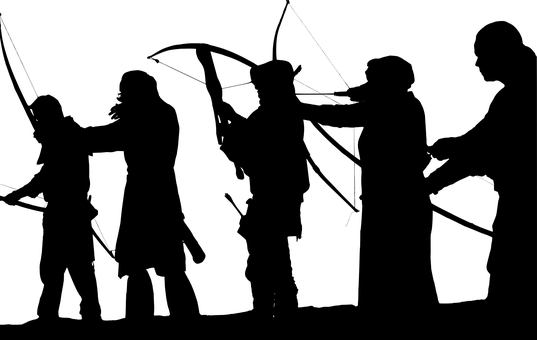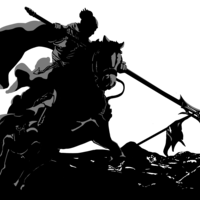周瑜(公瑾)も驚愕した諸葛亮(孔明)の奇策
■ 周瑜(公瑾)も驚愕した諸葛亮(孔明)の奇策
周瑜(公瑾)も驚愕した諸葛亮(孔明)の奇策
諸葛亮(孔明)の智謀を知れば知るほどその存在への危機感を募らせた周瑜(公瑾)は、諸葛亮(孔明)を亡き者にせんとさまざまな罠を仕掛けます。
三国志演義ではそのひとつとして赤壁大戦の折に周瑜(公瑾)が諸葛亮(孔明)に対して「10日で10万本の矢を用意しろ」という無茶ぶりをします。すると、諸葛亮(孔明)は涼しい顔で「10万本の矢ですが、3日で用意して見せましょう」と返答しました。
(しめしめ…自分の首を自分でしめるとはまさにこのこと)と思った周瑜(公瑾)はコソコソと職人たちが納期に矢の制作が間に合わないよう根回しを行いました。
10万本の矢収集の一部始終
■ 10万本の矢収集の一部始終
10万本の矢収集の一部始終
周瑜(公瑾)が職人たちに根回しをしていたことを知ってか知らずか、諸葛亮(孔明)の態度は依然として慌てた様子がなく、むしろ日を追うごとに自信に満ちた表情を浮かべるようになります。諸葛亮(孔明)は蜀の兵士たちに約束した3日間のうち、その大半を藁人形の制作に取り掛からせました。
そして諸葛亮(孔明)は船20数艙に兵士を30名、藁人形を乗せ船の周りには幔幕を張らせておくようにと指示しただけでした。
いよいよ約束の3日目です。その日は朝から濃い霧が川辺を埋め尽くしていました。諸葛亮(孔明)は20数艙の船団を引き連れ、曹操の大船団へと近づくと突如ドラや太鼓を打ち鳴らし、兵士たちに一斉に鬨の声をあげさせました。濃霧の中、突然現れた敵襲に驚いた曹操軍は慌てふためき、「矢を射かけて近づけさせるな」という曹操(孟徳)の命令で視界が遮られた状況でとにかく矢を雨のように降らせました。
諸葛亮(孔明)は頃合いを見計らって全軍退却の命令をします。霧が晴れると船に積んだ藁人形や幔幕には無数の矢が突き刺さっていました。20数艙に降り注いだ矢の本数を数えると、10万本をゆうに超えていました。
周瑜(公瑾)は「諸葛亮(孔明)の智謀奇策は、到底私が思いつくことのできないものだ」と驚愕しました。
10万本の矢の元ネタ
■ 10万本の矢の元ネタ
10万本の矢の元ネタ
史実には諸葛亮(孔明)が集めたとされる10万本の矢の元ネタがあります。正史三国志の「孫権伝」という章によれば、西暦213年、孫権(仲謀)は水軍を率いて曹操(孟徳)と儒須(じゅし)にて対峙しました。あるとき孫権(仲謀)が大船に乗って敵情視察に出かけたところ、曹操軍はそれに対して執拗に矢を射かけました。
船の側面に大量の矢を受けた孫権(仲謀)の船は大量の矢のせいで傾き、危うく転覆しようになりました。そこで孫権(仲謀)は機転を利かせて船を180度旋回させるように指示を出し、反対側の側面にもわざと矢を受けさせてバランスをとれるようにしました。そうして航行を安定させてから自軍へと引き換えしていったのです。
これが「10万本の矢」の元ネタです。10万本の矢を集めたのは諸葛亮(孔明)の奇策ではなく、孫権(仲謀)の機転でした。
関羽(雲長)が華容道で曹操(孟徳)を見逃したのがフィクション?
■ 関羽(雲長)が華容道で曹操(孟徳)を見逃したのがフィクション?
関羽(雲長)が華容道で曹操(孟徳)を見逃したのがフィクション?
赤壁大戦で大敗を喫した曹操(孟徳)はわずかに生き残った手勢を引き連れて、敗走を始めます。それはもはや袁紹(本初)の大軍を打ち負かしたかつての威勢は失われたようでした。各地で伏兵に遭遇し、さんざんに蹴散らされた曹軍は華容道までたどり着くことができました。道は狭く、雨で地面がぬかるんでそれでも先へ進もうとする中、兵士たちは次々に倒れてゆきました。そのとき曹操(孟徳)に残された曹軍の兵士はたったの300騎余りでした。
曹軍を待ち受ける最後の伏兵として登場したのが関羽(雲長)でした。諸葛亮(孔明)は関羽(雲長)の忠義心に厚い性格をよくわかっていたので、劉備(玄徳)に「関公を今回の戦に参加させるのは得策ではない」と反対していました。劉備(玄徳)も同じように考えていたのですが関羽(雲長)は「曹操(孟徳)との縁はすでに切れています」と豪語し、曹操(孟徳)に対して負い目がないことを全蜀軍へ証明するために参加しました。
最後の最後で関羽(雲長)に遭遇してしまった曹軍は「もはやこれまで…」という空気が辺りに立ちこみ戦意はすでにありませんでした。
諦めかけていた曹操(孟徳)に参謀の程昱が耳打ちをします。
「関羽(雲長)は義の人です。また、任侠に富んだ豪傑でもあります。我が君から受けた以前の格別な恩義を顧みて見逃してくれるやも知れません。ここは恥を忍んでお目こぼしを頼んでみては?」
曹操(孟徳)は下馬し、関羽(雲長)の前に進み出て親しげに挨拶をすると「雲長よ…私はかつてそなたに恩義を与え、劉備が見つかった折には咎めることなく送り出してやった。今私と私の兵士たちにはすでに戦意はなく、ただただ帰郷を目指すのみ。雲長を誠の好漢と見込んで、ここはどうか私たちを見逃してはもらえないだろうか。頼む。」と助命を嘆願しました。それに続いて曹軍の兵士たちも必死に命乞いをします。その哀れな姿に関羽(雲長)は手を下すことができず、自軍の兵士に「お前ら道を開けて曹丞相をお通ししろ」と命令しました。その言葉を聞いてホッとした曹操(孟徳)は関羽(雲長)に感謝の意を表わし、そそくさと華容道を通過しました。
本当はその場に関羽(雲長)はいなかった
■ 本当はその場に関羽(雲長)はいなかった
本当はその場に関羽(雲長)はいなかった
陳寿の記す正史三国志の魏志の武帝紀という章では、曹操(孟徳)は確かに「華容道を通過して徒歩で撤退した」ということが書かれています。また、大雨によって道がぬかるみ撤退に難儀していたこともどうやら事実であるようです。ところが、華容道で関羽(雲長)が待ち受けていたとする記述は史実にはどこにも見当たりません。このエピソードは関羽(雲長)の義侠心を際立たせるために羅貫中が加えたフィクションでした。それだけ関羽(雲長)にとって「義」というのは大切な要素でした。
封建時代が長く続いた中国で民衆の心を掌握したのは関羽(雲長)という義に厚い好漢です。それだけに、このエピソードは真実として語り継がれてきました。
まとめ
■ まとめ
まとめ
いかがでしょう?三国志演義はたしかに読んでいてハラハラ、ドキドキして大変面白い物語です。しかし、史実と三国志演義を比較してみると蜀将がカッコよく見えるように意識して書かれていることがわかると思います。つまり三国志演義は蜀贔屓のために事実を捻じ曲げながら書かれている物語であるとも言えます。