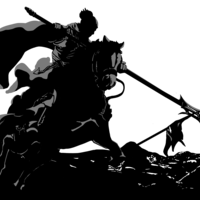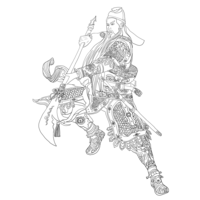降伏し投降を決めた呂布奉先
■ 降伏し投降を決めた呂布奉先
降伏し投降を決めた呂布奉先
さかのぼること198年、劉備の守護する小沛を呂布奉先は陥落させることに成功しました。これをキッカケとして当時劉備玄徳のバックアップをしていた曹操孟徳は呂布奉先の領地だった啓州に攻め込んできました。
これに応戦しようとした呂布奉先は参謀であった陳宮に戦ってはいけないと止められます。しかしその制止を振り切って曹操孟徳と戦います。武人として功績を残してきた呂布奉先ですから、敵に背中をみせるのが嫌だったのでしょうが、結果的には敗れてしまい籠城することとなったのです。
籠城をしていると、日本でもありがちですが水攻めがはじまります。さすが戦いを熟知している曹操孟徳といった感じで順調に呂布奉先は追い込まれていきます。この水攻めによって耐えかねた重臣たちは参謀の陳宮を捕らえて差し出し降伏してしまいました。
ひとりぼっちとなってしまった呂布奉先は曹操孟徳の兵たちに囲まれて降伏せざるを得なくなってしまったのです。呂布奉先が戦うことを諦めた瞬間でした。
命乞いをする呂布奉先
■ 命乞いをする呂布奉先
命乞いをする呂布奉先
死ぬ間際に潔かった関羽雲長などに比べて三国志史上最強と言われた呂布奉先は捕らえられた後、命乞いをしました。曹操孟徳の前に引き出された呂布奉先は曹操孟徳に自分がいれば天下をとるのに役立つのだから、その覚悟はあるのだから曹操孟徳に忠誠を誓うのだから命だけは助けて欲しいといったような趣旨のことを述べました。
確かに呂布奉先がいれば曹操孟徳の天下はグッと近くなるでしょうが、これまでに丁原と董卓を裏切ってきた過去があるので当然ながら信用されません。三度目の正直という言葉もありますが、二度あることは三度あるのです。この時、呂布奉先を信じない方が良いと言ったのは劉備玄徳でした。
呂布奉先は劉備玄徳こそ一番腹黒いと思っていたので、劉備玄徳こそ信用ならないと言い返したのですが、それは聞き入れられず、命乞いは失敗に終わったのです。そして呂布奉先は処刑されることが決まりました。
呂布奉先の処刑方法
■ 呂布奉先の処刑方法
呂布奉先の処刑方法
処刑されることが決まった呂布奉先ですが、その処刑方法について気になる方もいるかと思います。驚くべき処刑方法とは実は絞首刑でした。日本の戦国時代ですと大半の場合は斬首刑が基本になっていましたが、三国志の時代には絞首刑、つまりは首を絞めることで窒息死させるというものだったのです。
そう考えれば処刑の仕方は残虐だとか汚いだとかいうイメージはありませんが、絞首刑で亡くなったことが確認された後、斬首され、さらし首にされ、埋葬されるといった流れは言うほど変わらないのでやはり、武人ですのでそういった最期を迎えるのは仕方がないのかもしれません。
ただ、やはり投降して命乞いをして呂布奉先が亡くなるだなんて呂布奉先のファンからすると残念ですよね。あれだけの武将が戦場で華々しく散らないなんて格好悪いじゃないですか、日本でいう真田幸村のように華々しく散っていれば呂布奉先の株ももっとあがったでしょうが、所詮は裏切者という扱いなのでこの程度の死に方が似合っていると言えば似合っているのかもしれません。
なぜ呂布は最後まで裏切者扱いをされていたのか
■ なぜ呂布は最後まで裏切者扱いをされていたのか
なぜ呂布は最後まで裏切者扱いをされていたのか
呂布奉先はなぜ何度も裏切りを重ねてしまったのか、その答えはその狡猾さにあります。呂布奉先という人間は損得勘定で動く、計算高い人間でした。物事を決断する際に感情というものが欠落していたであろうと思わされるほどの立ち回りをしていたのです。現代で言えばまさにサイコパスのような人種でした。
最初の丁原を裏切った際も、董卓に誘われるがまま寝返りました。ただおそらく呂布奉先的にはこのまま丁原の下についているよりも董卓についたほうが自分の将来にとって得だとか、もしかすると後に董卓を裏切るつもりがこの瞬間に既にあったのではないかと思わせるほど頭の良い人物だったりもします。より強大な力を手にすることに執着しているのならばそのために必要のないものは裏切っていくスタイルなんですね。
ですので、後に董卓を裏切った際もついていく価値がないと判断したからでした。その後、劉備玄徳にも加担するふりをしますが、呂布奉先からすれば劉備玄徳の外面の良さに信用がならないと考えていたので劉備玄徳の領地をあっさり奪ってしまい、これもまた裏切りと言われました。
でも、考えてみれば裏切りも何も呂布奉先という人間は主君に対して最初から忠誠など誓ったことがないのではないでしょうか?というよりも人の心のうちが見えてしまうので人を信用できずついていこうにも誰にもついていけなかったのだと思います。しかし、最後に命乞いをした曹操孟徳のような人格者の家来になっていたのなら、もしかすると呂布奉先は自分の居場所を見つけられたのかもしれません。
ある意味、才能はありながらも人の邪念に気づいてしまう勘の良さを抱えながら生きていた呂布奉先は亡くなってはじめてそこから解放されることになり、亡くなることではじめて安らぎを手にしたのではないかと思います。というかそうであって欲しいと願います。
まとめ
■ まとめ
まとめ
裏切りに裏切りを重ね、狡猾に孤独に生きた三国志史上最強の武将呂布奉先の生涯は華々しく戦場で散ることすら許されないほど惨めな結果になりました。人には表裏の顔があってそれに感づいてしまいがちな呂布奉先はきっと長い間、その人生を苦しんだのかもしれません。
裏切りということは確かに悪いことですが。言い換えれば情に流されず自分の信念を貫いた結果なのではないでしょうか?自分の意思や野心を押し殺して生きてしまうことが果たして本当に正義だと言えるかはわかりません。自分の心に正直に生きた結果が裏切者としての像に繋がってしまっているのならば、呂布奉先は自分の生涯を本望であったと言えるのではないでしょうか?
日本で言えばまさに松永久秀のような扱いです。信じられる、ついていきたいと思えるような主君に巡り合えてさえいればきっと名実ともに優秀で人格者となっていたであろうとは思いますが、残念ながら主君に恵まれなかったというのはとても残念なことですね。
もし、呂布奉先が転生輪廻のもと、生まれ変わることがあるとするのならば、その世界では心の底から信じられる人に巡り合えると良いと心の底から思います。そうすればきっと彼の魂も報われることでしょう。