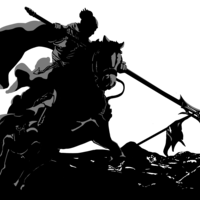皇族の末裔という高貴なる血統
■ 皇族の末裔という高貴なる血統
皇族の末裔という高貴なる血統
劉備(玄徳)が慕われる理由として外すことができないのは、その高貴なる血統ではないでしょうか?劉備(玄徳)は前漢の景帝の子である中山靖王劉勝の末裔であるとされています。ということは劉備(玄徳)は皇族の一員であるということになります。歴史上血統が出世に大きく影響する例は腐るほどありますが、皇族である劉備(玄徳)は誰から見てもサラブレッドだったのです。
ただ、実はといえば劉備(玄徳)の祖先と言われている中山靖王劉勝には50人以上の子供がいるとされており、孫などを含めると120人程度はいたとされています。日本でいう藤原氏などもそうですが、たどっていくと相当数が子孫に該当してしまいます。
ということは中山靖王劉勝の血統だと言われる人物はその時代に5000人以上いたとされるので考えてみれば劉備(玄徳)はいうほど特別な血筋でもないことがわかります。ただ、それをわざわざ口にする人もいないでしょうし、口にしても劉備(玄徳)そのものに魅力がなければ人はついてきません。
劉備(玄徳)が中山靖王劉勝の末裔だから建国できたのではなく、中山靖王劉勝の末裔だという人物が劉備(玄徳)であったからこそ建国できたというのが正解なのかもしれません。ようは人としてのカリスマ性に長けていたから多くの人がついてきたんですね。
優れた能力を持つことがリーダーの資質ではないという考え方
■ 優れた能力を持つことがリーダーの資質ではないという考え方
優れた能力を持つことがリーダーの資質ではないという考え方
優れた能力を持っている人には人がついていくというのはひとつの考え方にしかすぎません。三国志の舞台である中国では理想のリーダーとされるのは優れた能力を持っている人ではありません。では、理想のリーダーとはどのような人物なのでしょうか?
中国で理想のリーダーとされるのは、優れた能力を持つ者ではなく優れた能力を持つ者を上手く扱う事の出来る人がリーダーとされています。つまり自分の部下のモチベーションをあげたり、才能をひきだしてあげたり、上手いこと部下をコントロールできる人が理想のリーダーと言えるわけです。
考えてもみれば、確かに劉備(玄徳)は優れた武力があるわけでもありませんし、多くを部下に任せているように感じます。悪い言い方をすれば部下を利用しているといった感じですが、良い言い方をすれば上手いこと部下を活かしているということになります。
劉備(玄徳)は中国の考え方では理想のリーダーと言えます。確かに個でみれば尊敬できる人物であるかはわかりませんが、リーダーとしては十分に尊敬に値する人物であったのではないかと思います。
自身の損得よりも他人のことを一番に考える義の人
■ 自身の損得よりも他人のことを一番に考える義の人
自身の損得よりも他人のことを一番に考える義の人
義の人。その言葉を聞いてみなさんは誰を思い浮かべるでしょうか?日本の戦国時代であれば、最後まで秀吉公を思い豊臣のために戦った真田幸村や義を重んじ自身に美しくあろうという信念をもった直江兼続などを思い浮かべる人もいるでしょう。実は、劉備(玄徳)も義の人でした。
劉備(玄徳)は実際、そんなに野心はありませんし、勉学に励んでいたわけでもありません。そんなことよりも音楽やファッションなどに強い関心を持っており、堅いイメージとは裏腹に社交的で新しいもの好きであったとされます。
だからこそ多くのものをすんなり受け入れるだけの視野の広さ、器の大きさを持っていたので酒の席などでも簡単に人と打ち解けることができました。そういった性格が関羽雲長や張飛翼徳との深いつながりをよんだとされます。つまりは人に好かれやすいタイプの人間だったということです。この人のためなら何かしたくなるって多くの人に思わせるのも才能ですね。でも、それは自分の損得よりも他人のことを最初に考えるという劉備(玄徳)の人間性がそうさせてるのかもしれませんね。
とにかく低姿勢なリーダー
■ とにかく低姿勢なリーダー
とにかく低姿勢なリーダー
曹操孟徳といえば人に対して人を自分の野心のために利用するといったようなイメージがつきまといますが、劉備(玄徳)はそんなことはなく、人の協力なくして成し遂げることのできないことはあるのだから人を大事にするという考え方を持っています。
例えばですが、人に対して同じことをしてもらうにしても「やれ」といった命令口調や態度では人は動きませんし、動いたとしても人はついてきません。一方で「頼むよ。お願いできないかな」などと言われるとどうでしょう?どうにかしてあげたくなってしまいますよね。
そんなことを知ってか知らずか劉備(玄徳)は自然と人にものを頼む姿勢というのを心得ているリーダーなので人がついてきやすい性格の持ち主だと言われています。もちろん、亡くなる前の呂布奉先が指摘した通り、もしかしたら物凄く腹黒い人物だったという可能性もありませんが、多くの人の中では気持ちよく仕事をさせてくれるリーダーとされているわけです。
現代でも、ふんぞり返って偉そうにしてる上司ってのは随分と嫌われてしまいますよね。一方で部下とフレンドリーに関わって同じ目線でいる上でものを頼む姿勢のある人って何かしてあげたくなりませんか?それに劉備(玄徳)は漢王室を再興させたいという高い志をもってるので、そういう夢や志を持ってる人には自然に心打たれてしまうものなのかもしれませんよね。
まとめ
■ まとめ
まとめ
今回は蜀の名君であるとされる劉備(玄徳)が多くの人に慕われた理由について考察してみましたがいかがでしたでしょうか?人に慕われるのにもっとも大事なのはその人の人柄であることがなんとなくわかりました。確かに現代も含め、人は恐怖やお金で縛ることはできますが、それでは心の底から人はついてきません。
劉備(玄徳)には人の心を掴むようなまるでマインドコントロールをしているかのような魅力があります。ただ、それは人がついていきたいと思えるような人間としての魅力や高い志、人を下に見ず、人を理解しようと努めてといった人好きならではの魅力が備わっているからではないでしょうか?
自分のことしか考えていない人に人は惹かれませんよね。他人を思いやることができるからこそ人の上に立つ資質があると言えるのかもしれません。曹操孟徳や董卓、孫権などといったリーダーは三国志に登場しますが、劉備(玄徳)ほど人の心を掴むのが上手いリーダーというのはいないんだと今回わかりました。きっと現代でもこうしたリーダーは好かれるので、リーダーの立場に立ってる人は劉備(玄徳)を理想のリーダー像としてみると人がついてくるかもしれませんよ。