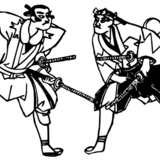三国志と虎
■ 三国志と虎
三国志と虎
三国志には虎にまつわるエピソードが数多くあります。
ひとつは劉備(玄徳)の義弟・張飛の「虎鬚」です。張飛といえば虎鬚の豪傑というイメージが定着しています。しかしこれは「三国志正史」には記載がなく、どうやら「三国志演義」の脚色のようです。
狩猟が好きでよく虎狩りをしたのが孫権です。自分の愛馬を襲われて、孫権は双戟を虎に投げつけたという逸話があります。転じて漫画「蒼天航路」では虎をペットにする孫権が描かれています。
素手で虎と戦ったという逸話があるのが曹操の息子である曹彰です。かなりの怪力を誇っていたようです。三国志演義では漢中を巡る攻防戦で、劉備(玄徳)の養子である劉封を一騎打ちで撃退しています。蒼天航路では素手で孫権のペットの虎を倒しています。
虎痴の異名
■ 虎痴の異名
虎痴の異名
そんな中で虎の名を異名に持つ人物がいます。曹操の近衛隊長である許褚です。「虎痴」と呼ばれ畏怖されました。字(あざな)だと思っている方もいるかもしれませんが違います。許褚の字は仲康です。
許褚が虎痴と呼ばれる理由は、「虎のように力が強い」からです。身長は八尺(180cm以上)あり、腰回りは十囲(110cm以上)で、牛の尾をつかんで百歩(140m以上)引きずって歩いたという記録があります。
一方で性格は慎み深く寡黙だったそうです。日頃はぼんやりしているように見えたことから、軍中では虎痴と渾名されていました。
かなり馬鹿にした呼び方なので、面と向かって許褚を虎痴と呼んだ者はいなかったことでしょう。
主君である曹操は許褚のことを「我が樊噲」と絶賛していますので、曹操すら虎痴などとは呼んでいなかったはずです。
虎豹騎と虎士
■ 虎豹騎と虎士
虎豹騎と虎士
曹操自慢の精鋭騎馬部隊が「虎豹騎」です。こちらにも虎の名がありますね。中国において虎は無敵の強さを象徴するような存在だったということです。
また曹操の近衛兵を「虎士」と呼んでいます。許褚が近衛兵の隊長だったわけですから、「虎痴が虎士を率いていた」わけです。この虎士にはもともと許褚と交友のあった侠客が多く在籍しており、許褚の訓練を受けていたからなのか精鋭揃いでした。
後にこの虎士からは数十名の将軍を輩出しており、校尉となった者も百名を超えたそうです。武将にとっては虎士に選出されることは、エリート街道に乗ったことを示していたのではないでしょうか。そのトップが許褚だったということになります。
馬超との因縁
■ 馬超との因縁
馬超との因縁
「錦馬超」と呼ばれた西涼の猛将・馬超と激突したのが許褚です。
三国志演義では、馬超と熾烈な一騎打ちを演じており、甲冑を脱ぎ捨てて戦い続けても勝負がつかなかったという場面が描かれています。つまり許褚と馬超は同じ強さだったわけです。
三国志正史には、馬超との一騎打ちの記録はありません。「潼関の戦い」では馬超の猛襲から曹操を守り、片手で船の舵を漕ぎながら、反対の手には馬の鞍を掲げて飛来する矢を受けています。許褚がいなければこの時に曹操は馬超に討ち取られていたことでしょう。
その後、曹操と馬超が会見の場を設けることになり、馬超はそこで曹操を殺そうと画策しますが、背後にいるのが許褚だと知り、手が出せなかったと三国志正史に記されています。馬超は許褚のことを虎痴ではなく、「虎侯」と呼んだそうです。
三国志正史では許褚の方が馬超よりも格上に描かれています。
張飛との因縁
■ 張飛との因縁
張飛との因縁
三国志演義でのパワーバランスを見ていくと実に面白いですね。
許褚と一騎打ちで引き分けた馬超は、張魯の客将として張飛と一騎打ちをすることになりますが、こちらも引き分けています。
許褚、馬超、張飛はほぼ互角であることがわかります。
しかし三国志演義の主役は劉備(玄徳)であり、その義弟である張飛です。ですから許褚と張飛が一騎打ちをした場合は、張飛を勝たせ、張飛の方が格上であることを示した方が盛り上がります。
二人が激突したのが漢中を巡る戦いです。兵糧を守る役目にあった許褚を張飛が襲撃するのですが、一騎打ちの末、肩を突かれて許褚は敗れるのです。
あれ?「許褚=馬超=張飛」だったはずなのにおかしいなと矛盾を感じるわけですが、そこは、この時の許褚は酒を飲んでいて力を発揮できない状態だったという設定にして押し通します。
許褚が酒で失敗するのか
■ 許褚が酒で失敗するのか
許褚が酒で失敗するのか
そもそも許褚は片時も曹操のもとを離れず、例え休暇の最中であっても曹操の身を案じて駆け戻り、暗殺を企てていた裏切者を斬り捨てるほどです。
法律を遵守し、曹操の同族の誘いであっても断って警護を続ける忠義の士なのです。
それが酒を飲んで、大切な兵糧を失うような失態をしでかすでしょうか。
酒で失敗するとしたらむしろ張飛の方です。この脚色はさすがに許褚ファンからすれば許せないはずですね。三国志正史にはそのような場面は記されていません。
実は漢中を巡る戦いは、張飛が活躍する最後になります。
三国志演義としては、逆に相手が酒で失敗する姿を描いて、張飛の成長を印象付けようとしたのではないでしょうか。その踏み台として利用されたのが許褚というわけです。
まとめ・許褚の謎
■ まとめ・許褚の謎
まとめ・許褚の謎
許褚はその強さ、その忠実さを曹操に愛され、中堅将軍まで昇進しています。また曹丕が魏の皇帝に即位すると、武衛将軍となっています。さらに二代目皇帝・曹叡にも仕えており、牟郷侯に進封されています。おそらくは病没したのでしょう、没後は壮侯と諡されました。
まさに魏を代表する重臣のひとりなのです。
しかし、ここでひとつの謎が生まれます。典韋が曹操の廟庭に祀られているのに対し、同じく身辺警護で活躍した許褚は祀られていないのです。後に三国志正史の注釈を行った裴松之は理解しがたいと述べています。
まさか、本当に酒を飲んで失態を演じてしまったからなのでしょうか?
廟庭には他に朱霊や臧覇などが合祀されているのです。どう考えても許褚の方が武功は上のはずです。
荀彧は曹操の魏公に真っ向から反対したために外されたのは仕方ないにしても、なぜ許褚が含まれていないのでしょうか。曹操の死因に何か関係があるのでしょうか?
許褚には未だ語られていないエピソードが隠されているのかもしれませんね。三国志演義の方が案外的を射ているのかもしれません。