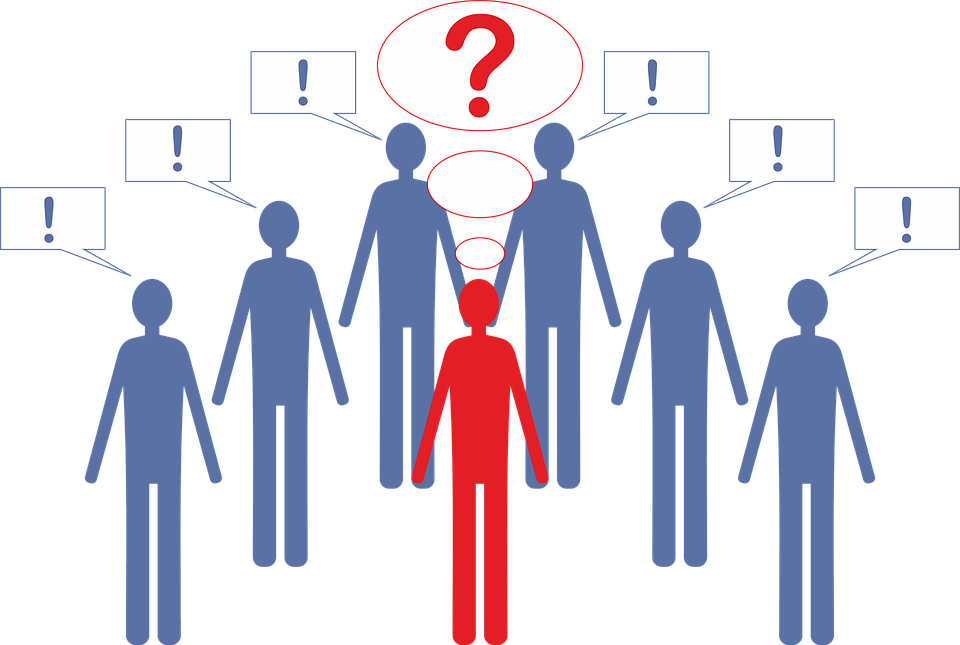赤壁大戦時の曹軍の誇張
■ 赤壁大戦時の曹軍の誇張
赤壁大戦時の曹軍の誇張
兄の遺恨を背負い孫権(仲謀)が18歳という若さで呉の君主となった年、呉の国中を震撼させるできごとが起こります。それは赤壁大戦です。
赤壁大戦は総勢約100万と言われた曹軍と呉・蜀の連合軍10万足らずが戦い、見事10倍以上の曹軍を呉・蜀連合軍が撃退したと伝えられる戦いです。
しかし、赤壁大戦は伝説的な戦だったがためにさまざまな誇張が加えられ、「どこからそんな根拠が?」と疑問に思わざるをえない脚色がところどころに見られます。本記事ではそのひとつである、曹軍総勢100万という大ウソについて説明します。
呉を震撼させた曹操(孟徳)からのメッセージ
■ 呉を震撼させた曹操(孟徳)からのメッセージ
呉を震撼させた曹操(孟徳)からのメッセージ
さて、なぜ呉が震撼したのかと言いますと乱世の奸雄曹操(孟徳)からの一通の手紙から始まります。
その手紙の内容とは、「袁紹(本初)を滅ぼした目下、私は世にはびこる逆賊を討ち、80万の兵を連れて中原に覇を唱えようと思う。あなたの勢力はその途上にあり、もし仇なす者となれば我らは迎え撃たねばならない。降伏の意を示すのであれば、我が軍はあなたの兵や民に危害を加えないと約束しよう。幼少の頃より聡明だと聞こえたあなたなら、どうすることが最善なのかお分かりであろう」というものでした。
呉は戦う前から人数に圧倒されていた
■ 呉は戦う前から人数に圧倒されていた
呉は戦う前から人数に圧倒されていた
呉軍は当時総勢約5万。兄孫策(伯符)がたった数千だった呉軍を獅子奮迅の侵攻によって滅ぼした軍の兵士を吸収し、ようやくここまで成長させた結果でした。
呉軍5万VS曹軍80万。どう考えても勝てないことは明白です。そのため、呉ではいつの間にか曹軍80万が100万へと誇張され「北より曹軍100万が攻めてくるぞ!!」という噂がすぐに広まり、呉の臣下たちはそれを聞いただけで膝を震わせ我も我もと降伏論を唱えました。
呉と同盟を結ぶ蜀と合わせてもこちらはせいぜいと8万といったところで、曹軍の10分の1程度です。しかもリーダーである孫権(仲謀)は実戦の経験が皆無に等しく、「戦場で臨機応変な指揮をとることができるのか?」という不安もありました。
対する曹軍は数で優る上に名族袁紹(本初)を倒し、北方を制圧する戦を潜りぬけた猛者の集団です。さらに、曹操軍は唯一の弱点だった水上戦を克服していました。
南船北馬
■ 南船北馬
南船北馬
中国では古来より「南船北馬」と土地柄の戦い方が説かれていました。広大な草原が広がる北部の移動には馬を使い、長江、黄河など川の多い南部は船を使って移動していました。これは戦時にも当てはまります。
華北の許都を本拠地とする曹操軍は騎馬こそ得意でしたが船を使った水上戦は苦手であると言われてきました。しかし、荊州軍を飲み込んだことで熟練の水兵を手に入れ、水軍を整えていました。曹軍に水軍が配備されたということは、曹軍は非の打ち所がない軍隊になったということを意味しました。
曹軍100万はもとより80万もウソだった
■ 曹軍100万はもとより80万もウソだった
曹軍100万はもとより80万もウソだった
いくらなんでも100万という人数は大げさすぎます。実際、曹操(孟徳)が送った手紙には80万と称していました。しかし、曹操(孟徳)が称する80万という数さえも大きなハッタリです。後世の代になって中国史の専門家が赤壁大戦時の全盛期の曹軍の軍勢を推計しています。その推計結果は多くても25万人。「戦わずして勝つ」ことを目的に軍勢や装備の数のサバを読むことは当たり前のことです。しかし、実質呉軍全体に噂が伝わったときには80万から100万と20万人も上乗せされたのは、それだけ呉の臣下たちが動揺していた証拠だと言っても過言ではありません。
正史三国志の記述によると、赤壁大戦に動員された曹軍は曹操(孟徳)が許都から連れてきた15万、降伏して傘下に下った荊州の兵士が8万の計23万人程度であるとされています。とはいえ、実際の曹操軍の数は呉軍の倍以上あったので、正規の人数を言われても呉の臣下たちは大騒ぎしたことでしょう。
曹操(孟徳)が軍勢の数を盛った理由
■ 曹操(孟徳)が軍勢の数を盛った理由
曹操(孟徳)が軍勢の数を盛った理由
次は曹操(孟徳)側に注目してみましょう。実は曹操(孟徳)も赤壁大戦をできるだけ避けたかったようです。その理由は3点あるのですが、どのようなものなのでしょうか?その理由を以下に書き出してみます。
理由その1 曹軍の兵馬は疲弊していた
■ 理由その1 曹軍の兵馬は疲弊していた
理由その1 曹軍の兵馬は疲弊していた
曹軍の兵士と馬は袁紹(本初)との戦いである官渡の戦いから昼夜を問わず遠征に遠征を重ねて休む暇もありませんでした。
事実夏侯惇(元譲)や荀彧(文若)ら重臣は、焦りを見せている曹操(孟徳)に対し、「兵馬はみな疲弊しています。官渡、長坂波、揚州と転戦に転戦を重ねて己が田畑さえ手付かずにしています。ここはいっそのこと休養を与えて家に帰し、来る年の兵糧の生産に打ち込むべきです。」と進言していました。
そのことはわかっていても曹操(孟徳)はなんとしても早く決着をつけたかったのでしょう。あのけちん坊の曹操(孟徳)が大金を費やして劉表から奪った荊州水軍のために大船団を作ってしまうほどです。しかしながら、兵馬が疲弊していることは曹操(孟徳)自身も十分に理解していました。
理由その2 移動距離が長くなったことで兵糧や戦費を節約したかった
■ 理由その2 移動距離が長くなったことで兵糧や戦費を節約したかった
理由その2 移動距離が長くなったことで兵糧や戦費を節約したかった
戦争をするということはその際の食料や、武器を作ったり、それに従事する職人を雇うお金も必要です。
当時の職人1人当たりの給与や武器の値段はわからないので、兵士たちの食費だけを現代価値の数字になおしてみましょう。中学校の給食は1人分1食あたり約300円、当時は1日2食の食生活だったので1人あたりに1日にかかる食費は約600円です。それに25万をかけてみると約1億5000万円。なんと1日兵士にごはんを食べさせるだけで市区町村の予算レベルの費用がかかっていました。
理由その3 開戦前に貴重な人材を失っていた
■ 理由その3 開戦前に貴重な人材を失っていた
理由その3 開戦前に貴重な人材を失っていた
曹操(孟徳)に降参した荊州軍の中には、劉表の妻である蔡夫人の弟で、諸葛亮(孔明)の義理の叔父にあたる蔡瑁(徳珪)がいました。蔡瑁(徳珪)は曹操(孟徳)から水軍を指揮する腕を買われて水兵の練兵と水軍の指揮を任されていました。ところが、呉から放たれたスパイたちによって曹操(孟徳)はいらぬ心配をしてしまい、それを未然に防ぐために誅殺を命じてしまいました。
あとから謀られたことに気づいた曹操(孟徳)はこればかりは後悔したと言います。
まとめ
■ まとめ
まとめ
いかがでしょうか?
赤壁大戦時曹軍は100万だということは大ウソであったこと。その当初80万だったウソが100万へと膨れ上がった経緯。曹操(孟徳)が軍勢を盛りに盛った理由について説明しました。赤壁大戦は曹軍にとっても呉と蜀の連合軍にとっても一筋縄ではいかなかった戦いであったようですね。