三顧の礼を経て劉備に迎えられた諸葛孔明(諸葛亮)は、次のように献策する。天下を曹操・孫権・劉備(玄徳)の三つの勢力に分けるべし―――この「天下三分の計」によって魏・呉・蜀の三国が成立する、というのはよく知られたストーリーだ。
しかし、正史の「三国志」諸葛亮伝を読むと、「天下三分の計」のイメージはやや変わってくる。渡邉義浩著『「三国志」の政治と思想』(講談社)では、史実をもとに英雄たちの意外な真実を紹介しているが、その中には「天下三分の計」についての記述もある。
諸葛孔明の策を「天下三分」と呼んでもいいのか?
■ 諸葛孔明の策を「天下三分」と呼んでもいいのか?
諸葛孔明の策を「天下三分」と呼んでもいいのか?
孔明が劉備(玄徳)に授けた策は、「草蘆対」とも呼ばれ、「天下三分の計」とよく同一視される。
いま曹操はすでに100万の兵を擁し、天子(皇帝)を差し挟んで諸侯に命令を発しています。これは正面から戦える相手ではありません。孫権は江東を支配して、すでに三代を経ており、国は長江の険を持ち、民は懐き賢才が手足となっているので、これは味方とすべきです。(「三国志」諸葛亮伝より。参考:「『三国志』の政治と思想」渡邉義浩著、講談社)
荊州と益州をともに領有し、その要害を保ち、西方の諸民族を手懐け、南方の諸民族を慰撫して、外では孫権と有効を結び、内では整った政治を行う。そして天下に変事が起こった際に、劉備(玄徳)自ら益州の兵を率いて出撃すれば、民は劉備(玄徳)を歓迎するだろう。そうすれば、覇業は成って漢王朝は再興できる。これが孔明の唱えた「草蘆対」の戦略だ。
これを「天下三分の計」呼ぶには、少々違和感があるはずだ。確かに孫権を一時的に利用するが、天下の三分は漢王朝復興の手段にすぎず、目的ではない。しかも、歴史学者の視点で見ると、「草蘆対」は奇策どころかごく常識的な戦略だという。
華北を曹操が掌握し、長江下流域に孫権がいる以上、残った荊州と益州を拠点として、洛陽と長安を取ろうとするのは、他に選択肢が思い浮かばないほど、常識に沿った王道である。(引用元:『「三国志」の政治と思想』渡邉義浩著、講談社)
孔明の策は、創作の中の「天下三分の計」のイメージとは異なる、大胆さの少ない堅実な策だったのだ。
本当に「天下三分」を唱えたのは意外な人物
■ 本当に「天下三分」を唱えたのは意外な人物
本当に「天下三分」を唱えたのは意外な人物
一方、同書では「もうひとつの天下三分の計」にも言及している。当時の中国を三つの勢力に分割する戦略を立てた人物が、孔明以外にいたというのだ。
その意外な人物とは、孫権の軍師として知られる魯粛である。魯粛をはじめとする孫呉の陣営は、多くの三国志作品では地味な扱いで、受け身な印象を受ける。例えば、横山光輝「三国志」などでは、孫呉は諸葛孔明の戦略によって赤壁の戦いに引きずり込まれ、「天下三分」の一角を担わされることになっている。そうしたイメージに親しんでいる私たちからすると、この史実は非常に興味深い。
魯粛は、徐州臨淮郡の豪族出身で、若い頃は枠にとらわれない言動から「狂児」と呼ばれたという。周瑜に物資の支援をしたことがあり、そのときは二つ持っている倉の一つを惜しげもなく与えてしまった。
魯粛は孫策に一時仕えたことがあるが、重用されなかった。孫策が横死し、孫権が跡を継いだばかりの頃(紀元200年頃)、周瑜は孫権に、魯粛を用いるよう強く進言した。
孫権が魯粛に戦略をきいたところ、魯粛はこう答えたという。
曹操は強く、漢は復興できないので、将軍(孫権)は江東を拠点に三分された天下の一つを支配する状況を作り出し、皇帝を名乗ってから、天下が変わるのを待つべきです。(「三国志」魯粛伝)
こちらの方が、「天下三分の計」と呼ぶにふさわしいだろう。
孔明が劉備(玄徳)に進言した策をわかりやすく言うと、「まず天下を曹操・孫権・劉備(玄徳)で分け、孫権と連合して曹操を倒し、そののち孫権も倒して、漢朝を復興させるべきだ」というものだ。漢朝の復興が前提にあって、そのための一番現実的な筋道が天下三分だった。
それに比べて魯粛はどうか。主君の孫権に皇帝を名乗れ、といっている。この時、孫権は張昭や張紘らの補佐のもと、漢王朝を助けるという方針を固めていた。これは、当時の支配的な考えである儒教の教えに則った、常識的な考えだ。
しかし、魯粛はそう考えなかった。漢王朝の復興は、すでに現実的なものではない。漢の復興に見切りを付け、孫権の勢力を生き残らせるのを最優先するべきだ。そのための戦略が、魯粛が唱えた「天下三分の計」なのである。
儒教では主君への忠誠は第一である。名目的には、当時の群雄たちも漢の臣下なので、孫権もまた自然な考えで「漢王朝の復興」を大義名分としていた。
もちろん、漢王朝の復興が非現実的だと認識している知識人も多かったはずだが、それを無理だと断言し、孫権に皇帝を名乗るよう求めた魯粛の戦略は、相当に常識を超えたものだったといえる。
また、曹操・孫権に続く「第三の男」として劉備勢力を育てようとする、という戦略も大胆で独創的なものだ。
構想を唱えるだけでなく、実行した魯粛
■ 構想を唱えるだけでなく、実行した魯粛
構想を唱えるだけでなく、実行した魯粛
この献策から数年後の208年、赤壁の戦いの直前のことである。曹操が大軍を率いて南下してくるという状況下、孫呉の内部では降伏論が有力になっていた。そうした中、使者として劉備(玄徳)のもとに派遣された魯粛は、劉備(玄徳)や孔明と友好関係を結び、孫権との同盟を劉備に約束させた。
赤壁の戦いが、周瑜の指揮によって曹操の敗北に終わったことは言うまでもない。この勝利によって、孫呉の独立政権としての自立が確定する。
周瑜が若くして病没したあと、国家戦略を任されたのが魯粛だった。彼は、自分の唱えた「天下三分の計」を実現するため、劉備(玄徳)の荊州の領有を支援した。そして、「劉備(玄徳)が他に支配地を得るまで荊州を貸し与える」という変わった条件まで出して、孫権・劉備(玄徳)の同盟をまとめるのだ。
魯粛は、自分の唱えた「天下三分」を実現するために、孔明を支持して劉備(玄徳)と孫権を同盟させた。赤壁の戦いの後には荊州を劉備(玄徳)に貸し与え、孫呉の内部も納得させ、「天下三分」の基本形を作り上げたのである。創作の「三国志演義」では、優秀だがお人好しで、孔明の知略に翻弄される損な役回りとなっている。横山光輝の「三国志」でも同様で、上司の周瑜に叱られるシーンも多い。そんなキャラクターが、史実では知略と行動力に満ちた人物像なのだから面白い。
創作の三国志では、多くの場合諸葛孔明の戦略で「天下三分」が実現する。しかし、史実では「天下三分」をいち早く唱えたのは魯粛であり、それを実現するために計略をめぐらせ、実際に「天下三分」の状態をつくりあげたのである。「三国時代」をつくったのは、「三国志演義」では脇役にされてしまった魯粛の先見性と独創性だったのだ。

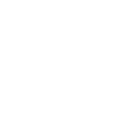
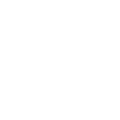
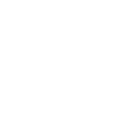





















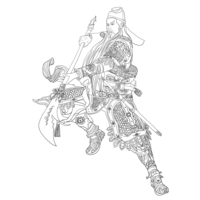


歴史好きフリーライター。史実解説・トリビアをメインに書いていきたいです。