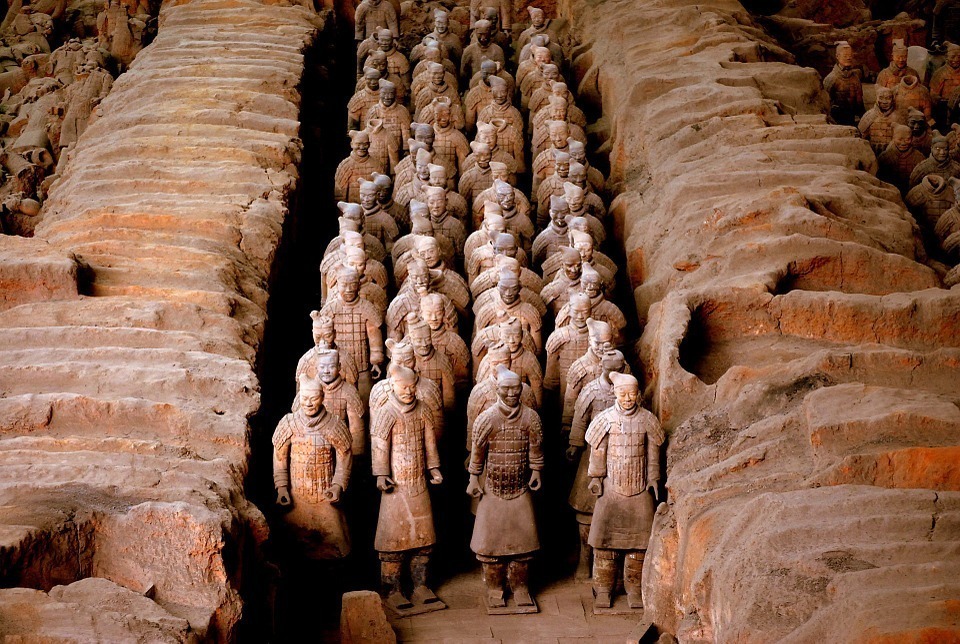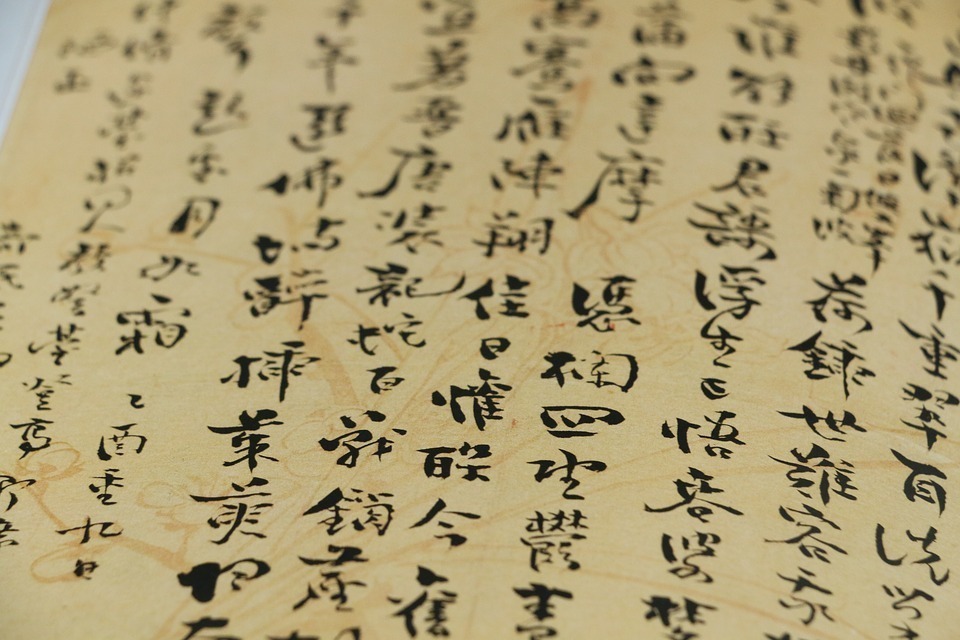戦いにいたる経緯
■ 戦いにいたる経緯
戦いにいたる経緯
208年におきた赤壁の戦いののち、魏と呉の南郡での戦いを横目に劉備(玄徳)は、荊州南部の4郡を支配することに成功します。
214年、呉は荊州の返還をもとめ、劉備(玄徳)配下の関羽軍と衝突。劉備(玄徳)もまた軍勢を動かし、蜀呉の全面対決の様相となります。
しかしここで互いに戦力を損耗しては魏に漁夫の利を与えることになる―そのことが両者の念頭にあり、蜀は関羽、呉は魯粛を派遣して会談を行います。互いに味方を連れ立つことなく刀一本のみ持して会談に赴いたことから、単刀赴会と呼ばれています。
時期を同じくして、曹操が漢中に攻め込む動きを見せたため、劉備(玄徳)は、「湘水で荊州を東西に分割し、江夏・長沙・桂陽を呉が、南郡・武陵・零陵を蜀が支配する」といった内容で和睦し転戦することを余儀なくされました。
呉にとってはひとまず半分の領土返還がなされた格好でしたが、荊州問題の清算ができたわけではなく、また関羽の強硬な対応からも後に禍根を残す決着となりました。
戦いの流れ
■ 戦いの流れ
戦いの流れ
2年後の217年、呉の外交官として蜀呉の荊州に関しつねに折衝にあたっていた魯粛が死去します。魯粛のあとをついだ呂蒙は、魏との戦いの前にまずは荊州の残り半分を蜀から取り戻して足がかりとするべきと主張します。
そのチャンスは、意外とはやく訪れます。
219年、折しも関羽は魏との戦い(樊城攻略)に注力をしており、于禁・龐徳を破り、樊城を包囲します。このとき、主力を率いての遠征であったため、呉への備えが手薄となっていました。
これを察知した呂蒙は、策を講じて荊州を攻略します。
商人に偽装した部隊が関羽の敷いた警戒網をかいくぐり、驚くべき速さで各地を押さえると、すぐさま善政をしき民心をつかむことに成功しています。
根拠地を失った関羽は、樊城をせめるどころではなくなります。
関羽軍の多くは荊州の人間ですから、荊州が呉のものとなれば関羽のもとでは戦いにくいのでしょう。配下の逃亡が相次ぎ、軍勢を減らしてしまった関羽は、魏の徐晃との野戦にもやぶれ、一時麦城に立てこもります。その後、劉備(玄徳)のいる益州方面へむけ逃げる途中で呉軍に捕らえられ、打ち首となりました。
呂蒙は、長年にわたる荊州問題を解決し、一世の英雄である関羽を討つという前人未到といってよい功績を手中におさめました。
呂蒙の人柄
■ 呂蒙の人柄
呂蒙の人柄
前半
■ 前半
前半
呂蒙とは、どんな人柄であったのでしょうか。
呂蒙は、他の将軍たとえば周瑜や魯粛、陸遜などとは比べようもないほどの貧しい生まれで、呉軍に参じたのも経済的な自立が目的だった節があります。
はじめ姉の夫である鄧当の軍に紛れ込んで鄧当と実母から激しく叱られるも、貧困から抜け出すためだと反論し、これには実母もおし黙るほかありませんでした。
若い頃は、血気盛んな無骨者といった感じで、鄧当の下に仕えていた役人に出自を嘲笑された際には、怒りのあまり斬り殺してしまうという事件も起こしています。
この事件はのちに当時の呉主・孫策の耳にも入り、孫策直々に呂蒙の人柄を検分するのですが、孫策は呂蒙にやどる豪傑の気迫を愛し、そのまま側近にとりたてています。
後半
■ 後半
後半
歴史のふしぎというか、ときに呂蒙のような貧しい家から異才が育つことがあります。
日本では羽柴秀吉の例があるように、三国志においては呂蒙がその好例といえます。
もともと、血の気が多く怒ると見境いがなくなる一面がありましたが、その後呂蒙は学問に目覚め、知勇兼備の将として開花しています。
黄祖との戦い、赤壁の大戦における烏林の戦いと大活躍した呂蒙。その傍ら、主君の孫権から学問の大切さを説かれています。
もともと性格は単純で素直だったのでしょう。学問を重ねてゆくと、半端な学者など及ばないほどの知性を備え、あの魯粛をして「呉下の阿蒙にあらず」(呉にいた蒙ちゃんではないね!)と賞賛されています。この呂蒙の変身ぶりは、日本においても
「男子三日会わざれば、刮目して見るべし」ということわざとなって今日も息づいています。
孫権の呂蒙評
■ 孫権の呂蒙評
孫権の呂蒙評
孫権は、呂蒙に学問をすすめ、呂蒙もまたこれに答えました。
もともと孫策は呂蒙の武勇を買ったのですが、孫権からみたばあい、いかにも猪武者にみえて頼りなかったのかもしれません。しかし、みごと孫権の期待に応え、呂蒙は著しい成長を見せます。主君からみてこれほど可愛げのあるやつも少なかったのではないかと考えられます。
孫権はいいます。
「人が成長して、ますます勤勉さを増すということにかけては、呂蒙・蒋欽に勝るものはおるまい。地位も名声も得てなお、学問に勤しみ、書物を愛し、財宝よりも義をあがめ、人々の手本となり、国にとって無二の存在となるとは、本当に素晴らしい臣下であることよ。」
関羽の呪いと呂蒙の死
■ 関羽の呪いと呂蒙の死
関羽の呪いと呂蒙の死
一世の英雄・関羽を鮮やかな知略で破った呂蒙ですが、その後病に倒れ、関羽と同年の年末に死去しています。
そのあまりのあっけなさからか、呂蒙は関羽の呪いのために死んだとの噂があがったのも無理はありません。
三国志演義では、戦勝の宴の最中、呂蒙が突然、孫権の胸ぐらを掴み、「碧眼の小児、わしが誰かわかるか…我こそは関羽雲長…死して呂蒙を道づれにせん!」
と叫び昏倒したあと、身体中の穴から血を吹き死んだとされています。
また、関羽の愛馬である赤兎馬も関羽のあとを慕うように死んでいます。
赤兎馬は、もと董卓の持ち馬で懐柔のため呂布に贈られたのでした。呂布討滅後は曹操が手に入れます。しかし気性が荒く誰も乗りこなせるものはいませんでした。
のち、一時的に曹操の客将となった関羽が赤兎馬を譲り受けていたものです。関羽は赤兎馬を乗りこなすことができました。
関羽の死後、赤兎馬は関羽を捕らえた馬忠に与えられるのですが、まぐさを食べなくなり死んだと伝えられています。
まとめ
■ まとめ
まとめ
今回は、呉の名将として名高い呂蒙についてまとめてみました。
武将としての勇猛さに加え、智謀も備えた呂蒙はまさに鬼に金棒。あの関羽をさえ上回る大きな存在となったものの、関羽の呪いのためか、あえなく最期を迎えてしまいます。
文字どおり呉の柱石となった呂蒙がその後生き続けたらどのような活躍を見せたのか、と考えるととても興味深いものがありますね。