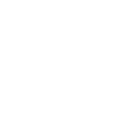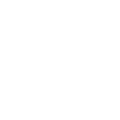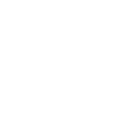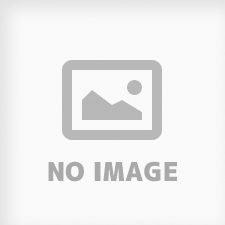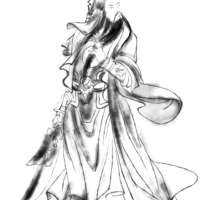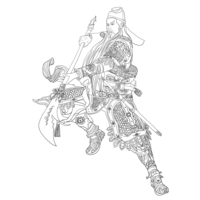修正を余儀なくされた天下三分の計
■ 修正を余儀なくされた天下三分の計
修正を余儀なくされた天下三分の計
諸葛亮(孔明)が考え出した天下三分の計。「三顧の礼」にて劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)が出会った当初の頃は「劉備(玄徳)が荊州を継承して地盤とする」という計画でした。しかし、実際には劉備(玄徳)が劉表(景升)から「継承」を受けることを渋り、その隙に曹操(孟徳)に荊州を取られてしまいました(蔡瑁が降伏してしまう)。要するに「天下三分の計は計画当初から頓挫」した訳です。もはや曹操軍に太刀打ちできる勢力は呉国のみ、ここで呉国が荊州と同様に降伏してしまえば万事休すです。諸葛亮(孔明)は天下三分の計実行のために「曹操軍と呉を戦わせる」という難題に取り組みます。
開戦か降伏か 国論が二分されていた呉国
■ 開戦か降伏か 国論が二分されていた呉国
開戦か降伏か 国論が二分されていた呉国
曹操(孟徳)南征軍の進撃に呉国も騒然とします。開戦か降伏かで国論が二分されてしまいます。これには孫権(仲謀)も悩んでしまい、国論はますます割れるばかり。それは国主が孫策(伯符)から孫権(仲謀)に代わって以来、長く平和が続いていたことも一因で「平和慣れしてしまっている呉軍が実践を重ねている曹操軍に勝てるはずがない」というのが「降伏派」の言い分でした。
そこで、孫権(仲謀)は「曹操軍と長く戦っている劉備軍の様子を探るように」と江夏・夏口に魯粛(子敬)を派遣します。この状況下で意外にも「先に動いた」のは呉国側だったのです。
諸葛亮(孔明) 単身で呉国に行く
■ 諸葛亮(孔明) 単身で呉国に行く
諸葛亮(孔明) 単身で呉国に行く
魯粛(子敬)は劉備(玄徳)から曹操軍の現状を聞き出そうとしますが、劉備(玄徳)は「逃げ回ってばかりいますから」と言ってなんやかんやとしっかりした情報を伝えません。これは諸葛亮(孔明)の入れ知恵で、「呉国に曹操軍の情報を伝えないことで、不安を煽らせる」という狙いがあったのです。加えて魯粛(子敬)は「開戦か降伏か」で国論が二分されていることを劉備(玄徳)に伝えます。それを聞いた諸葛亮(孔明)は、「降伏論者を説き伏せなければ」と劉備(玄徳)の反対を押し切って呉国を訪れる決意をします。表向きは「侵略者曹操から国主孫権および中国を守る」でしたが、実際には「呉と曹操を戦わせなければ、天下三分の計が無になる」ばかりでなく「劉備(玄徳)一族の滅亡」になるからです。諸葛亮(孔明)も「背に腹は代えられぬ」状況だったのです。
諸葛亮(孔明)の大論陣 さながら武器を持たない戦い
■ 諸葛亮(孔明)の大論陣 さながら武器を持たない戦い
諸葛亮(孔明)の大論陣 さながら武器を持たない戦い
呉国を訪れた諸葛亮(孔明)を待ち構えていたのは降伏論を唱える文官たちでした。しかも大勢。諸葛亮(孔明)はこれら文官たちと一人でやり合わなければなりません。諸葛亮(孔明)が一人にでも言い負ければ、それは「天下三分の計の敗北」「劉備(玄徳)一族の敗北」につながります。孔明にとっては「背水の陣」です。
張昭(子布)をはじめとした文官たちが諸葛亮(孔明)に襲い掛かります。
◆劉備(玄徳)は荊州で敗れ江夏に敗走した。
◆百万の曹操軍に勝てる筈がない。
◆曹操(孟徳)が逆賊だと言うのならば、過去に国を打ち立てた人物はすべて逆賊になってしまう。
(なので、曹操(孟徳)は逆賊ではないのだから、彼に服することは正しい)
これらに諸葛亮(孔明)はことごとく反論します。
●我が殿(劉備)は敗走した訳ではなく、荊州の民衆を守るために行動している。しかし不幸にも荊州は降伏し、圧倒的少数の勢力で「戦いながら引いている」のである。現状の勢力で総攻撃などすれば、それこそ破滅してしまう。現状を正しく見極めず局部的な判断で破滅の道を選ぶ事こそ大局を見ていない証拠である。
●百万と言っても半数以上は旧袁紹軍の兵と荊州兵で曹操(孟徳)への忠誠など中途半端。なのに、3代の長きに渡って呉国には忠臣が揃っているはず。にもかかわらず「数」に恐れ主君に降伏を勧めるなど卑怯千万!
●曹操(孟徳は漢から禄を受けているにもかかわらず、今は漢朝をないがしろにしている。これを逆賊と言わずして何であろう。あなた(呉の文官)は呉から禄を受けていようが、主君孫権(仲謀)の力が弱くなったら、曹操(孟徳)のように主君をないがしろにするのか。
諸葛亮(孔明)。すごいですね。
結局、呉の文官たちは全員黙ってしまいます。論戦は諸葛亮(孔明)の勝ちとなりました。
そして、呉水軍大都督 周瑜(公瑾)との会談へ
■ そして、呉水軍大都督 周瑜(公瑾)との会談へ
そして、呉水軍大都督 周瑜(公瑾)との会談へ
「都督」とは軍司令官の意。周瑜(公瑾)は呉水軍の最高司令官の立場にいて、曹操軍との戦いにおいて、大きな裁量権を持っていました。しかし、周瑜(公瑾)の考えは微妙でした。「どちらかと言えば降伏」という感じです。総司令官までもがこのような曖昧さですから、国論が二分されても無理はありません。
魯粛(子敬)が開戦論を展開しますが、周瑜(公瑾)はイマイチ乗り気ではありません。
そこに、諸葛亮(孔明)が割って入ります。しかし、文官たちと話した時とは一転、今度は降伏論を擁護し始めます。現状の兵力差を見れば降伏論を検討するのが普通。下手に戦って民衆を戦渦に巻き込んで敗れ、主君をより不利な立場に追い込むよりは降伏する方が利口であると諸葛亮(孔明)は言います。それに頷く周瑜(公瑾)。
魯粛(子敬)は驚きと戸惑いの眼差しで孔明を見ます。さっきの文官たちへの熱弁は何だったのか。その場が何となく降伏論へ傾きます。
しかしその時、諸葛亮(孔明)がこう続けます。「降伏もせず、戦いもせず曹操軍を撤退させる方法があります。」
周瑜(公瑾)も魯粛(子敬)も驚いて諸葛亮(孔明)の言葉に耳を傾けます。彼の話はこうでした。
呉国に在住する大喬、小喬の美人姉妹を曹操(孟徳)に差し出せば、曹操(孟徳)は喜んで軍を撤退させて本国へ戻るでしょう。
周瑜(公瑾)は信じませんが、諸葛亮(孔明)はさらに続けます。曹操(孟徳)は天下統一後の余生の楽しみをひとつの詩にしている。それは次のような詩で北方では有名である。
「二喬を東南よりとりて 朝夕楽しみて共にせん」
要は「晩年は大喬、小喬とともに過ごし、余生を楽しみたい」と公に詩に歌っているのです。呉国など当然平定しているというのが前提のこの詩。
これに周瑜(公瑾)は激怒します。詩の内容が、あまりにも呉国をないがしろにしていることも一因ですが、小喬とは周瑜(公瑾)の奥様だったからです。ちなみに大喬は孫策(伯符)の奥様。「我が妻を曹操(孟徳)ごとき下輩に差し出せるか!」と言って一転、開戦を決断します。即決です!
まとめ
■ まとめ
まとめ
大都督周瑜(公瑾)の意見は大きな影響力を持ち、開戦か降伏かで悩んでいた主君孫権(仲謀)をも説得してしまいます。これにて開戦決定。孫権(仲謀)は張昭(子布)をはじめとした文官たちも呼び、公の場で開戦を宣言します。
それにしても、「開戦の決め手」が周瑜(公瑾)の奥様(小喬)だったとは意外です。歴史なんて案外そんなことの繰返しなのかも知れません。