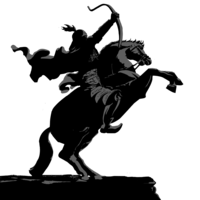「曹操(孟徳)」という人物
■ 「曹操(孟徳)」という人物
「曹操(孟徳)」という人物
三国志を語る上で曹操(孟徳)という人物は欠かせません。魏という大国を率いており、勇猛さや知勇はもちろんのことですが、その人の器の大きさから多くの優秀な武将が魏に集まってきました。三国志の中でも最高に優秀な人材であり、人の前に立つべき立派な人でした。最後の最後まで周辺の国の人々を怯えさせ、天下統一を目指し続けた人です。
そんな周辺の武将がおののいた曹操でも一切歯向かわずに言うことを聞いていた人物がいます。それは彼の妻、丁夫人です。周りを圧倒するような威圧を放っていながらも嫁には頭が上がらなかったようです。
第一夫人、第二夫人の存在
■ 第一夫人、第二夫人の存在
第一夫人、第二夫人の存在
第一夫人は丁夫人でしたが、名家育ちでありお嬢様育ちであったため気が強い性格だったと言われています。そのため曹操も逆らうことができず、戦場ではエリートだった曹操も家では頭が上がらなかったようです。さらに曹操には第二夫人がいたようですが、丁夫人にひどくいじめられていたようです。そんな丁夫人にしびれを切らしたのか曹操は不倫に走ってしまいます。
曹操は現在の河南省周辺を領土としていた張繍に奇襲をかけます。この結果、降伏させることができたのですが、その勢いで張繍の兄の嫁である雛氏と不倫の恋を始めてしまいます。
ここから曹操の悲惨な恋愛が始まります。浮き足立っていた曹操に激怒した張繍が奇襲をかけます。ここで油断していた曹操はボロボロにされてしまい、曹操の代わりに息子である曹昴が身代わりとなり、戦死してしまいます。
おそらく、曹操が年齢的にも一番充実していた時期でもあったため、なんでもできる気がしていたところに落ちた天罰とも言えるでしょう。
不倫をしてしまった曹操のその後
■ 不倫をしてしまった曹操のその後
不倫をしてしまった曹操のその後
ボロボロになり、息子を戦死させてしまった曹操は命からがら自分の都に帰ることに成功します。しかし、そこで待っていたのは自分の第一夫人である丁婦人からの怒号でした。もちろん、丁夫人は不倫された上に自分の愛する息子を戦死させた自分の夫を許すわけはありません。
罵りの声が絶えることはなく、「私の大切な息子を戦死させて、よくそんな平気な顔でいられるわね。」とことあるごとに責め立てます。この怨念は常に曹操に向けて発せられて、最初は我慢していた曹操も我慢の限界を迎えてしまいます。
そこで曹操は常に発奮している丁夫人を実家に返しました。実家に返し、ほとぼりが冷めるまで様子を見ようというのが曹操の考えだったと思います。この頃の豪族の家では男性と女性が居住するスペースも分けられており、丁夫人が不倫をするというリスクもありませんでした。
そして、丁夫人の機嫌が直ったと思った際には、実家に様子を見に行くという行動を繰り返していました。そして、丁夫人の機嫌が直るまで通い続けたと言われています。
許されなかった曹操
■ 許されなかった曹操
許されなかった曹操
丁夫人の機嫌を取るために、丁夫人がいる実家に通い続けた曹操ですがその思い通じることはありませんでした。実家に戻った丁夫人は常に自分の仕事を行い続けます。丁夫人は毎晩のように機織りを行っていました。乱世で荒れていた世界ではこの機織りの音はとても綺麗で美しい音色を響かせていたと言われています。そんな綺麗な音を響かせていた丁夫人ですが心の中は濁っていたようです。
曹操は丁夫人の様子を見にいつもどおり、訪れますが丁夫人は曹操の方に振り返ることもせずに機織りを行っています。曹操も耐えられなくなり、「そろそろ一緒に帰ろう」と伝えますが、丁夫人は一切振り向かずに手を休めることなく、カタンコトンと機織りを行っています。一切曹操に応じることなく接していると、「まだ許してくれないのか」と曹操もしびれを切らします。ここで丁夫人と曹操の正式な別れを遂げることになります。
戦場ではどんな状況でも恐れず、誰にも媚びずに生きてきた男ですが、第一夫人である丁夫人には最後まで頭が上がらなかったようです。
丁夫人のその後
■ 丁夫人のその後
丁夫人のその後
こうして、曹操と丁夫人の愛の物語は終えることになりましたが、実はこの裏でもう一つの物語がありました。それは第一夫人であった丁夫人と第二夫人の友情による物語です。
丁夫人が曹操と離婚すると、第二夫人が繰り上げで正妻になったわけですが、第二夫人は丁夫人を曹操が不在の際に屋敷に呼び入れて二人でお茶をしたりしていました。いじめられていたのにも関わらず、こういった女性同士で友情を築き上げることができたのは第二夫人が寛容であり、丁夫人を人として好んでいたからだと言われています。
また、第二夫人は四季折々で丁夫人に贈り物を行ったり、曹操に関する助言を聞きたいということで相談を丁夫人にしたりなどして信頼をしていました。
そんな第二夫人に対して最初は怪しがっていた丁夫人ですが、そのうちに心を開き女性同士での交際がスタートします。決して同性同士の恋愛が許されていなかった時代でもないため、こういった結末を迎えるのも珍しくはありませんでした。三国志の世界の女性も男性に負けず、自分の意志道理に進んでいくという強気な女性が多かったようです。
最後までめそめそしていた曹操
■ 最後までめそめそしていた曹操
最後までめそめそしていた曹操
丁夫人と第二夫人と最後まで仲睦まじく生活していきました。ある意味で曹操がきっかけで二人が出会い、最高の友情を手にしたのであれば、曹操のお手柄といっても過言ではないかと思います。その絆は丁夫人がなくなるまで続いていきました。
丁夫人がなくなった際には曹操に告げて、首都の郊外に立派な墓を建てました。それほど第二夫人にとって、丁夫人は仲の良い人でした。
一方で曹操は最後まで丁夫人に未練を持ち続けており、いつまでもめそめそしていたそうです。終いには、「あの世で曹昴にお母さんはどこと聞かれた際に、なんて答えればよいのだろう。」と言っていたようです。
才能や武勇に長けていたにも関わらず、天下もとれずに嫁も失って、欲しいものは何も手に入らずに亡くなっていった曹操でした。
まとめ
■ まとめ
まとめ
今回は魏の歴史には欠かせない人物である曹操(孟徳)のプライベートな話を紹介しましたが、曹操の歴史はいい評判ばかり聞くような武将ですが、そんな曹操にも悪い噂はやはりあったようです。どんなに優れている人物でも欠点というものはやはり持っているようです。