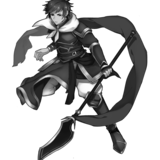魏を打倒というよりも、長安を落としたかった
■ 魏を打倒というよりも、長安を落としたかった
魏を打倒というよりも、長安を落としたかった
近年の研究ではこれが叫ばれています。いきなり魏を打倒するのではなく、まずは長安を落とす。長安とは現代の西安になるのですが、三国時代に於いてはいわば首都クラスの大都市。ここを落とせば三国のバランスを大きく崩せると考えた部分もあるでしょう。
そもそも「三国志」とは銘打たれているものの、実際の国力では魏が圧倒的でした。国土面積だけを見ても魏が一番広大な面積を保有しているのが分かるのですが、面積以上に大きな差となっていたのが国力、つまりは経済力です。
蜀が収めていた成都はいわばまだまだそこまで発展していた訳ではありませんでした。更に蜀は山岳地帯も多く、面積の割にはそこまで経済的な発展がなかったのです。
そのため、国力の差は如何ともしがたいものがありました。ガップリ四つに組んでは魏にかなわないことくらいは聡明な諸葛亮孔明のこと、重々承知していたでしょう。
そこでまずは長安を落とすことにより大都市を奪取。それにより、経済的なミリタリーバランスを崩す狙いがあったのでしょう。もしもですが、蜀が長安を落としていれば長安という大都市の経済力が蜀に属することになりますので魏とも互角に戦えるだけの戦力を整えられたでしょう。
たらればを言い出したらキリがないのですが、諸葛亮孔明は長安さえ落とせば何とかなると考えていた節もあります。都でもありますので、ただ単に領地を増やすだけではなく「魏の大都市を落とした」と大々的にアピールすることで魏の兵士たちの士気を落としたり、呉に対してのアピールになることも考えていたはずです。
また、蜀の領土でもある漢中からはそこまで遠くはありません。補給等を考えると長安を落とすのはある意味で現実的な路線でもあります。国力を考えると北伐はしばし夢物語かのように思われがちですが、距離やその後の展開を考えると十分に現実的なものです。
攻められるよりも攻める
■ 攻められるよりも攻める
攻められるよりも攻める
これも大きかったのではないでしょうか。蜀は山岳地帯ですので守るにはうってつけでした。実際、蜀滅亡時には諸葛亮孔明の意思を継いだ姜維が剣閣に籠って奮戦。成都が落ちても尚、抵抗を続けられたのも天然の要害があったからこそ。
つまり、攻められれば勝てたでしょう。ですが攻められるとなるとどのように攻められるのか分かりません。ましてや当時の戦争は近現代のように宣戦布告などありません。いわばすべてが奇襲。いつ攻められるのか分からないので攻められたら常に不意打ちのような状況だったのです。
いくら天然の要害に恵まれているとはいえ、圧倒的な物量を誇る魏に攻められてしまったら状況を覆すのはなかなか簡単ではありません。
そもそも攻められるともなればどこから攻められるのか分かりません。守備の兵士をどこに配置するのか。国力に劣る蜀は兵士を分散させては防御も弱くなりますので兵士を分散して守りを固めるより、攻めに転じることで兵士をより集中させることも出来るのです。
それだけに、攻められるよりも先に攻めることで自分たちが有利な状況を作りたかったのかもしれません。攻めた方が先手を打てます。陣や補給線の確保等を考えた時、攻めた方が有利だと考えたのでしょう。
勝つ自信があった
■ 勝つ自信があった
勝つ自信があった
実際の所、これもあるでしょう。諸葛亮孔明は北伐を数度に渡って行っているのですが、諸葛亮孔明自身、無謀なことを行うタイプの人間ではありません。
勝算があったからこそ戦を仕掛けているのです。実際には勝利を収めることは出来ませんでしたが、実際に敗北したのは一度のみで、後は馬謖の話に代表されるように、何らかのミスによって成功が手から逃げていったのであって、馬謖をはじめ配下たちがすべていう事を聞いていれば案外あっさりと北伐は完了していたかもしれません。
いくら諸葛亮孔明でも配下が勝手に行動しては計画通りには行きませんが、計画段階だけであれば自信があったからこそ戦を仕掛けていたのかもしれません。
そもそも負けるだろうと思って戦を仕掛ける人間はいません。「イチかバチか」で戦を仕掛けるケースもあるでしょう。
ですが蜀の国力等を考えた時、博打を仕掛けるのはリスクが高すぎます。つまりは諸葛亮孔明は結果だけを見れば北伐に何度も失敗していますが、勝つ自信があったからこその北伐だったのでしょう。
また、先にも話したように長安を落としさえすれば…との思いもあったでしょう。魏を滅ぼす自信があったのかは定かではありませんが、長安を落とす自信はあったのではないでしょうか。
劉禅に危機感を促す意味もあった
■ 劉禅に危機感を促す意味もあった
劉禅に危機感を促す意味もあった
これがすべてではないとは思いますが、理由のうちの何割かにはあったのではないでしょうか。
劉禅と言えば三国志の英雄を祭る武候嗣にさえ祭られていない程の暗愚な人間であったのは三国志マニアであれば誰もがご存知でしょう。趙雲が命がけで救った阿斗があのような大人になってしまったのは何とも言えない話ですが、自分自身何度も何度も戦を経験しただけではなく、実際に戦場に赴いて戦の苦労や悲惨さを知っている父・劉備(玄徳)に対し、息子の劉禅は大切に育てられたがためにほとんど戦を知りませんでした。
そのため、劉禅に対して「決して平和ではない」とアピールしたかった狙いもあるのかもしれません。
もしもです。戦を知らないだけではなく、戦そのものが起きていないともなれば三国鼎立の状況であれ「平和だ」と感じるでしょう。「今のままで十分だろう」と錯覚してしまうリスクも十分に考えられます。
ですが北伐を繰り返すことによって「平和じゃないんだぞ」と暗に戦を知らない皇帝に対してアピールする狙いもあったのかもしれません。
結果だけを見れば残念ながらその願いは叶わないものになってしまいましたが…。
まとめ
■ まとめ
まとめ
いくつか考えられる理由を挙げてみましたが、極論すればその理由は諸葛亮本人に聞かなければ分かりません。
北伐は三国志のいわば「最後のドラマ」と言っても過言ではありません。勝利出来なかったからこそ、いわゆる判官贔屓で蜀の人気が高い部分もあります。
考え方は様々ですし、他にも考えられる理由はあるでしょう。それらをいろいろと想像してみるのもまた、三国志の楽しみ方なのかもしれませんね。