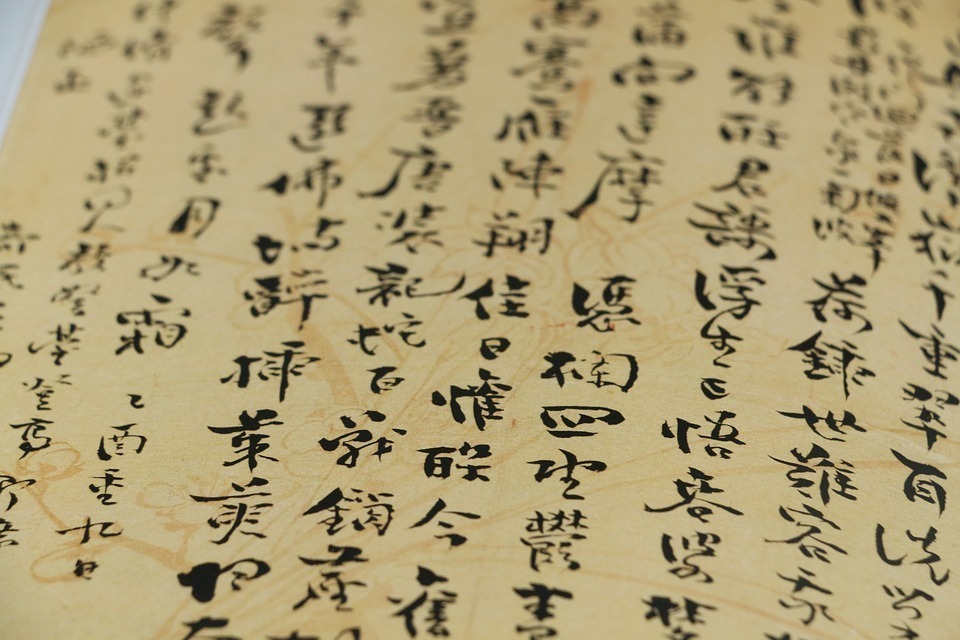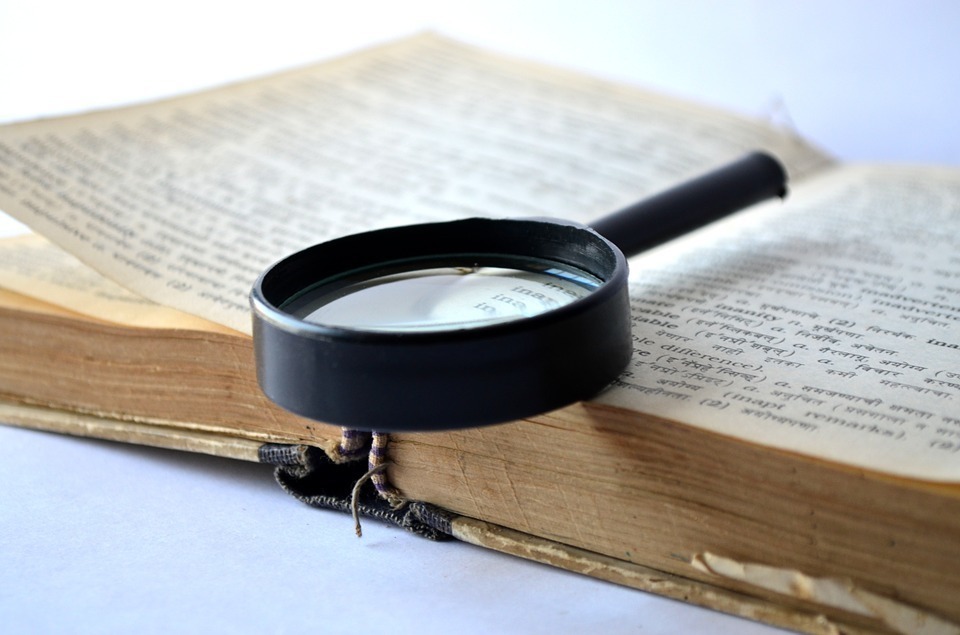三国志に登場する個性的な面々
■ 三国志に登場する個性的な面々
三国志に登場する個性的な面々
三国志が現代でも引き続き大人気である理由のひとつに、たくさんの個性豊かなキャラクターたちが登場することがあげられるでしょう。
とてつもない野心をもった者、武勇が飛び抜けて優れた者、すぐに他人を裏切る者、最期まで忠義を尽くす者、深い智謀の持ち主、仁徳に優れた英雄、酒好きもいれば、無類の女好きもいます。それらが時に激突して伝説的な場面を作り上げ、時に人間臭さを演出します。強烈な個性がぶつかり合い、絡み合うのが三国志の魅力なのです。
中でもその個性が変人の域にまで達している人物もいました。それが今回紹介する「禰衡」です。わずかな登場シーンながら、その言動は強烈なインパクトを三国志読者に与えています。
禰衡の個性「瞬間記憶能力」
■ 禰衡の個性「瞬間記憶能力」
禰衡の個性「瞬間記憶能力」
禰衡、字は正平といいます。青州の平原郡の生まれで、同じく青州出身である名士・孔融に高い評価を受けていました。孔融が驚いたのはその頭脳です。学問・文学に精通しているだけでなく、禰衡は「一度目にした文章を忘れることのない」という能力を持っていました。現代でいうところの「瞬間記憶能力」というものではないでしょうか。もしかすると禰衡はあらゆる古書を記憶していた可能性があります。
これが事実だとすると、この時点ですでに三国志の登場人物の中でも屈指の特殊能力者のひとりですね。曹操に匹敵する才能の持ち主だった可能性すらあります。
身分にかかわりなく、高い能力を持っている者であれば登用してきた曹操にしてみれば、実に興味を惹かれる人材だったのではないでしょうか。
しかし禰衡を有名にし、全土にその名前を知らしめたのはもうひとつの個性でした。
禰衡の個性「超毒舌」
■ 禰衡の個性「超毒舌」
禰衡の個性「超毒舌」
現代の日本の芸能界を見ても、「毒舌」で知られ、人気を誇るタレントは複数います。毒舌家は、通常の人であれば言葉にすることをためらわれる他人の欠点や特徴を、本人に向けて真正面からぶつけていきます。単なる悪口で終わらないのは、その発言が正確な評価でもあるからでしょう。
三国志に登場する人物の中で、もっとも辛口なのがこの禰衡です。超毒舌家として恐れられていました。何せ献帝を擁して朝廷を牛耳っていた曹操に対しても歯に衣を着せぬ物言いなのです。権力者に逆らうということは、自身が処刑されるどころか、九族皆殺しにされてもおかしくない話です。
実際に曹操は無礼な禰衡を処刑しようとも思いましたが、ここは懐の広いところを見せるためにグッと我慢をし、都から追い出すだけにしています。その指摘がある程度的を得ていたからかもしれませんね。
禰衡の毒舌集「曹操の家臣編」
■ 禰衡の毒舌集「曹操の家臣編」
禰衡の毒舌集「曹操の家臣編」
それでは禰衡の毒舌ぶりを確認していきましょう。独特の表現で他人をこけおろしています。
●「私にとっての張良」だと曹操から高評価を得ていた荀彧に対し、禰衡は「荀彧にもっとも似合っているのは葬式の弔問役だ」と評しています。つまり立派なのは容姿や作法だけということです。
●郭嘉は、「私を理解できるのは郭嘉だけだ」と曹操に評価されていましたが、禰衡にかかると「眠れない時にちょうどいい。郭嘉に本を朗読させると眠くなる。格好の子守役だ」と評されています。それだけ無駄に難解な書物を読んでいたということをいいたいのでしょう。
●曹操の留守を呂布から守り抜いた程昱は「郭嘉の書物を収めた書庫の番人だ」と評されています。守らせることだけはしっかりやりぬくということでしょうか。
●さらに軍師役の荀攸は「墓守」、武勇に優れた于禁は「左官屋」徐晃は「屠殺業者」といった扱いです。戦場で指揮をする立場である以上、「死」は常につきまといますが、そのシーンだけしか活躍場所がないということをいいたいのでしょうか。お金に強い執着心を示す曹洪は「銭取り太守」、呂布との戦いで片目を失った夏候惇は「五体満足将軍」、猛将として恐れられる許褚は「牛飼いの番人」、張遼は「太鼓叩き役」と酷評されています。
禰衡の毒舌集「曹操編」
■ 禰衡の毒舌集「曹操編」
禰衡の毒舌集「曹操編」
曹操に対しても禰衡の姿勢は変わりません。屋敷に呼ばれた際には、門の外に座り込み曹操の罵詈雑言を並び立てました。曹操が出てくると「人のふりをしているが人ではないものに会うのだから、礼法など必要ない」と吐き捨てるように言い放っています。
あの曹操に正面から毒舌を浴びせたことで、禰衡の名前は後世まで語り継がれることになり、この場面は京劇の演目にすらなっています。権力に屈せず、毒舌で曹操に対抗した人物として、禰衡は未だに中国では人気があるのです。
曹操は禰衡をひっ捕らえ、荊州の劉表のもとへと追いやりました。劉表に対してはやや大人しめだった禰衡ですが、その家臣たちはやはり毒舌の餌食となってしまいます。憎しみが募っていき、憤慨した黄祖によって処刑されてしまうのです。
まとめ・そんな禰衡の高評価を受けた二人
■ まとめ・そんな禰衡の高評価を受けた二人
まとめ・そんな禰衡の高評価を受けた二人
しかし禰衡は誰かれ構わず口撃したわけではありません。高く評価した人物が二人いました。それが面識もあった名士・孔融と、まったく面識もない若い楊脩です。孔融が楊脩の書いた文章に感動し、写していったのを禰衡が見たのだといいます。その文章を見ただけで、禰衡は楊脩を有能な人物だと認めました。
楊脩はそれに対して特に反応を示していませんが、父親である楊彪はかなり警戒しています。口は災いのもとであることを知っていましたし、周囲から憎まれている禰衡に高く評価されたということは、その憎しみの矛先が我が子に向く恐れがあったからです。
やがて楊彪の不安は的中することになります。禰衡が処刑された10年後、禰衡と互いにリスペクトし合っていた孔融もまた曹操の命令によって処刑されてしまうのです。さらにその10年後に楊脩が曹操の命令で処刑されました。
ちなみに孔融は曹操を誹謗中傷した罪によって妻子ともども殺されています。楊脩は劉備(玄徳)との漢中を巡る戦いに際し、曹操が発した「鶏肋」という言葉に敏感に反応して命令違反の罪を着せられています。楊脩が後継者争いで曹植派であったことも曹操に警戒された理由とされています。
こうして禰衡をはじめ、禰衡から高評価された二人も無残な死を遂げることになるのです。その背景には禰衡に対する曹操の憎しみのようなものも感じられますね。