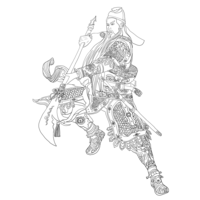蔡邕(さいよう)の祖先と娘
■ 蔡邕(さいよう)の祖先と娘
蔡邕(さいよう)の祖先と娘
周の文王を祖とし、蔡国の初代国王となったのが蔡仲(蔡胡)です。その子孫が「蔡邕」となります。蔡邕は陳留郡の生まれで、字は「伯喈」。祖父は県長を務めましたが、父は官途につかなかったそうです。
曹操がその暗記力に感嘆したと伝わる「蔡琰」は蔡邕の娘です。蔡琰は父親譲りの芸術肌で、幼い頃から、演奏中に切れた琴の絃を聞いていただけで当てることができたそうです。
ちなみに蔡邕・蔡琰の祖先には蔡勲という県令を務めた人物もいましたが、前漢を滅ぼした王莽に反発して隠棲しています。正道を貫く血を蔡邕は受け継いでいるのです。
橋玄(きょうげん)との出会い
■ 橋玄(きょうげん)との出会い
橋玄(きょうげん)との出会い
若い頃の蔡邕の名を広く知らしめたのが、母の死に対して「三年の喪」を実際に行ったことでした。母の墓の近くに小屋を建て、ひたすら喪に服したのです。これを実際に実行できる者は少なく、その孝の篤さが評判となりました。
やがて蔡邕は都・洛陽に上り、数学や天文などの学術、さらには琴などの音楽を学びます。その後は帰郷しひっそりと暮らしていたのですが、霊帝の治世となっていた171年に司徒府に招聘されます。声をかけたのは文武両道の名士である「橋玄」でした。あらゆる分野に精通する能力を持ちながら、清廉潔白を貫く橋玄の姿に蔡邕は憧れを抱くようになりました。蔡邕が30代後半のことです。
宦官との確執
■ 宦官との確執
宦官との確執
175年以降から後漢王朝は天災に見舞われることになります。洪水、旱害、蝗害、地震と相次ぎました。政の在り方に原因があるのではないかと考えた霊帝は六経(礼経・易経・書経・詩経・春秋・楽経)に精通している蔡邕に対し、政策の失策を指摘するように命じます。蔡邕は素直に汚職のある官吏の実名を記入しました。それを宦官の曹節が先に確認し、怒りを感じた宦官たちが霊帝に蔡邕の非を諫言します。その諫言を信じた霊帝は蔡邕を捕らえ、流刑としました。行き先は幷州の五原郡です。
宦官は暗殺を謀りましたが、追っ手は蔡邕の清廉さを知っていたので殺すことをしませんでした。県令たちも蔡邕を暗殺するように命じられましたが、むしろ蔡邕を気遣い、毒殺される可能性があることを告げ、警告したといいます。
12年間の逃避生活
■ 12年間の逃避生活
12年間の逃避生活
すぐに蔡邕の罪は許され、都に戻ることができるようになりましたが、宦官らの陰謀によって暗殺されることを恐れ、蔡邕は家族と共に南へと逃げます。長江を渡り、呉郡や会稽郡で生活していたようです。
もし宦官が権力を握る政治が続いていたら、蔡邕が都に戻ることはなかったでしょう。しかし朝廷が大きく揺らぐ事件が起こります。外戚である大将軍の何進と宦官らの軍事衝突です。何進は宦官らによって暗殺されましたが、何進派の武官らがその報復に宦官を皆殺しにしたのです。武官のリーダー格が袁紹でした。
ただ、この混乱を鎮めたのは少帝を保護した董卓だったのです。董卓は何進の兵力を吸収し、武力をもって朝廷を牛耳ることになります。そして暴虐の限りを尽くしました。
董卓に招かれる
■ 董卓に招かれる
董卓に招かれる
189年、蔡邕の清廉潔白ぶりを聞いた董卓は、蔡邕を脅して無理やり司空府に招聘しました。蔡邕に面会したとき董卓は驚くほど鄭重だったといいます。董卓は蔡邕を重用し、祭酒に任じ、さらに尚書、そして侍中へと瞬く間に昇進させていきました。董卓は蔡邕の誠実さを信じたのです。だからこそ蔡邕の助言には比較的素直に耳を傾けたと伝わっています。
なぜ正道を貫く蔡邕が悪名高き董卓に仕え続けたのでしょうか?
誰の指示にも従わず、慣例を破壊し、逆らう者を虐殺していく董卓を導くことのできる可能性のある者が、蔡邕だけだったからではないでしょうか。もしかすると董卓は長安に遷都した後、帝位の禅譲を画策していたかもしれません。その蛮行をなんとか思いとどまらせることができたのが蔡邕だったのではないでしょうか。
董卓にとって蔡邕は師のような存在だったのかもしれません。
後漢王朝を守るために蔡邕は朝廷に残り、最後まで董卓を相手にしたのではないでしょうか。
王允によって捕らえられる
■ 王允によって捕らえられる
王允によって捕らえられる
蔡邕の助言によって命を救われた人物に劉備(玄徳)の師である盧植がいます。盧植は尚書として朝廷にあり、董卓が少帝を廃してその異母弟を皇帝に据えようとしたことに真っ向から異議を唱え、董卓に処刑されそうになります。このとき取り成したのが蔡邕でした。
さらに朝廷から発せられる草稿はすべて蔡邕の手によるものだったといいます。それだけ董卓の信頼を得ていたわけです。
そんな中、裏では着々と董卓暗殺計画が練られていました。首謀者は司徒・王允、罷免されていた元太尉・楊彪、そして三国志最強の武を誇る呂布らです。192年4月にその計画は実行に移されます。董卓は呂布の寝返りによって討たれることになるのです。
董卓が討たれたという報告はすぐに朝廷の内外に広まり、多くの人たちが歓喜しました。しかし蔡邕だけは暗い表情でため息をついていたといいます。それを見ていた司徒・王允は怒り、蔡邕を獄にくだします。
王允は、史書を編纂する役目にあった蔡邕に悪く書かれることを恐れたからだともいわれています。
太尉の馬日磾などはすぐに蔡邕の釈放を願い出ましたが、王允は決して許しませんでした。蔡邕も獄中で謝罪したそうですが、王允は受け入れていません。そして蔡邕は処刑されます。王允はこれによって大きく人望を失い、その後、董卓の残党の再起を抑えきれずに殺されてしまいます。
まとめ・董卓からの解放
■ まとめ・董卓からの解放
まとめ・董卓からの解放
王允は董卓の重用を受ける蔡邕に嫉妬していたのかもしれません。または、蔡邕は董卓に肩入れする逆賊という敵愾心が日頃からあったのかもしれません。
はたして本当に蔡邕は董卓が殺されてショックを受けていたのでしょうか?
猛獣のような董卓を制御することから解放されてほっとしていたのではないでしょうか。王允が見たものは、蔡邕の安堵のため息だったかもしれません。
蔡邕、王允の死後、長安を出た蔡琰は匈奴に捕まり、左賢王の側室として12年ほどを過ごすことになります。やがて朝廷を掌握した曹操が使者を出して交渉し、蔡邕は解放されることになるのです。
蔡邕が逃避行を続けた期間と、蔡琰が異民族に捕らえられていた期間はほぼ同じだったようです。苦難に満ちた人生を歩んだ父娘の奏でる琴の音色はどのようなものだったのでしょうか。