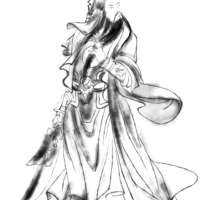劉備の流浪 手柄を立てても悪徳官僚に陥れられる
■ 劉備の流浪 手柄を立てても悪徳官僚に陥れられる
劉備の流浪 手柄を立てても悪徳官僚に陥れられる
黄巾党の「地公将軍」張宝は黄巾の乱を起こした「張角」の弟。実質的な「ナンバー2」でしたが、劉備は鉄門峡にて張宝を打ち取ります。同じ頃に張角は病死。もう一人の兄弟「張梁」も戦死。黄巾の乱は184年に終結します。
劉備(玄徳)は大きな手柄を立てますが、大した褒美も与えられず、一応「手柄」ということで、片田舎(安喜県)の尉に任命されます。「ナンバー2を倒した手柄」に対しては、あまりにも小さな「褒美」です。小さな村役人の収入では、今まで生死を共にしてきた「義勇軍」を養っていく事ができません。劉備(玄徳)はやむなく義勇軍を解散します。
さらに、ある時、洛陽から訪れた官僚から「中央の役人のもてなし方(賄賂の意)」を揶揄されるだけでなく、不条理な罪を仕立て上げ、陥れられそうになります。結局、劉備は安喜県から去ることになってしまいます。劉備(玄徳)、関羽(雲長)、張飛(翼徳)の志は、中央官僚の心無い扱い(手柄を過小評価)と、悪徳官僚の横暴によって、踏みにじられてしまいます。
乱れた現実より恐ろしい「普通のこと」という慣例
■ 乱れた現実より恐ろしい「普通のこと」という慣例
乱れた現実より恐ろしい「普通のこと」という慣例
劉備たちに大きな非はなく、明らかに「官」という組織の「上」にいる人物の過ちです。「官」の乱れによって、若い世代の志を潰しています。これでは近い将来に国が滅んでもおかしくありません。結局、三国時代の後に、「漢」は崩壊してしまいます。
しかし、物語を読んでいると、こういった「乱れ」についてもっと恐ろしく感じることがあります。それは、上に出てきた「中央官僚」や「悪徳官僚」たちに「悪意」があったかどうかです。どうも彼らが劉備(玄徳)たちに行った行為は悪意の下に行われたように思えません。彼らにとっては「普通のこと」だったのです。特に劉備(玄徳)に賄賂を迫った官僚などは、「それは、もてなしとして普通のこと」と思っていたのでしょう。
「かつては自分の上司もそうしていた」「その上の上司も…」「だからオレもやっている」「何か問題が?」
ってな感じでしょうか。約400年続いた漢王朝ですが、長きに渡って少しずつ腐敗に陥った果てが、この状況なのでしょう。
国の統治状態にはレベルがある
■ 国の統治状態にはレベルがある
国の統治状態にはレベルがある
国を統治する目的はたくさんありますが、その大きな目的のひとつは「弱者を守る」ことです。「強者による弱者からの不法な搾取」を防ぐために「法」を用いて支配します。これがなければ、世の中は単なる「弱肉強食」となり、動物の世界と変わりありません。人々を良識ある「法」によって「統治」する意義は大いにあります。そして、私が考えるに「統治状態」には、次のような「レベル」が存在します。
◆無政府の状態
⇒強い者が弱い者を力で制する。建設的な繁栄は見込めない。
◆群雄割拠の状態
⇒小さな国家での統治は行われるが、国家間の争いが多くなり、争いによる犠牲者が多くなる。
◆一族支配、一党支配の状態
⇒人々の生活は安定するが、政権の交代がなく官組織の腐敗、弱体化が起こる。結果的に政権の交代が達せられず崩壊する。国家は不安定になり「群雄割拠の状態」にレベルダウンする。
※三国志の時代は、このレベルに該当するでしょう
◆平和な政権交代可能の状態
⇒政権を担う人物、政党、団体等が複数存在し、適度な間隔で平和に政権後退が達せられる。官組織の腐敗、弱体化が起き難い。人々が長期的に安定した生活を送ることが出来る。
※アメリカやイギリスの「2大政党制」は、このレベルに該当するでしょう
2017年 衆議院選挙に見る日本の状況
■ 2017年 衆議院選挙に見る日本の状況
2017年 衆議院選挙に見る日本の状況
新しい政党の台頭、野党第一党の分裂等で話題となった今回の衆議院選挙ですが、現在の日本の状況は上記の「一族による統治、一党による統治」から「政権担当可能な複数統治」の状況に移り変わろうとしているように思います。
長く政権を担っている政党があり、その政党の一党支配の状況です。この状況から脱却すべく「政権担当可能な新たな政党」を作ろうとしていますが、今回もそれは叶いませんでした。現代でいう「ひとつの政党による統治」は三国志時代の「一族の統治」に相当するでしょう。長期化すれば、癒着、馴れ合いが横行して腐敗が始まります。そして行き着く先は「官の弱体化、国の弱体化、崩壊」です。
政権担当能力を持つ人物、政党が他になければ、当然、混乱が生じます。アメリカ、イギリスの「2大政党制」がすべて正しいとは言いませんが、日本にも「政権を担当できる団体」がもう一つほしいところです。
諸悪の根源たる十常侍討伐後も暗黒は終わらない
■ 諸悪の根源たる十常侍討伐後も暗黒は終わらない
諸悪の根源たる十常侍討伐後も暗黒は終わらない
後漢時代の諸悪の根源と言っても過言ではない「十常侍」。後漢末期の霊帝の時代に専権を振るった宦官の集団ですが、当時の大将軍何進(遂高)や袁紹(本初)によって打ち取られます。しかし、この時、たまたま皇帝の劉弁と劉協を保護した董卓(仲穎)が朝廷の実権を握ってしまいます。悪政の限りを尽くした董卓(仲穎)。三国時代となる直前の群雄割拠の時代を象徴する存在と言える人物です。
董卓(仲穎)が実権を握った頃、黄巾賊による反乱や朝廷の混乱は一応収まりますが、董卓(仲穎)が行ったのはまさに恐怖政治。私欲を満たすための行動しか取れない人物でした。当然、人々が平和に暮らせる世の中になどなる筈はありません。漢の暗黒の時代は終わりません。
三国志でよく使われる「官軍」という言葉、董卓(仲穎)は一応「官軍の将」です。この頃、朝廷の高官に買収を重ねて20万の兵力を誇る大勢力となっています。そうです。董卓(仲穎)のような軽輩でもお金の力によって大勢力に成長してしまった。これも「官の乱れ」を象徴するひとつの出来事と言えます。お金の力で勢力を伸ばし、呂布(奉先)を元の主君から引き抜き、朝廷の混乱に乗じて実権を握ってしまった。英雄の逸話としては、全くつまらない話です。
結局、董卓(仲穎)は頼みの綱だった呂布(奉先)に殺害されて生涯を終えますが、殺されてこんなに喜ばれた人物も少なかろうと思います。まぁこれぞ「自業自得」「因果応報」っていうモンですね。
まとめ
■ まとめ
まとめ
後漢末期の国の乱れ、その根源は「官の乱れ」です。十常侍をトップとする「高官」から「劉備(玄徳)」をいじめた低級官僚に至るまで、この時代の「官」は乱れていました。そして「役人」のみならず董卓(仲穎)に代表される「官軍」までもですね。最終的には「官の乱れを正し、皇帝を補佐するフリ」をした曹操(孟徳)が大きく台頭して行きますが…そして、曹操(孟徳)も「官軍の将」です…だめだこりゃ…ですね。