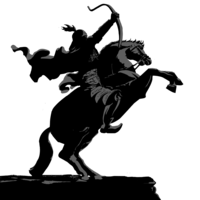猛将・張遼の息子とは【張虎】
■ 猛将・張遼の息子とは【張虎】
猛将・張遼の息子とは【張虎】
三国志演義では諸葛亮の北伐の際に魏軍の将としてよく登場するのが張虎です。父親は魏の名将の中でも筆頭にあげられる前将軍の張遼です。張遼はもともと呂布の家臣であり、曹操に降ってからも武功をあげました。合肥の戦いでは呉の孫権を絶体絶命の状態まで追い詰めています。孫権にとってはまさに天敵同然です。曹操の廟庭に祀られた二十人の功臣の一人ですし、唐代に選ばれた武廟六十四将の一人でもあります。そんな抜群の功績を積んできた張遼の息子ですから、当然のように重用されますが、三国志正史では張遼の家督を継いだことと、偏将軍まで出世したことぐらいしか記されていません。
三国志演義での張虎の扱いはひどく、諸葛亮の北伐に対し敗戦を重ね、捕縛されています。しかも衣服を脱がされ帰されるという屈辱を受けました。その姿からは父親の猛将ぶりはまったく見受けられません。また、237年に遼東の公孫淵が燕王を自称し、魏の毌丘倹を撃退しましたが、238年には司馬懿が張虎らを率いて公孫淵を討っています。このとき司馬懿は反逆の恐れがあるとして15歳以上の男子七千人を虐殺し、京観を築いたといわれています。
名将・楽進の息子とは【楽綝】
■ 名将・楽進の息子とは【楽綝】
名将・楽進の息子とは【楽綝】
張遼と匹敵する活躍を見せて、五大将軍の一人に数えられたのが魏の楽進です。張遼とは合肥の戦線で共に孫権と戦っていますが、不仲だったと伝わっています。楽進の子の楽綝も三国志演義では張遼の子である張虎と組んで蜀と戦っています。こちらは不仲だったとは記されていません。しかし諸葛亮の前では凡将として描かれており、敗戦を重ねています。
三国志正史では父親の楽進同様に武勇に優れた人物であると紹介されており、255年に起きた毌丘倹と文欽の反乱の鎮圧で活躍し、揚州の刺史に就任しています。257年に鎮東大将軍であった諸葛誕が司馬昭に対し反乱を起こします。三公の一つである司空に任じられ中央に召集されますが、諸葛誕はこれを怪しんで先制攻撃を仕掛けたのです。このとき諸葛誕が率いていた軍勢は十万を超えていました。楽綝は諸葛誕に討たれています。これにより楽綝は衛尉を追贈されました。
猛勇・許褚の息子とは【許儀】
■ 猛勇・許褚の息子とは【許儀】
猛勇・許褚の息子とは【許儀】
曹操の警護役として有名なのが虎痴の異名を持つ許褚です。典韋や馬超と互角の一騎打ちを演じて武勇を示しています。許褚の息子が、許儀です。許褚の家督を継いでいます。登場するのは魏が蜀を滅ぼす263年のことです。許儀は蜀を攻める総大将の鍾会に従い出陣しました。許儀は進軍先の架橋の任に就きますが、その橋を通過する際に鍾会の馬が躓き落馬してしまいます。鍾会はその責任を追及し、周囲の制止を振り切り許儀を処刑します。戦場での活躍はまったく伝わっていないのです。許儀の家督はその子・許綜が継ぎました。
大将軍・夏候惇の息子とは【夏候楙】
■ 大将軍・夏候惇の息子とは【夏候楙】
大将軍・夏候惇の息子とは【夏候楙】
曹操配下の中でも大黒柱だったのが夏候惇です。曹操が「不臣の礼」として魏の官位を与えなかったといわれています。あくまでも曹操は自分と対等な漢王朝の臣として最後まで夏候惇を扱ったのです。この夏候惇の息子として有名なのが、夏候楙です。三国志演義では夏侯淵の息子という設定で、夏候惇のもとに養子に出されています。字は三国志正史と三国志演義では異なっており、三国志正史では子林、三国志演義では子休となっています。三国志正史では養子とは伝わっておらず、夏候惇の次子として夏候惇とは別の爵位を授かっています。
夏候楙は曹操の娘を正妻としており、家督は継いでいませんが名門・夏侯氏の一人として重用されています。叔父の夏侯淵が219年に劉備(玄徳)の軍の攻撃を受けて定軍山で戦死すると長安近郊に駐在して蜀の侵攻に備えました。220年に曹操の跡を継いだ曹丕が魏の皇帝に即位すると、安西将軍となり関中の司令官を務めています。三国志正史でも三国志演義でも金儲けが好きで、武勇の面では暗愚であったと記されています。三国志正史ではそのため二代目皇帝である曹叡に洛陽に呼び戻されました。その後は女好きもたたって曹叡に処刑されるところでしたが、ギリギリのところで許されています。三国志演義では対蜀の司令官として諸葛亮の北伐に実際に対抗しています。しかし趙雲や魏延に侮られ、そのとおりに敗戦して捕らえられてしまいました。さらに解放された後は西方の異民族の地へ亡命し、魏には戻らなかったという設定になっています。
大司馬・曹真の息子とは【曹爽】
■ 大司馬・曹真の息子とは【曹爽】
大司馬・曹真の息子とは【曹爽】
曹操の親族として重用された曹真は曹氏の筆頭格として活躍します。諸葛亮の北伐に対しても大将軍として魏軍を率いて善戦しました。さらに大司馬に昇進しています。その息子が曹爽、字は昭伯になります。2代目皇帝である曹叡に寵愛されて出世し、曹叡が重病となると父親同様に大将軍に就任しました。そして司馬懿と共に次の皇帝となる曹芳の後見役を任されることになります。このときはまだ曹爽も司馬懿のことを父と慕っており、関係は良好だったようです。
しかし曹爽の取り巻きたちが司馬懿の失脚を画策し始めます。曹爽もまたその気になってしまい、司馬懿を名誉職であり実権のない太傅に昇進させて政治中枢から締め出しました。司馬懿は病を装い曹爽らの警戒を解き、249年に曹爽が外出した隙を突いてクーデターを起こします。曹爽は許されると思って抵抗せずに降伏しましたが、捕らえられた後に三族皆処刑されています。これにより曹氏の力は衰え、司馬氏の専政を招く結果となるのです。
まとめ・2世武将の活躍について
■ まとめ・2世武将の活躍について
まとめ・2世武将の活躍について
夏侯覇は以前お伝えしましたので、夏侯淵の息子以外の2世武将を紹介してみました。もちろん他にもいるのですが、ご紹介した武将については、父親ほど活躍できていませんね。有名武将の子もまた武勇に優れているのはなかなか稀なことなのかもしれません。そう考えると孫堅の息子の孫策や、馬騰の息子の馬超といったところはレアなケースなのでしょう。
ちなみに于禁、徐晃、張郃、曹仁、曹洪ら他の名将の息子についてはどうだったのかまったく伝わってもいません。やはり過酷な環境からしか武勇に優れた名将は誕生しないのでしょうか。このあたりが魏が早くに滅亡した原因なのかもしれません。