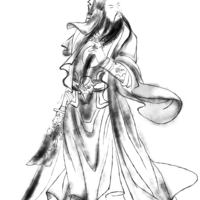反董卓連合を率いる主要人物
■ 反董卓連合を率いる主要人物
反董卓連合を率いる主要人物
袁術(公路)の一族は後漢の名門貴族である汝南袁氏で、父も高位の官僚でした。袁術(公路)も官僚となりますが、霊帝が亡くなると、大将軍である何進が十常侍抹殺を目論見、その反乱軍に参加しています。しかし、何進が十常侍によって暗殺されてしまうと、同族の袁紹(本初)と共に宮中へと侵入し、宦官らを粛清していきます。
その後、董卓が実権を握って都を制圧すると、袁術(公路)は将軍へ昇格し、そのまま都で生活しています。曹操(孟徳)が反旗を翻して洛陽から逃亡すると、共に何進のもとで兵を挙げた仲である袁術(公路)は、被害が及ぶのを恐れて荊州へと逃げ出します。
孫堅との関係
■ 孫堅との関係
孫堅との関係
袁術(公路)は豊かな土地である荊州を支配しようと、孫堅を利用していき、南陽太守に就任しました。反董卓連合では、袁術も孫堅を伴って南陽から進みます。董卓軍からは徐栄が進軍して曹操らを破ると、孫堅も敗退しました。このとき、孫堅軍は兵糧不足に陥っていますが、袁術は兵糧を届けるのを渋っていました。もともと小心者である袁術は第三者の諫言を信じ、孫堅を疎ましく思うようになっていたのです。しかし、孫堅が自ら袁術のもとへ迫ると、袁術はその気迫に押されて兵糧をすぐに届けています。
反董卓連合の主要人物となっていた袁術(公路)は、孫堅を巧みに利用して勢いを盛り返し、陽人の戦いでは呂布や華雄といった董卓軍の主力を退けています。董卓は洛陽を焼き払って長安に遷都していきます。
反董卓連合は次第に不協和になり、お互いが領土を専横し合う形になっていきました。名門出身である袁術(公路)と袁紹(本初)には多くの兵が集まっています。反董卓連合軍は自然と解散し、群雄が領土争いを演じるようになっていきました。時勢に乗り遅れなかった袁紹と袁術は、ともに2大勢力として君臨していくようになっていきます。
袁術(公路)は南陽に戻り、軍備を整えていきます。袁紹に味方する勢力を攻撃したのを受けて、袁術と袁紹は対立を深めていきました。南陽は人口が多く豊かな土地であったため、袁術は贅沢な生活を繰り返し、民衆には圧制をしいていきます。この頃から袁術に対して庶民や末端の兵はもちろん、配下の将に至るまで、不満が募っていくことになります。
曹操・袁紹・劉備と対立していく袁術
■ 曹操・袁紹・劉備と対立していく袁術
曹操・袁紹・劉備と対立していく袁術
袁術(公路)は孫堅(文台)に荊州南部の劉表を攻撃するように命令を下します。孫堅は終始優勢に戦況を進めていきますが、伏兵の弓矢によって戦死を遂げています。孫堅を失った軍は敗退に陥りました。袁術は長男の孫策(伯符)を預かり、劉表との対立を一向に深めていきます。
袁術は自ら出陣して陳留を目指しますが、袁紹(本初)と曹操(孟徳)の連合軍によって大敗を喫しています。さらに劉表には退路を断たれてしまい、本拠地である南陽を捨てることになってしまいます。袁術の身柄を確保したい曹操でしたが、袁術は揚州を攻略して陣取っています。
袁術は大敗後も未だに勢力を保ちますが、この敗戦を受けて曹操や袁紹のもとへ離反するものが増えていきます。特に徐州を支配していた陶謙は、最初袁術側に立っていましたが、曹操が台頭してくると、袁術を見限って劉備(玄徳)を取り入れるようになっていきます。陶謙が死去後、陳登ら配下たちは劉備を後任に推しますが、当の劉備は袁術を恐れて気が進みませんでした。結局は陳登らに推し進められ、袁紹と組んで袁術に対抗するようになっていきます。
孫策の台頭
■ 孫策の台頭
孫策の台頭
袁術(公路)は孫堅の長男である孫策(伯符)を寵愛していき、自身に造反する太守たちを退けたら孫策を登用する約束までしていました。孫策は野心溢れ、自分で敵太守を攻略した場合、後任を任せる約束をさせます。孫策は袁術に反感する太守を降伏させると、当然そのまま太守に就こうとしますが、袁術はそれを許さず自身の配下を抜擢しました。孫策は反感を覚え、次第に袁術から独立しようと考えていきます。
袁術は徐州に侵攻しようとし、背後を突かれないように孫策へ劉ヨウの攻略を任します。袁術は孫策の才能を恐れるようになり、兵をあまり持たせずに出陣させますが、孫策は周瑜(公瑾)を味方に付けて兵を増やし、父の代からの名将たちも配下に付けていきました。孫策は袁術軍が1年あまりかけて攻略できなかった劉ヨウ軍を破ると、江東を平定しようと画策し、袁術に劉ヨウの撃破の報告だけ済ませて、自身は独自勢力で領土を拡大していきます。袁術は孫策が攻略していった領土に自身の血縁を太守に任命していますが、孫策はこれを追い出して袁術と距離を図っていきます。
呂布を味方につける
■ 呂布を味方につける
呂布を味方につける
袁術(公路)は徐州の劉備を攻め、劉備(玄徳)は関羽(雲長)を伴って迎撃してきます。徐州の留守を任されたのは張飛(益徳)でした。同時期に呂布(奉先)が曹操(孟徳)に敗れて劉備陣営に身を寄せており、袁術は呂布が人に仕えて我慢している男ではないと見抜き、20万石もの物資を提供する条件で、劉備の背後を急襲するように画策します。
呂布はそれを受け入れ、張飛(益徳)を破って城を占拠します。行き場の無くなった劉備は退却して呂布に降伏しています。袁術はさらに劉備を攻めますが、助けを求められた呂布の仲介によって強引に和睦させられてしまいます。
自称皇帝を名乗る
■ 自称皇帝を名乗る
自称皇帝を名乗る
袁術(公路)は、献帝が行方不明になったことを受けて漢王朝が滅亡したとし、自身が皇帝になることを考え始めます。実際には曹操(孟徳)によって保護されており、袁術は逆に逆賊として扱われてしまいます。
激怒した袁術は、197年に皇帝として即位し、仲王朝を開きます。当然、諸侯は認めず、孫策は当初諌めるも聞く耳をもたない袁術に失望して完全に離反していきます。袁術は傲慢になり、宮殿を計画して浪費生活を送るようになり、民衆には重税を課していきました。袁術の家臣たちから離反するものも増え、反乱も起こり、次第に勢力が弱まっていくことになります。
袁術は呂布と婚姻関係を結ぼうとしますが、断られてしまい徐州へ侵攻しますが、呂布軍に大敗を喫してしまいました。曹操にも攻められて大敗し、袁術は一時の勢力を失い、国力や兵力も一気に低下していきます。
最期を迎える
■ 最期を迎える
最期を迎える
呂布(奉先)と曹操(孟徳)の対立が激化してきたことを受け、袁術(公路)は呂布と再度同盟を結びます。しかし、曹操によって呂布が討ち取られ、周囲に味方の無かった袁術は突然襲った飢饉の影響を受けて絶滅寸前にまで追いやられてしまいます。袁術は最後の望みとして同族の袁紹(本初)を頼りにし、自らの帝位を譲る条件で庇護を申し入れます。袁紹は受け入れますが、その道中に病を発病した袁術は、民衆にも食料の提供を断られ、部下の裏切りにも遭って199年に病死しています。
一時代を築いた袁術ですが、傲慢さを前面に推しだしたことで、暴君として周囲から離反者が多くなってしまいました。董卓・曹操・袁紹・劉備・呂布・劉表といった群雄の中でも勢力を最大に膨れさせた袁術はその性格が災いしなければ、天下を取って本物の皇帝として即位できたのかもしれません。