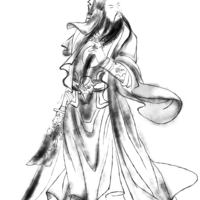四世三公の名門・袁氏
■ 四世三公の名門・袁氏
四世三公の名門・袁氏
袁術、字は公路。名門である汝南袁氏の出身です。父親は霊帝からの信頼の厚い司空・袁逢であり、袁逢の父は三公すべてを歴任した袁湯です。さらに袁湯の子の袁隗も司徒に二度就任しています。袁術はこのように三国志に登場する群雄の中でも抜き出た名士だったのです。汝南袁氏の家督は袁湯から袁逢に受け継がれ、袁逢の死後は長子である袁基が受け継いだといわれています。袁隗は充分に袁氏の長になれる器でしたが支える立場に徹したのではないかと見られています。
汝南袁氏の有名人では他に袁紹がいます。袁紹の出生は謎とされていますが、一説では袁湯の後を継ぐはずだったが早世した袁成の子であるとか、袁逢の庶子であるなど諸説あります。
兄である袁基の死
■ 兄である袁基の死
兄である袁基の死
袁術と袁紹といえば兄弟でありながら覇権争いを繰り広げたことで知られています。おそらく手を取り合っていれば曹操につけ入られるようなことはなかったでしょう。袁術と袁紹がなぜこうも反目し合ったのか、その理由については「汝南袁氏の長の座を巡る争い」だったと思われています。家督を継いでいた袁基が殺されてしまったために、家督が宙に浮いたのです。しかも汝南袁氏をまとめていた袁隗もまた同時期に殺されています。これで袁術と袁紹をコントロールできる人物がいなくなってしまったのです。袁基、袁隗を殺害したのは洛陽を占拠していた董卓でした。袁術、袁紹が反董卓連合を結成し、洛陽を攻めたために三族皆殺しになったわけです。反董卓連合を解散した後は、袁術と袁紹は他の群雄を巻き込んで本格的に対立を始めます。
袁術派の群雄
■ 袁術派の群雄
袁術派の群雄
袁紹は冀州を本拠地として勢力を広げていきます。手を結んだのは兗州の曹操、荊州の劉表です。これに対して袁術は、北方の雄・公孫瓚、徐州の陶謙と結びます。長沙の孫堅も袁術の心強い味方でしたが、荊州の劉表を攻めた際に戦死してしまいました。
こうしてついに武力衝突が発生するのです。袁術らは曹操の兗州を攻めますが、敗北。さらに袁術は本拠地にしていた荊州北部の南陽を劉表に押さえられてしまいます。
袁術は東へ落ち延び、揚州北部にある寿春を本拠地としました。
徐州の陶謙は曹操に攻められ、大勢の民衆も巻き添えになって虐殺されています。ここで曹操のいない隙を突いて兗州を乗っ取ったのが天下無双の呂布です。さらに徐州の陶謙は後を客将の劉備に託して病没します。
勢力図が変わろうとしていたのです。
揚州南部を占拠する
■ 揚州南部を占拠する
揚州南部を占拠する
袁術の後背を脅かすのが正式な揚州の刺史である劉繇でした。袁紹や曹操とも親しい仲です。袁術は長江以南の揚州南部を平定することを決意します。
ここで大将に抜擢されたのが、孫堅の遺児である孫策でした。孫策はわずか21歳にして一軍を率いて劉繇を攻めました。
孫策の武勇は劉繇軍を圧倒します。さらに呉郡を平定、会稽郡、予章郡、丹陽郡を吸収し、あっという間に勢力を拡大しました。これは袁術の支配地が増えたことを意味するのですが、孫策には自立の志があり、そのチャンスをうかがっているような状態でした。
197年に孫策が独立する
■ 197年に孫策が独立する
197年に孫策が独立する
驚くべきことが起きたのは197年の正月のことです。なんと袁術は皇帝に即位したのです。
このとき袁術は大義名分を「讖緯」という予言書に頼っています。そこには「漢に代わる者は、当塗高なり」と記されていました。袁術公路の「術」も「路」も、そして讖緯の「塗」もまた「道」の意味です。
こうして袁術一代限りの幻の王朝「仲」が建国されました。
漢王朝は曹操の庇護のもと健在であり、ほとんどの群雄が袁術の王朝を認めていません。それどころか配下の孫策は江東で独立を宣言することになります。
袁術は一転して大ピンチに陥るのです。そして他国に攻められ、国を失い、袁術は没します。
孫策が味方であれば
■ 孫策が味方であれば
孫策が味方であれば
もし孫策が離反しなかったら袁術はどうなっていたでしょうか?
袁術は孫策の兵を前面に押し出して戦ったかもしれません。孫策の父親である孫堅がそのように袁術に起用されています。
その頃の徐州は呂布に支配されていますが、こちらは袁術との姻戚関係の構築が計画されていました。
孫策の軍勢が健在であれば、呂布も自分の娘を袁術の息子に嫁がせることに異論はなかったかもしれません。徐州・揚州は袁術・呂布・孫策によって万全となるのです。
曹操が最も恐れた形でしょう。
兗州の曹操は押さえられず
■ 兗州の曹操は押さえられず
兗州の曹操は押さえられず
こうなると兗州の曹操は単独では到底太刀打ちできません。さらに冀州の袁紹が曹操に援軍を出せば、幽州の奥地に追い詰められていた公孫瓚も息を吹き返します。曹操、袁紹はまさに挟撃される形になるのです。袁紹と曹操の首を討ちもらしても、これによって兗州、豫州、冀州、青州と天下の半分は袁術派が手にしたことになります。
許都を落とした袁術は献帝を退位させて、漢王朝を強引に滅亡させることでしょう。天下にあるのは袁術が皇帝として君臨する仲王朝だけです。
袁術の次なる矛先は洛陽・長安方面と荊州です。ここまでくると荊州の劉表も対抗する手段がありません。袁術の仲王朝は破竹の勢いで全土を掌握していきます。
天下を統一した袁術は、功績のあった孫策、呂布、公孫瓚らが王となることを許したかもしれませんね。
まとめ・袁術の天下
■ まとめ・袁術の天下
まとめ・袁術の天下
三国志というタイトル自体が無くなってしまいますが、こんな結末も見てみたかった気はしますね。果たして「仲王朝」はどこまで続いていくのでしょうか。日本の卑弥呼は仲王朝に朝貢外交をしたでしょうし、聖徳太子らも「遣隋使」ではなく「遣仲使」を送っていたかもしれません。
こんな未来が、孫策の手綱さえしっかりと握っていたら、可能だったかもしれませんね。
しかし袁術は孫策の信頼をどんどん失っていき、離反されてしまうのです。
反乱した孫策は袁術領に攻め込んでいますが、袁術の子孫たちはなぜか生き残っています。娘は孫権の後宮に召されていますし、息子の袁耀もまた孫権に仕えています。皇帝を自称し、逆賊の汚名を受けることになった袁術ですが、その血は受け継がれていくのです。不思議ですね。
そう考えると孫策や孫権は袁術のことを心底憎んでいたわけでもなかったのかもしれませんね。きっと孫策を繋ぎとめる方法はいくらでもあったことでしょう。