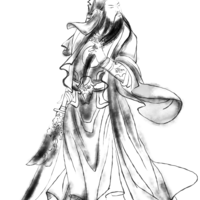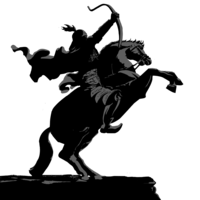孫堅の死後は袁術に従う
■ 孫堅の死後は袁術に従う
孫堅の死後は袁術に従う
孫策(伯符)はまだ16歳だった191年、孫堅(文台)を劉表との戦いで亡くし、名門出身で主家にあたる袁術(公路)によって孫堅軍が再編されました。孫策にはわずかな供がいるだけでとても父のように大軍を動かせるだけの影響力はありませんでした。
翌192年には、実力者の袁術に対して孫策は父の軍を返還するように求めています。まだ若い孫策に対して袁術は難色を示し、孫策は縁者を伝って挙兵しています。しかし、初の挙兵は失敗に終わり、民兵の反乱軍にまで敗れる始末でした。一度敗戦を喫した孫策は、軍を立て直し、民兵を鎮めています。
やがて袁術の下へと戻った孫策は、再度孫堅軍の返還を求め、袁術は1000人ほどの兵を送ります。少数でしたが、この中には孫堅軍の中枢を担った黄蓋や朱治、程普といった歴戦の武将がいました。
孫策は着実に力を蓄え、袁術の指示によって、各地を転戦していき、連勝を重ねていきます。しかし、太守の座を約束していた袁術は、孫策が制圧した土地を自身の配下や親族に分け与えていたので、孫策は袁術を見限るようになっていきます。
周瑜の参戦
■ 周瑜の参戦
周瑜の参戦
袁術(公路)の元を去る機会を覗っていた孫策(伯符)でしたが、自身の叔父が揚州を支配していた劉ヨウと対峙していると聞き、援軍に駆けつける名目で袁術から離れています。わずか1000人ほどの小軍でしたが、孫策の挙兵を知った昔馴染みの周瑜(公瑾)が兵を率いて駆け付け、周瑜の知人であった魯粛(子敬)も参戦しています。このときの孫策軍は数千人の規模にまで膨れ上がり、諸将には周瑜や魯粛の他に、周泰や諸葛瑾、陳武、凌操といった後の呉を支える重鎮が集っていました。
躍進を重ねる孫策
■ 躍進を重ねる孫策
躍進を重ねる孫策
孫策(伯符)は劉ヨウを直接攻めず、近隣の城から攻めていきます。まずは食料や軍需物資を奪取して、長期戦をできる体制にし、周瑜らと共謀して短期決戦で劉ヨウ軍を撃破していきます。
劉ヨウ軍からは宰相のサク融が参戦しており、孫策は自身が弓矢の狙撃に遭うと、死亡に見せかけて棺に運ばれる振りをしてサク融を騙し、追撃してきた劉ヨウ軍を伏兵で奇襲して多大な損害を与えました。そのままサク融の陣営を襲うと、恐怖のあまりサク融は後退して陣を固くして守りに備えています。
すると、孫策はサク融を無視して進軍し、劉ヨウ軍の別働隊を急襲して各県を支配していきました。その勢いは凄まじく、電光石火のごとく近隣を支配下に収めていきました。
劉ヨウを撃破
■ 劉ヨウを撃破
劉ヨウを撃破
孫策は劉ヨウ軍と対峙し、大いに破ります。このとき、劉ヨウ軍には武勇に優れた太史慈がいましたが、傘下になって浅い太史慈を優遇することに抵抗があった劉ヨウは偵察を命じています。太史慈は同じく偵察に来ていた孫策と曹禺し、一騎打ちを挑んでいます。両雄の決着は着きませんでしたが、孫策は太史慈の実力を認めて配下に欲しいと思い、太史慈も大将でありながら武勇も優れている孫策に興味が湧いていました。
太史慈を使いこなせないほどの劉ヨウ軍でしたので、孫策にとって攻略は造作でもなく、恐れをなした劉ヨウは逃げだしています。このとき、太史慈は劉ヨウ軍を離れて独立し、丹陽太守を自称しました。
劉ヨウ軍を吸収していく
■ 劉ヨウ軍を吸収していく
劉ヨウ軍を吸収していく
劉ヨウを撃破した孫策(伯符)は、一度矛を鎮め、貢献してきた配下の将兵に恩賞を与えます。さらに戦乱で荒れた土地に住む民のために治安の維持に努めて、民衆からの支持を得ていました。さらに孫策は、揚州全域に対して政令を出し、劉ヨウやサク融の配下でも降伏を申し出れば一切罪に問わず、それに従軍するものも罪にせず、その家族までも保護を約束しました。さらに従軍するのを断る人物がいても強制してはいけないことを打ち出しており、景気よくて信頼感のおける孫策の元へは多くの将兵が集まるようになっていきました。
三国志の時代には連座というのが一般的であり、罪によって処罰されると一族までも投獄されたり処刑されたりしていました。しかし、孫策はその常識を逆手にとり、自分に従うものはだれにでも門戸を解放し、従わないものはそのままでよいというスタイルで揚州の評判を得て治安を安定させていきました。
孫策の勢力は3万人ほどに膨らみましたが、袁術との対立は避けておくようにし、借りた兵を素直に返還しています。
江東平定へ
■ 江東平定へ
江東平定へ
その後、孫策(伯符)は呉郡と会稽郡を攻撃し、連戦連勝を重ねていきます。天下の名士といわれた王朗(景興)が太守を務めていた会稽郡に照準を絞ります。王朗は孫策を迎え撃つように準備して守りを固めますが、孫策は配下の進言もあって直接攻めず、周囲の城を落としていきます。
要となる守りの城を落とされた王朗は焦って配下に出撃命令を下しますが、すでに軍を分けていた孫策によって、防がれてしまいます。孫策は勢いに乗って本拠地も占領し、会稽郡を支配することに成功しました。城を脱出した王朗は船で逃れますが、元々水軍に強い孫策軍はすぐに追いつき、王朗は降伏を申し出ています。
王朗は謙虚で学識もあり、民にも善政を敷いていたので、孫策は処罰せずに解放しています。後に王朗は曹操(孟徳)に招かれて都へと仕えるようになり、孫策が指揮官として優れた人物であると曹操に進言しています。
以降も孫策に反抗する軍勢が出てきますが、孫策は自ら対処していきます。これによって江東に孫策ありという印象が天下にもたらされていくようになります。当然ながら孫策の活躍は袁術(公路)の耳にも入っており、その勢いを恐れるようになっていました。
袁術から完全に独立
■ 袁術から完全に独立
袁術から完全に独立
袁術はかねてから帝位に就くことを考えており、孫策は手紙を送って諌めていました。しかし、袁術は自ら皇帝と称すると、孫策は完全に独立を決意していきます。袁術配下の将兵では孫策に就くことものも現れ、さらに規模が大きくなっていきます。袁術は自分に味方する勢力に孫策を攻めさせますが、これをあっさりと撃破しています。
強大な地盤を確保して孫呉の基礎を築く
■ 強大な地盤を確保して孫呉の基礎を築く
強大な地盤を確保して孫呉の基礎を築く
孫策(伯符)は独立勢力の太史慈を捕えて配下に加えています。太史慈は敗残兵をまとめ上げており、さらに勢力が拡大していきます。孫策は父の仇である劉表を狙います。特に実質孫堅を死亡させたのは黄祖の軍でしたので、この一戦にかける意気込みは重く、孫策は周瑜(公瑾)と弟の孫権(仲謀)に黄祖を攻めさて大勝しています。
豊富な領土を抱える荊州を支配している劉表は、さすがに手強く、こう着状態が続いたので孫策はひとまず軍を引き上げます。するとまたしても反乱軍が勃発しますが、電光石火のごとく諸将を派遣し、周瑜や周泰らの活躍によって反乱軍はすぐさま鎮圧されています。孫策は自他ともに認める江東・江南支配者となっていきました。
孫策は25歳にして病に倒れてこの世を去りますが、わずか8年あまりの間にこれだけの功績を残しています。跡を継いだ弟の孫権は、孫策が築いた地盤を基にして領土を拡大していき、呉を建国することになります。孫策が長生きしていたら、孫権よりも好戦的だったために三国志の勢力図は大きく変わっていたのかもしれません。