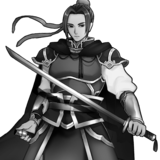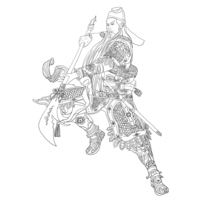劉禅の即位
■ 劉禅の即位
劉禅の即位
223年に劉備(玄徳)の息子である劉禅は皇帝に即位しました。蜀の二代目皇帝の誕生です。このとき劉備(玄徳)は60歳を過ぎていましたが、劉禅はわずかに17歳だったと伝わっています。隣国には巨大な魏が存在し、皇帝は経験豊富な曹丕。また老練な呉は曹操や劉備(玄徳)と覇を競い合った孫権が健在です。その中で戦場の経験も、政治の経験もほとんどない劉禅が蜀の皇帝に即位するのは不安要素だらけでした。しかも劉備(玄徳)を支えてきた五虎大将軍の関羽・張飛・馬超・黄忠ももはやこの世にはいないのです。そして最大のピンチなのは先代皇帝である劉備(玄徳)が関羽の敵討ちのために呉に攻め込んで大敗し、多くの将兵を失っていることでした。あらゆる面で蜀は危機的状況だったわけです。劉禅はその中で皇帝に即位したのです。2年、3年で滅んでおかしくはない状況だったといえます。
蜀のスーパーヒーロー
■ 蜀のスーパーヒーロー
蜀のスーパーヒーロー
しかし、蜀には三国志の英雄・諸葛亮孔明がいました。劉備(玄徳)が夷陵の戦いで大敗を喫したとき早速益州で反乱が起きますが、諸葛亮が迅速に対処しています。頼りない劉禅が皇帝に即位しても、諸葛亮がいるから大丈夫だろうという安心感はおそらく蜀にはあったのではないでしょうか。諸葛亮は蜀の丞相であり、益州刺史でもあり、実質的な蜀の統治者といっても過言ではありません。魏から盛んに諸葛亮に降伏を促す書状が届きますが、蜀漢復興の志がある諸葛亮はすべて無視します。劉禅も素直に諸葛亮を信頼しており、関係がギクシャクしたような場面はほとんどありません。悪く言うと政務はすべて諸葛亮に任せっきりの状態だったわけです。劉禅は完全に蜀の象徴的な存在になっていました。
大黒柱である諸葛亮の死
■ 大黒柱である諸葛亮の死
大黒柱である諸葛亮の死
そんな諸葛亮は過労によって病没します。234年のことです。劉禅が皇帝に即位してから11年が過ぎています。ついに劉禅は独り立ちしなければならなくなったのです。魏と呉に挟まれ、大黒柱の諸葛亮を失っても、蜀は滅びることなく存続し続けます。さらに諸葛亮の遺志を継いだ姜維が北伐を継続しました。諸葛亮を失ってもなお、劉禅は魏との戦争を続行したのです。魏を討伐し、漢を復興するのが建国の志とはいえ、大国の魏を相手にひるむことなく攻めた姿勢は立派ですね。しかし度重なる北伐によって蜀の人民は疲弊していました。なぜこうまでして魏と戦わねばならぬのか、魏に降伏した方が幸せなのではないのかといった意見や主張も在地の人民の世論にはあったのです。蜀は戦うことに疲れ果てていました。
263年魏の蜀への侵攻開始
■ 263年魏の蜀への侵攻開始
263年魏の蜀への侵攻開始
262年、魏の最高権力者は司馬懿の次男・司馬昭でした。そして蜀を完全に滅ぼすことを決意します。そして263年8月に蜀を討伐する大軍が洛陽から出撃しました。魏の部隊は大きく分けて三つになります。最西のルートを辿るのが征西将軍の鄧艾、武都を目指すのが雍州刺史の諸葛緒、そして最短ルートとなる子午谷道、駱谷道、褒斜道を辿って漢中を攻めるのが鎮西将軍の鍾会です。本来の魏の作戦は西の鄧艾・諸葛緒が姜維を引きつけている間に鍾会が成都を突くというものでしたが、姜維が巧みに兵を統率し漢中から成都に至る道筋にある剣閣に籠城したのです。鍾会は南下できなくなります。
しかし鄧艾が険しい山岳を突破し、蜀軍の予想外のところに出現しました。蜀の官民は皆、驚き慌てふためきます。冷静に考えると兵站のない鄧艾は持久戦ができない状況であり、援軍も剣閣で食い止められているわけですから、籠城戦を選択すればそう簡単には陥落しないはずなのですが、劉禅は無血開城を決断します。大胆な決断だともいえます。
成都を陥落させた鄧艾は、さらに呉も降そうと司馬昭に書状を送りました。これに対して鍾会は報告書を偽造して鄧艾を失脚させます。鄧艾は逮捕されて送還され、諸葛緒もまた鍾会に難癖つけられて送還されています。鍾会は成都に入り、姜維と結託。蜀の地で独立を画策しました。しかし司馬昭に動きを読まれており、慌てた鍾会は率いてきた武将たちの処遇をどうするか躊躇しているうちに反乱が起きて殺害されてしまいます。姜維もまた同じく殺されました。
洛陽に移る劉禅
■ 洛陽に移る劉禅
洛陽に移る劉禅
劉禅は呉に亡命したり、南蛮へ落ち延びる選択肢もありましたが、譙周の進言に従い潔く降伏することを決断しました。自分の身体を縛り、棺桶を担いで魏に降っています。それを受け入れた鄧艾や、その後に来た鍾会などは次々と失脚していきましたが、劉禅は家族とともに魏の都である洛陽に無事移されました。従った家臣は数名で、そこには郤正や張飛の息子である張紹の姿があります。司馬昭は劉禅を幽州の安楽県で安楽公に封じました。さらにその子孫を諸侯に取りたてています。劉禅は実際に幽州に移り住むわけでもなく洛陽で気ままに暮らしたようです。降伏した蜀の君主を優遇したのは、この後の呉討伐を楽に運ぶためだとも考えられています。呉の君主が降伏しやすい状況を演出したかったのでしょう。
まとめ・271年に劉禅死去
■ まとめ・271年に劉禅死去
まとめ・271年に劉禅死去
魏に降伏した劉禅でしたが、やがてその魏も司馬炎に禅譲して滅びます。劉禅は、今度は晋に仕えることになったのです。271年、劉禅は60歳を過ぎたところでこの世を去ります。後継者の選択で揉めましたが、最終的に劉恂が安楽公を継ぎ、異民族の反乱である永嘉の乱で亡くなったとされています。
約8年もの間、劉禅はどのような思いで、洛陽で暮らしていたのでしょうか。劉禅の洛陽に来てからのエピソードでは、宴会の席で蜀の音楽を聴き、家臣が泣いているのに劉禅一人は笑顔だったというものがあります。司馬昭が蜀への思いを訪ねたところ、「洛陽が楽しいので蜀のことは思い出しません」と答えています。郤正から「泣きながら、故郷にある先祖の墓を毎日思っている」と答えなさいとアドバイスもらったところ、そのまま演じ、司馬昭に郤正の言う事とそっくりですねと突っ込まれ、そのとおりですと素直に答えたとも伝わっています。暗愚さを見せることで、司馬昭からの警戒がすっかり解けました。
はたして劉禅の真意はどこにあったのでしょうか。それを示す記録は他に残っていません。