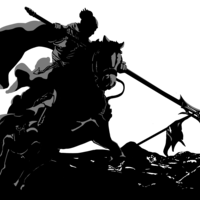劉備(玄徳)、仇討ちに失敗し病に倒れる
■ 劉備(玄徳)、仇討ちに失敗し病に倒れる
劉備(玄徳)、仇討ちに失敗し病に倒れる
献帝に禅譲させて魏を建国した曹丕(子桓)の皇位を認めない劉備(玄徳)は、諸葛亮(孔明)の献策により221年に蜀を建国し、初代皇帝となりました。裸一貫から天下統一レースをスタートし、少年時代からの大望であった皇帝への即位を実現した劉備(玄徳)でしたが、もはや残された時間はありませんでした。
関羽(雲長)、張飛(益徳)など劉備(玄徳)を旗揚げ当初から支えてきた者たちはこの世にはもういません。翌年、荊州奪還のため大軍を率いて呉と戦いますが、関羽(雲長)と張飛(益徳)の仇討ちに固執しすぎたためか大敗を喫してしまいます。
この時の戦況を人づてに聞いた曹丕(子桓)は「劉備(玄徳)は戦術のいろはも知らんのか」と嘲笑したと言われています。
敗戦のショックと二人の義弟の仇討ちが叶わなかったことが重なり、劉備(玄徳)の身体は病魔へ侵されていきました。やがて関羽(雲長)と張飛(益徳)の霊が劉備(玄徳)の前に現れ、「我ら兄弟が集うのもそう遠いことではないでしょう」と告げてたちまち消え去りました。
劉備(玄徳)の死に際には諸葛亮(孔明)の姿が
■ 劉備(玄徳)の死に際には諸葛亮(孔明)の姿が
劉備(玄徳)の死に際には諸葛亮(孔明)の姿が
義兄弟の霊からのお告げを聞き、己の死期を悟った劉備(玄徳)は息子の劉禅(公嗣)と諸葛亮(孔明)を蜀の首都だった成都から呼び寄せました。
劉備(玄徳)は身体を横へ向け諸葛亮(孔明)の手を取りながら「もし、私の息子が助けるに値する者ならばこれを助けよ。助けるに値せなんだら、君が代わりにこれを執れ。」と言いました。
諸葛亮(孔明)は落涙し、「これまで通り私は股肱の臣として忠義を尽くし、死をもって陛下の志の実現させます」と答えました。それを聞いた劉備(玄徳)は皇太子の劉禅(公嗣)とその兄弟に「私が死んだ後は、お前たち兄弟は孔明を父と思って仕えよ」と遺言し、ついに63年の波乱万丈な人生に幕を下ろしました。
劉備(玄徳)死後の蜀
■ 劉備(玄徳)死後の蜀
劉備(玄徳)死後の蜀
17歳という若さで父の後を継ぎ、2代目の蜀の皇帝となった劉禅(公嗣)でしたが、劉備(玄徳)の不安は的中してしまいます。2代目皇帝は凡庸な人物でした。しかし、諸葛亮(孔明)は劉備(玄徳)との約束を守り、魏の打倒と蜀の天下太平に向けて粉骨砕身な働きをします。
諸葛亮(孔明)の真価は、若き日の天才軍師としてよりも、むしろ丞相として活躍した劉備(玄徳)の死後にこそ発揮されたと言ってもよいでしょう。夷陵の戦い(先述した呉との戦い)で軍事力の大半を失い、また劉備(玄徳)の死に呼応して各地で内乱が勃発しました。本来は同盟関係である呉との敵対関係も決定的なものとなってしまいました。この絶体絶命のピンチに、諸葛亮(孔明)は鉄や塩の専売制や蜀錦などの殖産産業を興すといった政策で財政を立て直し、続いて南方の乱の平定、呉との外交関係の修復に努めました。こうして蜀は、三国鼎立の一角を維持することに成功します。
蜀漢2代目皇帝 劉禅(公嗣)はどんな人物か?
■ 蜀漢2代目皇帝 劉禅(公嗣)はどんな人物か?
蜀漢2代目皇帝 劉禅(公嗣)はどんな人物か?
偉大な創業者が一代で築いた身代を2代目が無能なばかりに没落させてしまうケースは数多いです。劉備(玄徳)の息子劉禅(公嗣)はその典型例でした。三国志における不肖の息子、暗愚の王の代表格として劉禅(公嗣)はその名を後世に残しています。かつて中国共産党の礎を築いた毛沢東は「国民はみな阿斗(劉禅の幼名)になってはいけない」という銘演説をしました。
諸葛亮(孔明)の死後、宦官の黄皓(おうこう)を寵愛して国事を省みず、父が建国した蜀を滅亡させました。三国の中で主役と言うべき蜀を真っ先に潰してしまったその罪は重いと言わざるを得ません。
劉禅(後嗣)のおまぬけっぷりは呆れるばかり
■ 劉禅(後嗣)のおまぬけっぷりは呆れるばかり
劉禅(後嗣)のおまぬけっぷりは呆れるばかり
劉禅(公嗣)は蜀を滅亡に導いた以外にもおまぬけなエピソードがあります。魏が蜀を滅亡させた後、劉禅(公嗣)らは洛陽へ連行されました。魏の司馬昭は劉禅(公嗣)を宴に招き、その場で彼らのために蜀の音楽を演奏させ、芸妓に蜀の舞を踊らせました。蜀の旧臣たちがみな涙を流しているのにも関わらず、劉禅(公嗣)はなぜかヘラヘラと笑っています。
司馬昭は半分冗談交じりで劉禅(公嗣)に「洛陽はどうですか?」と質問すると劉禅(公嗣)は涙を流している臣下に脇目もふらず「ここはめんどくさいことを考えなくてよいので、とても楽しいです」と笑い交じりに答えたそうです。
劉禅(公嗣)があまりにも空気が読めない様子だったので司馬昭もさすがにあきれてしまい「諸葛亮(孔明)が生きていたとしても、この男を補佐することはできなかっただろう」と語りました。
さらに司馬昭は劉禅(公嗣)に対して「少しは蜀のことを思い出したのではないですか?」と尋ねたときは「ここでの暮らしは楽しいので、蜀を思い出すことはありません」と平然と答えたといいます。これを見かねた蜀の旧臣の郤正(げきせい)が「あのように質問されたら、先祖の墓も蜀にあるので、悲しまぬ日はありません、と申してください」と諫めたので、やり直すためにもう一度司馬昭が同じ質問を繰り返すと、今度は郤正が言ったことをそっくりそのまま答えました。
司馬昭も驚いて「これはまた、郤正の言ったこととそのままですね」と言われると劉禅(公嗣)は驚いた様子で「はい、その通りです」と答えました。周囲にいた者はみな笑いましたが、劉禅(公嗣)はからかわれたことが理解できず、ひとりきょとんとするばかりでした。
劉禅(後嗣)は本当に無能なのか?
■ 劉禅(後嗣)は本当に無能なのか?
劉禅(後嗣)は本当に無能なのか?
これが事実だとすれば、劉禅(公嗣)は暗愚の王と呼ぶにふさわしい無能な皇帝ということになるでしょう。しかし、彼が本当に愚か者ならば、諸葛亮(孔明)にあれほど好き勝手にやらせ、一度は自ら失脚した諸葛亮(孔明)を復職させるようなことはしなかったと思います。劉禅(公嗣)が諸葛亮(孔明)の才能を認め、諸葛亮(孔明)に絶対的な信頼をおき、全権を託すくらいの度量を持ち合わせていたことが蜀には幸いでした。
司馬昭は劉禅(公嗣)の補佐は諸葛亮(孔明)でも無理と言いました。逆に蜀の2代皇帝が劉禅(公嗣)だったから諸葛亮(孔明)は丞相として輝くことができたともいえます。
遺言の背景にある劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)の確執
■ 遺言の背景にある劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)の確執
遺言の背景にある劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)の確執
ここまで全権を委任された諸葛亮(孔明)なら、その気になればいつでも劉禅(公嗣)を蹴落として取って代わることができたのではないでしょうか?
劉備(玄徳)は死の間際「息子が助けるに値しないならお前がなれ」と言ったです。劉禅(公嗣)が助ける価値のない人物であることは誰がどう見てもわかることだし、むしろ劉備(玄徳)の方から「お前がなれ」と言われているのだから自分が蜀の皇帝になってもなんの問題もないはずです。
しかし、諸葛亮(孔明)はそれをしませんでした。あくまで劉備(玄徳)との約束を守り、劉禅(公嗣)を助けました。
西暦234年の五丈原の戦いで最期を迎えながらもライバル関係だった司馬懿(仲達)を敵前逃亡させた「死せる諸葛、生ける仲達を走らす」の由来となった話はすさまじい執念が伝わってきます。もちろんこれらの話は諸葛亮(孔明)の忠義を示す美談として語り継がれています。
それなのに後世の人々の評価はというと、劉備(玄徳)に忠義を尽くした家臣といえば圧倒的に関羽(雲長)と張飛(益徳)の両名です。明末期~清代の学者である王夫之(おうふうし)は、劉備(玄徳)の遺言を「絶対に言ってはならないもの」と評価し、さらに「このことから劉備(玄徳)は諸葛亮(孔明)を関羽(雲長)ほどには信頼していなかったことがわかる」と結論づけています。それは劉備(玄徳)の遺言は遠回しに諸葛亮(孔明)が皇帝に即位することを警戒して、逆にそれをさせまいと釘を刺しているという見方もできます。
劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)との間にあった緊張感
■ 劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)との間にあった緊張感
劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)との間にあった緊張感
諸葛亮(孔明)の忠義という名の皮を剥がしていくと、劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)の間には微妙な緊張関係が露呈します。
劉備(玄徳)が存命中だったころ、諸葛亮(孔明)は劉巴(りゅうは)という名士を尚書令に任命しました。劉備(玄徳)は劉巴を嫌っていたのでこれに反対していました。かつて劉巴が、劉備(玄徳)の臣下になることを拒否して隠居した過去があったことを根に持ってのことでした。しかし、劉巴の才能を高く買っていた諸葛亮(孔明)はこの人事を強行しました。
尚書令のポストにはかつて法正という参謀が任命されていました。法正は知略に明るかったが執念深く恨みがましい性格だったので、諸葛亮(孔明)とは馬が合いませんでした。諸葛亮(孔明)の発言力が強くなりすぎないように劉備(玄徳)が諸葛亮(孔明)を牽制するための人事を行ったものと考えられます。
劉備(玄徳)の遺言にはこのように自分と諸葛亮(孔明)との間にある緊張感から生まれたせめぎ合いが背景にあります。確かにいくら自分の息子が無能だからと言って、ファミリー企業の社長が専務に対し「いつでも息子をクビにしていいから仕事を手伝ってやってくれ、ダメなら君が社長になってもいいよ」と言うのはあまりにおかしい話です。何か裏があったと考えるほうが自然ではないでしょうか?
まとめ
■ まとめ
まとめ
私は王夫之の論文を読むまで劉備(玄徳)と諸葛亮(孔明)は厚い信頼と忠義という鎖で固くつながっていたと思っていました。
しかし、王夫之の考えを読んだときまるで雷に打たれたかのような衝撃を受けました。「なるほど…劉備(玄徳)の遺言は美談だが、こんな見方をする人もいたのか」と。
諸葛亮(孔明)ほどの大物ならば国をよくするために皇帝との確執もいとわなかったことでしょう。最後まで皇帝になることなく、丞相として頑張っていたのは先代の劉備(玄徳)の恩義に報いるためと純粋な愛国精神からだったと私は信じています。