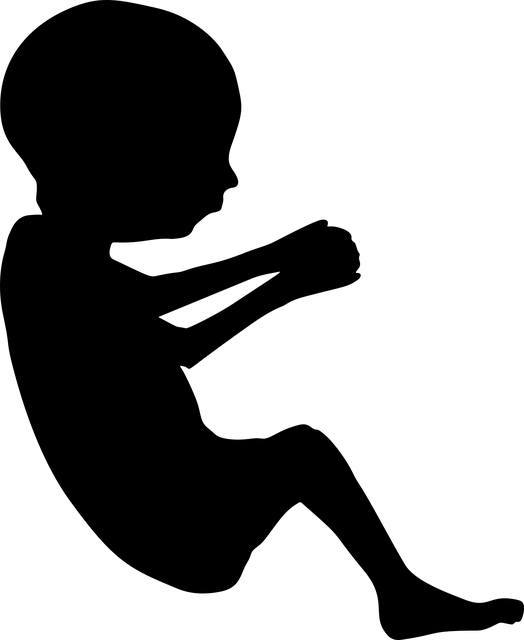ホントはもっと頑張ってた
■ ホントはもっと頑張ってた
ホントはもっと頑張ってた
華佗が手術や治療を行っているシーンを想像すると、毒矢を受けた関羽の手術だったり刺客によって全身ズタボロ状態になった孫策の手当をしているくらいにしか三国志演義には書かれていません。しかし、正史三国志や後漢書、古代中国の医学書を調べてみると華佗の医療実績に関する記述は意外と多いです。
本記事では、映画やドラマでは見ることができない華佗の医療実績を記載します。
似た症状が出た患者の病気を見極める
■ 似た症状が出た患者の病気を見極める
似た症状が出た患者の病気を見極める
李延と兒尋(にいじん)という郡司配下の下級役人が、2人とも頭痛と発熱があり、同じような病気にかかったと華佗に症状を訴えました。
華佗が言うには「兒殿は内側から、李殿は外側から病をえているので、治療の方法が違います」と病原と治療方法について説明をしました。そのあとで、李延と兒尋に別々の種類の薬を処方しました。2人が華佗からもらった薬を服用すると、翌朝には2人そろってたちまち病が癒えていたそうです。
陳登にバチが当たる
■ 陳登にバチが当たる
陳登にバチが当たる
孫策暗殺未遂事件の黒幕であるとも言われている陳登は江東地方の名士で、一時期劉備(玄徳)の配下として仕えていた時代があります。
破竹の勢いにのって、まるでドミノ倒しのように次々と勢力を拡充していく孫策のことを好ましく思っておらず、許貢の残党をけしかけて下手人を放ったのが陳登ではないかと言われています。
その陳登は、劉備(玄徳)の下を離れたあと広陵の太守に任命されてかの地に赴任していました。あるときひどい胸やけと顔じゅうが赤くなって食欲もないという奇妙な病気にかかりました。陳登は名医と名高い華佗を呼びに行かせて自身を診察させました。
華佗は脈をはかりとっただけでこのような診断を下しました。
「太守の胃の中に大量の寄生虫が巣くっています。このまま放置すれば寄生虫はどんどん太守の胃をむしばんでいき、将来腹部に潰瘍ができてしまうでしょう」
ギョッとしている陳登に向かってさらにこう続けました。
「これは…生の魚肉を食べたことが原因ですね~」
すると陳登は、
「先生、私は膾(かい:冷えた生肉に塩味をつけた料理)が大好物でね、魚を食べるときも刺身で食べるんだよ。そういえば、この前魚の刺身を食べたんだよ」
「きっとそのせいでしょう」
華佗はこのように言い切ると、2升(3.6リットル)の煎じ薬を煮出して、陳登に1升飲ませ、しばらく時間が経過するのを待ってからもう1升飲ませました。
それから四半刻ほど時間がたったころ、陳登はおよそ3升におよぶ血液と寄生虫を吐き出しました。その寄生虫はウネウネとうごめいており、マグロの赤身を千切りにしたような見た目をしていたそうです。
この治療の甲斐もあり、陳登の苦痛はすっかりなくなりました。ところが華佗は奇妙な予言を残します。
「太守はこれより3年後、同じ病を再発させます。私がそのときまで生きていられたら救えますが…さもなければ…」
陳登は華佗の言う通り、その3年後に同じ病を患いました。しかし、その時すでに華佗は曹操から受けた厳しい拷問の末にあの世へ旅立ってしまい、良い医者にかかることもできずに陳登は苦しみながら永遠の眠りにつきました。
手術する?しない?
■ 手術する?しない?
手術する?しない?
宮廷に仕える医官の長が、ある日突然厳しい腹痛に襲われました。これの診察を請け負ったのが華佗でした。華佗の診断結果によると、
「先生を悩ませている病根は、腹の深いところにあります。そのため、病根を取り除くには腹を切り開かなければなりません。腹部を切開した後、諸悪の根源となる腫瘍を切除するという手術を行います。ですが先生の場合、寿命がいくばくもありません。手術をしても天寿を全うするのに10年とかからないでしょう。手術をすれば治りますが、もし手術をしなければ今後もこの痛みは続きます。病根が強ければ10年も苦しむことはありませんが、病根が先生を死に至らしめることができなければ苦しみ続けて天寿が尽きるまで過ごすことになります。先生が病死するのと天寿を全うする時期が同じなのでわざわざ手術をしなくてもいいと思うんですが…どうします?」
長はあまりの痛みに耐えかねていたので、手術することを望みました。華佗が手術を成功させると病気はすぐに治りましたが、それから10年後華佗の言う通り長は寿命が尽きて永遠の眠りにつきました。
お腹に残留した水子を摘出
■ お腹に残留した水子を摘出
お腹に残留した水子を摘出
華佗が曹操の幕下に加わって間もないころ、李という姓の将軍が往診を願い出ました。なんでも将軍の夫人が重い病を患っていたようなのです。
李夫人の手をとり、脈を指ではかった華佗は不思議なことを言いました。
「将軍、奥方は流産されたようですが、まだ胎児がお腹の中におりますぞ」
「いかにも妻は流産したのだが、産婆の話によると既に子は流れ出たということだぞ」
と李将軍は答えました。
「はて…?しかしながら、奥方には妊婦特有の活脈があるので、子はまだ子宮内にいるはずなのですが…」
華佗は眉間にシワを寄せて、李将軍の顔を見上げました。
すると、華佗の言うことを信じられない李将軍は語気を荒げて
「それはおかしいぞ!!貴様は嘘をついて誤診をごまかそうとしているのか?」
と言って華佗を追い返してしまいました。
華佗が帰ってから李夫人は少しばかり回復しました。
ところが華佗が初診をして3か月が経ったころ、李夫人がまたもや発作を起こしました。そのため、李将軍は慌てて華佗を呼びに行きました。
「奥様の脈拍をみたところ、これは1つ子宮内に胎児がいること、2つ双子であることを示しています。おそらく1人目が流れた際に出血がひどく、奥方や出産に立ち会った者はもう1人残存していることに気付かずに出産を終えたのでしょう」
「そのため、2人目は出てくることができず、子宮内で息絶えました。お子の死体が夫人の腰椎の内側にへばりついて乾燥し、夫人の子宮内の水分を吸い取っていったため、そこがキリキリと痛み出したのです」
華佗の説明は、このように誠に信じがたいものでした。続いて、これからの治療方法を説明しました。
「これから奥方には煎じ薬を飲んでいただき、すぐに鍼灸術を背腰部に施します。さすればお腹に残っている子は出てくるはずです」
李夫人が薬を飲み、華佗が腰椎部に鍼を打つと、李夫人のお腹が痛みだしました。すると、華佗が
「このような子は乾いてしまってから長い時が経っておりますので、自分で出てくることができません。この類は、必ず人の手によって摘出するものなのです」
そう言うと、李夫人の子宮内に残っている水子を手で掴み、ズルンと引きずり出しました。
華佗の手には確かに胎児の形をした遺骸があり、四肢がしっかり揃い、肌の色は黒く、カラカラにミイラ化していました。
ただの医術ではない!?
■ ただの医術ではない!?
ただの医術ではない!?
エコー装置もないこの時代の医者は妊娠した女性にしか現れない活脈を読み取って、懐妊、流産、早産を判断したそうです。
しかも華佗の場合、患者の寿命や死期までも予言することもできました。そのためか、後漢書に書かれている華佗の医療技術に関する記述は「方術伝」という伝記にあります。
この「方術伝」は張角の太平道や于吉の五斗米道などの宗教、巫蟲(ふこ)やおまじないに関する呪いの方法が書かれている伝記になります。
このように華佗の医術は、魔法や呪いの類と同等に見られていました。設備や知識も乏しいこの時代、難解な病気をすぐに治したり、病気が再発する時期や死亡する時期を言い当ててしまう華佗のことを魔術師だと思う人も多かったことでしょう。