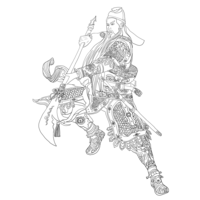三国志っていきなり国が三つに分裂して戦争するようになったの?
■ 三国志っていきなり国が三つに分裂して戦争するようになったの?
三国志っていきなり国が三つに分裂して戦争するようになったの?
三国志というと三つの国が覇権争いをしているようなイメージですが、実は一つの国の中で覇権争いが行われている状態でした。
これは日本の戦国時代を想像すると分かりやすいのですが、天皇は一人だったのに対し、戦国武将は何人もいて覇権争いをしていました。豊臣秀吉が天下統一を果たし、徳川家康が江戸幕府を築きましたが、その際も天皇は存在していました。
しかし中国の場合、220年に曹丕(士桓)(曹操(孟徳)の長男)が魏の皇帝になると221年に劉備(玄徳)が蜀を建国し皇帝になり、229年には孫権(仲謀)が呉を建国し皇帝となりました。
つまり三国(三人の皇帝)が誕生したのは229年のことになります。しかし、「三国志」と言ったら184年に起きた黄巾の乱からを指すことが多いです。
そのため「三国」とは後付けだと思ってもらって構いません。
なんで誰もが呂布(奉先)が最強って言ってるの?
■ なんで誰もが呂布(奉先)が最強って言ってるの?
なんで誰もが呂布(奉先)が最強って言ってるの?
三国志では「人中の呂布、馬中の赤兎」という言葉があります。これは「人では呂布(奉先)が、馬では赤兎馬が最強という意味です。もちろん「天下一武道会」などなかったため誰が一番強いかなんて判断は尽きませんが、彼が最強と言われる訳があります。
1つは董卓(仲穎)が、呂布(奉先)が強すぎて敵対する丁原をどうすることもできなかったからです。
絶対権力者である董卓(仲穎)には敵う者はおらず今にも帝位を脅かそうという状態でした。しかしそこに立ちはだかったのが丁原です。丁原は董卓(仲穎)の暴政を防ごうとし敵対しました。簡単にひねりつぶせると思った董卓(仲穎)ですが呂布(奉先)のあまりの強さに手も足も出ませんでした。そこでとった行動が「呂布(奉先)に赤兎馬を与えて自分の養子にする」という手でした。これがまんまとはまったわけですが、この際に呂布(奉先)の強さを垣間見ることができました。
そしてもう1つが一人で劉備(玄徳)、関羽(雲長)、張飛(翼徳)の三人を相手にしたという事です。関羽(雲長)は数々の猛者を葬るほどの手練れで、三国志で五本の指に入るほどの実力者です。そして張飛(翼徳)は関羽(雲長)が「自分より強い」と言ってしまうほどの猛者です。劉備(玄徳)は置いといてこの二人を同時に相手にできるのは呂布(奉先)しかいないため「彼が一番強い」という事に異を唱える人が少ないのです。
三国志って結局どうなったの?
■ 三国志って結局どうなったの?
三国志って結局どうなったの?
当たり前のことですが三国志には終了があり、最後は一つの国にまとめられることとなりました。そしてその一つにまとめた国というのが「晋」です。
ここで「あれっ三国志って魏・呉・蜀の話じゃなかったっけ?」と思う人がいるでしょう。確かに魏・呉・蜀が覇権を争った話な訳ですが、魏は途中国名を「晋」に変えています。
細かく言うとちょっと違いますが、感覚的には有能で発言権の強い側近が、あまり権威のなかった皇帝の帝位を簒奪したという感じです。
それまでの皇帝は三国志の覇者と言っても過言ではない曹操(孟徳)の子である曹丕(子桓)でした。しかし、曹操(孟徳)ほどのカリスマ性がなかったため司馬一族に徐々に追いやられる形となってしまったのです。
一方司馬一族は司馬懿(仲達)が丞相(国のナンバー2のポジション)となると息子の司馬師(子元)が大将軍となりました。さらにその司馬師(子元)のクーデターが成功し、国政の実権を握るようになり、弟の司馬昭(子上)が軍を掌握して代将軍となりました。
司馬昭(子上)の子である司馬炎(安世)が魏を廃止し、晋の皇帝の座に就いたわけです。
最終的にその晋が三国を統一したのでした。
三国志ってどれくらいの長さだったの?
■ 三国志ってどれくらいの長さだったの?
三国志ってどれくらいの長さだったの?
三国志は184年の黄巾の乱が始まったところから晋が呉を降伏させ中国統一した280年までの約100年間が三国志というわけです。
このためよく「OOは実は嘘だった」というタイトルに例えば「曹操(孟徳)は三国時代にはいなかった」というのが現れるわけです。(ちなみに曹操(孟徳)が亡くなったのが220年で翌年に息子の曹丕(子桓)が魏の皇帝のなったため)
ですが特に三国志を大まかに知ろうという人は年表を追う事よりもどんな人物がいたのか、誰と誰が争ってどちらが勝ったのかという大きな流れをつかんだ方がよりハマると思います。
諸葛亮(孔明)が亡くなったところが三国志の終わりじゃないの?
■ 諸葛亮(孔明)が亡くなったところが三国志の終わりじゃないの?
諸葛亮(孔明)が亡くなったところが三国志の終わりじゃないの?
これは結構勘違いされる人が多いのですが、諸葛亮(孔明)が亡くなったところが三国志の終わりではありません。
実は諸葛亮(孔明)が亡くなった46年後に晋が中国統一を果たしたのです。つまり、彼が亡くなったのは年表でいうと三国志のちょうど真ん中くらいです。
それにもかかわらずそういう認識がなされているのには日本で知れ渡っている吉川英治氏の「三国志」がほぼそこで終わりであとはダイジェスト的に書かれているだけだからです。
三国志の後半は前半と違って他国と戦争をするというよりは「内輪もめで内乱が勃発する」という展開が多いため前半のような面白みがないからそうせざるを得なかったのではないかというのが個人的見解です。
ちなみに三国志は全120回の話でできていますが、諸葛亮(孔明)が亡くなるのは104回(三国志一の名シーンとも言える「死せる孔明、生ける仲達を走らす」はこの回になります)のことですから、やはり前半の方が多く記述されていることになります。
いずれにせよ、諸葛亮(孔明)が亡くなった後もまだまだ三国志は続くのです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志について「いまさら聞けない」的なことを記載してみましたがいかがでしたか?
実は勘違いされていたことや、「そうだったんだ」という発見があれば幸いです。大まかな枠組みを捕らえてから細かいところを知ろうとした方が、圧倒的に理解度が高まるので、ネタバレではないですが、まずは結論から知った方がいいと思います。
その上でこの国が好き、この武将が好きというのが出てくればより「三国志をもっと知りたい」となっていくきっかけになることでしょう。
まずは100年くらいの歴史物語で一つの国で覇権争いが起こり、国が分裂し、晋が最終的に一つの国に統一した。と覚えるといいかもしれません。