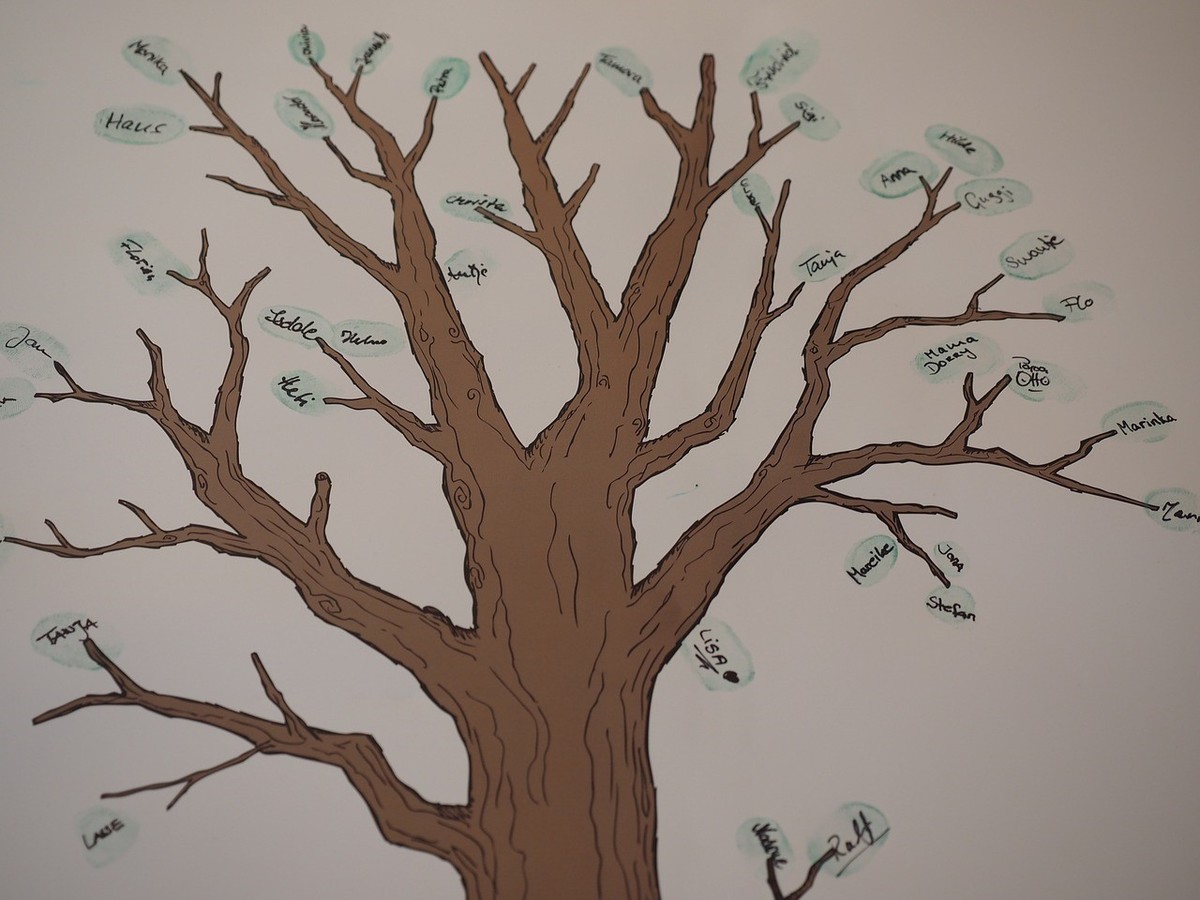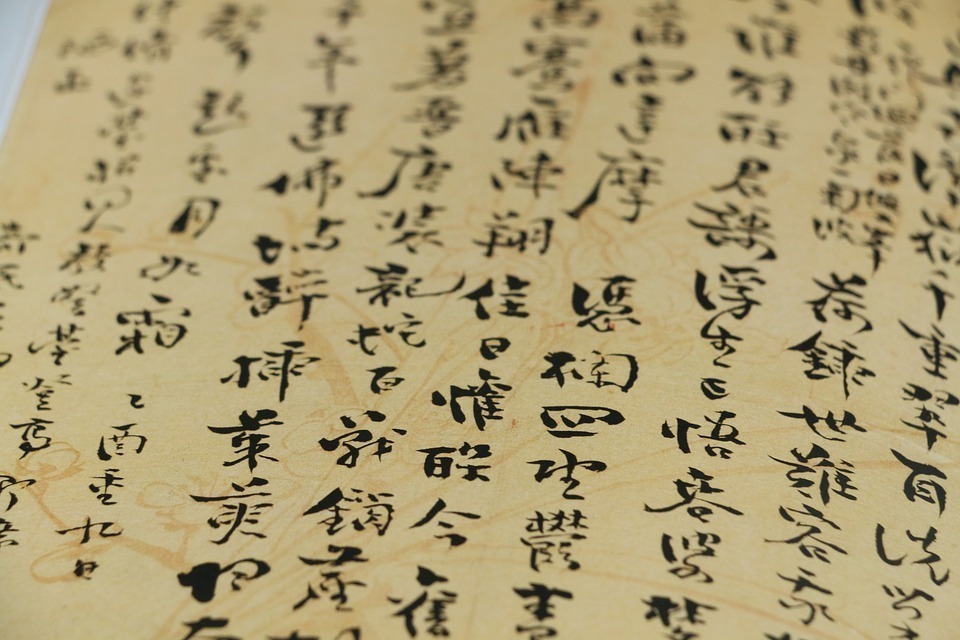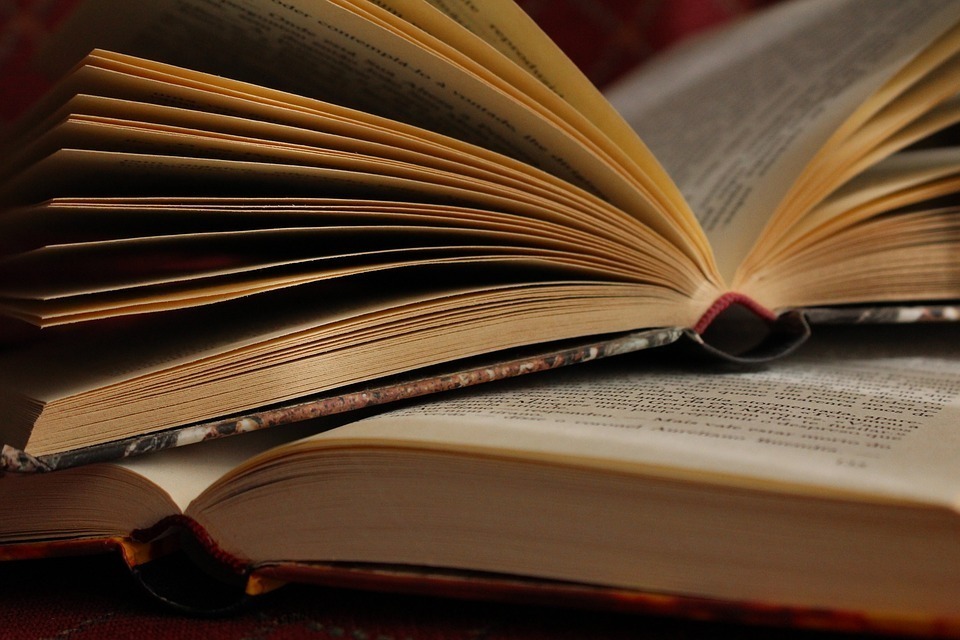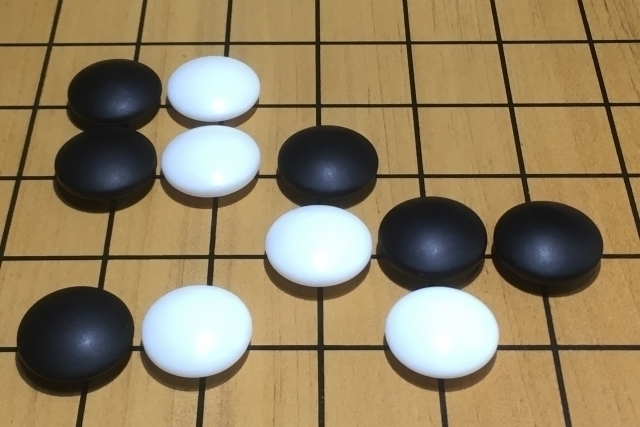一族の血を残すことの重要性
■ 一族の血を残すことの重要性
一族の血を残すことの重要性
戦国時代に重要視されたのは主君への「忠」よりも、先祖への「孝」だとされています。
先祖代々受け継いできた血脈を守るために、孝子は忠臣として主君に仕えるのです。
逆の言い方をすると、一族の血脈を守るためには、愚かな主君であれば裏切っても構わないということになります。背に腹は代えられないからです。
それが「良禽は木を択んで棲む」という、主君選びを正当化する言葉となったのでしょう。
しかし、実際のところ君主の能力が優れていても、滅ぶ時は滅ぶものです。そこには天運が係わってきます。勝負は時の運ともいいます。誰が勝ち、誰が繁栄するかは、断定できないのです。
そこで古来より、一族を分散し、別々の主君に仕えるという方法がとられてきました。互いに敵同士になる可能性もあるということです。
親子、兄弟で殺し合いをすることになりますが、確実にどちらかは生き残り、子孫を遺すことができます。
徳川と豊臣に分かれた真田家
■ 徳川と豊臣に分かれた真田家
徳川と豊臣に分かれた真田家
日本でもこのような事例は多々ありますが、有名なところでは、信濃の豪族・真田家があげられるでしょう。
「表裏比興の者」の異名を持つ知勇兼備の武将・真田昌幸は、武田信玄に仕えた後、これを滅ぼした織田信長に仕えました。本能寺の変で織田信長が死ぬと、豊臣秀吉に仕えています。そして豊臣秀吉の命令で、敵対関係にあった徳川家康の与力となりました。
豊臣秀吉が死ぬと、徳川派と反徳川派で「関ヶ原の戦い」が起こります。このとき、真田昌幸は次男・真田信繁を引き連れ、反徳川派についています。しかし、長男・真田信幸は徳川側について戦っています。
勝敗は徳川派の勝利。真田昌幸と信繁は流罪。真田信幸は真田信之と名を改めて、上田藩主となり、真田一族の血脈は守られ、明治維新後まで続くことになったのです。
荀一族の分散
■ 荀一族の分散
荀一族の分散
それでは三国志の時代、有能な士を多く輩出してきた荀彧の一族はどのような選択をしたのでしょうか。
荀一族は、もともと豫州潁川郡に住む名門の一族です。荀彧の父の代は、兄弟が八人おり「八龍」の異名を持つほど優秀でした、
この八龍には、荀彧の父親である荀緄の名がありますし、荀爽の名もあります。荀倹は、その子・荀悦が有名です。それ以外の同族にも荀攸がいますし、荀彧の弟の荀諶もいます。
しかし、そのほとんどが故郷の潁川を追われることになるのです。
後漢末期の混迷、戦乱が荀一族をバラバラにしたのでした。
荀爽の選択(董卓派)
■ 荀爽の選択(董卓派)
荀爽の選択(董卓派)
荀爽は八龍の中で、最も優れているという評判でした。朝廷に仕え、黄巾の討伐の際にも活躍しています。
その荀爽を最も高く評価したのが、朝廷の混乱に乗じ、洛陽の都を占拠した董卓です。
董卓は荀爽を地方の相に任じた後、矢継ぎ早に光禄勲、そして三公のひとつである司空に昇格させています。
荀爽は王允らと共に董卓を討つことを画策していたとも言われていますが、長安遷都時にも董卓に従い、その地で病没しています。董卓に逆らったという事実はありません。
荀攸の選択(朝廷派→曹操派)
■ 荀攸の選択(朝廷派→曹操派)
荀攸の選択(朝廷派→曹操派)
同じように朝廷に仕えていたのが、黄門侍郎の荀攸です。
荀攸は董卓を暗殺することを企てますが、事前に露見し捕まりました。死刑も確定していたのですが、直前で王允と呂布によるクーデターが成功し、命をとりとめています。
その後、荀攸は益州へ赴任することを望み、蜀郡太守に任じられましたが、益州では牧である劉焉が独力勢力を形成しており通行を制限していました。
荀攸は益州に辿り着くことができず、隣州の荊州で足止めされています。
ちょうどこの時、許都に献帝を迎えた曹操から招聘されました。以後、曹操の陣営の筆頭軍師として活躍をしています。
三国志演義では、曹操が魏王に封じられる際に反対し、怒りを買った設定になっていますが、三国志正史には一切そのような記載はありません。
荀諶の選択(袁紹派)
■ 荀諶の選択(袁紹派)
荀諶の選択(袁紹派)
董卓が洛陽を焼き尽くした際に、潁川にも被害が及ぶことを恐れ、荀彧は一族を弟の荀諶に率いさせて冀州に向かわせました。ちょうど潁川出身の韓馥が冀州牧に就任しており、潁川で人材を募集していたのです。
しかし冀州は袁紹が目を付けていました。
荀諶は辛評、辛毗、郭図、郭嘉らと共に冀州を目指していましたが、到着前に名士・何顒に招待され、そこで袁紹に仕えることを勧められたのです。
荀諶は袁紹の家臣の列に加わり、袁紹の親族のひとりである高幹と共に、韓馥を説得する使者となります。そして北の公孫瓚の侵攻を防ぐためにも、印綬を袁紹に譲るべきだと説き伏せました。
以降、荀諶は袁紹の重臣に名を連ねることになるのですが、三国志正史・演義ともに存在は消えてしまいます。
荀彧の選択(曹操派→?)
■ 荀彧の選択(曹操派→?)
荀彧の選択(曹操派→?)
荀彧は荀諶を先行させた3ヶ月以上後に冀州に入りました。
最後まで潁川で住民の避難に尽力しましたが、故郷を離れることに応じる者が少なく、最終的には董卓配下の李傕の略奪を受けて多くの住民が殺されています。
荀彧が冀州に入った時には、牧は韓馥から袁紹に代わっていました。もちろん荀彧も袁紹に仕官するよう勧められます。しかし、荀彧はこれを断り、黄河を渡って兗州に向ったのです。
恐らく袁紹のもとには弟の荀諶がいるので、自分は他の勢力に仕えた方が良いと考えたのでしょう。
兗州東郡を拠点にしていたのが、何顒に高く評価されていた曹操です。
曹操は、191年に荀彧に会い、「吾の子房なり」と大いに喜び、すぐに司馬に任命しました。
子房とは、漢の高祖(劉邦)を補佐した張良のことです。
何顒もまた南陽郡の太守を務めていた時に、荀彧を「王佐の才あり」と評しています。
こうして荀一族は別の地で、別の主に仕えたのです。
まとめ・荀彧は最期に曹操と袂を分かつ
■ まとめ・荀彧は最期に曹操と袂を分かつ
まとめ・荀彧は最期に曹操と袂を分かつ
曹操を選択した荀彧の人を見る目は、卓越したものだったといえるでしょう。
曹操は荀彧の協力もあり、兗州を張邈や陳宮、呂布の反乱から守り抜き、袁紹との戦も諦めることなく死力を尽くして戦い、勝利を収めることができたのです。
そして天下統一に最も近い英雄となりました。
まさに荀彧は王佐の才です。
荀彧は荀攸や郭嘉、陳羣、司馬懿、王朗なども曹操に推挙しています。荀彧なくして曹操の偉業は成し得なかったことでしょう。
しかし、最期には曹操の魏公即位に反対し、曹操の怒りを買って自害したと伝わっています。これだけの貢献をした荀彧でしたが、魏の官位を受けていないため、曹操の廟庭に功臣の一員として祀られることはありませんでした。
魏に仕えるのは同族の荀攸に任せ、自分は後漢と共に滅びる道を選択したのかもしれません。逆に曹操が粛清され、後漢が再興されるという可能性もあったからでしょう。
荀彧は最期まで一族の血脈を閉ざすことのないよう選択したのではないでしょうか。